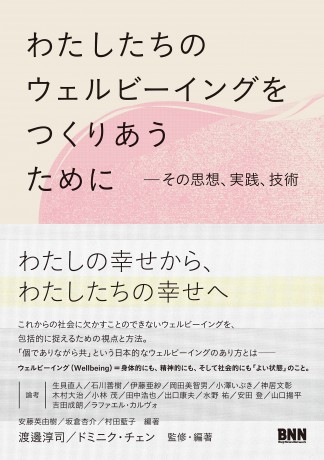―言語を介して、知らない景色を想像する楽しみを覚えていったんですね。
ドミニク:そうですね。その原体験から、ただ単にネガティブな意味ではなく「わかりあえなさ」をデフォルトにした考え方が自然とベースになっていって。コミュニケーションというのはすれ違いから出発するので、100%わかりあえるということは現実ではほぼないけど、一瞬でもわかりあえたと思えること自体が奇跡的なのだという感覚ですね。あとは、幸運なことに両親が「こうならないといけない」 というイメージを押し付けるようなタイプではなかったことで、自分のペースで好奇心を持って言語や関連する事柄に対する興味を深めていけたように感じます。自分がいざ子育てする身になって思い返すと、すごくありがたいことでした。
―そこからビジュアルやデザインのような非言語の分野へ関心が広がるようになったのはいつ頃でしょうか?
ドミニク:非言語の表現にものすごく惹かれたのは、同じく幼少期におじいちゃんの形見としてもらった銀塩フィルムのカメラがきっかけです。まずはそのカメラ自体におもしろみを感じて、フィルムを巻いて近所の公園を撮りにいっては、お小遣いで現像に出してみて。でもまあ、大半が失敗してなんだこれってなるんですけど(笑)、その分うまく撮れたときに、写真を家族や友人に見せることでいろいろなフィードバックが返ってきたのがおもしろかったんです。言葉でのコミュニケーションとまったく違うやりとりが生まれたことで、よりおもしろさや喜びを感じるようになりました。その後、家にあったマッキントッシュとスキャナーを父親が使っていない間にこっそりといじっては、取り込んだ写真をPhotoshopで変形させて一枚の絵にする遊びを10歳頃から始めました。
―もはや作品制作ですね。学校の同級生も同じようにパソコンやソフトで遊んでいた時代ですか?
ドミニク:いや、それが誰も理解してくれる友達なんていなかったですね(笑)。一方で、この時代はインターネットであらゆる世界の人々が立ち上げたウェブサイトがたくさん見れるようになった時代でもあって。すごく素朴な感想なんですけど、 初めてインターネットに接続してウェブサーフィンをしたときに、「この画面の向こう側にこんなにたくさんの人がいるんだ」って感動したことを覚えてます。住んでいる現実世界とは違う世界があって、そこにアクセスできることに幸せを覚えつつ、さらにそこに自分みたいにPhotoshopで加工した写真作品をアップする人たちがいたんですよ。そういう同好の士が集まるサイトに自分も作品を投稿してみたら、ある日トップページに掲載されて。嬉しくてみんなに自慢したいから、学校の友達に「見て見て! これ俺の作品!」って図書館のパソコンの画面に映る自分の作品を見せたんですけど、「へーそうなんだ」くらいの薄いリアクションしか返ってこなくて(笑)。
―インターネットで体感した熱量が現実世界だと違うものになってますね(笑)。
ドミニク:でも、このときの経験がインターネットの可能性の本質でもあるように思いましたね。現実空間で自分にとって大事な価値観を共有する人がいないときに、インターネットがあることは救いになりました。言語の世界はおもしろさもあるけどやっぱりすごくストレスフルでもあったから、そのインターネットの原体験は新たなフィードバックをもらえるものとして、非言語のおもしろさに気づけた大きな体験だったかもしれません。そこから表現を学ぶためにデザイン学科のある大学に通うようになりました。
―わたしも転勤族だったので、方言や地域の独特なリズムを掴むおもしろさの一方で疲れることもあって、ネットを介して人と交流する未知な体験に救われた思い出があります。
ドミニク:牧歌的なインターネットの時代でしたよね。今はインターネットについて研究者の視点から語ろうと思うとどうしても社会問題となっているネガティブな事象に目が向きがちですけど、同時に現在もそういう救いになる幸せな邂逅がたくさん起きている。こういうふうに各々の原体験を話すことで、いい思い出も思い返せますよね。