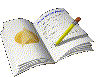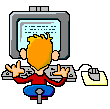昨日ネイリスト技能検定を受けたのだが、どうも落ちた気がする。合格を確信しているか、落ちたに違いないと諦められているならば気が楽なのだが、「気がする」程度だから昨日からずっと落ち着かず、脳みそのはしっこのほうがうるさい。合格かもしれないし、不合格かもしれない。そのどちらの地上にも着地できずに、どちらでもない、あるいはどちらでもあるとさえ思えるこの居心地の悪い空中は、一体なんという場所だろうか。
昨日までの出口調査速報を伺うに、僕が応援している参議院選の立候補者はどうやら当落線上、つまり当選するかもしれないし、当選しないかもしれない瀬戸際にいるらしい。昨日まであんなにけたたましかった選挙カーの声も聞こえず、選挙当日なのに最も静かな朝が少し不気味にさえ思える。この選挙期間を振り返ると、苦しかったという言葉が最初に浮かんでくる。これまでも選挙の結果を見て苦しくなることはあったが、選挙期間がこんなにも苦しかったのは初めてだった。ともにこの国で生きている人を生まれながらの属性で切り分け、それらに優先順位をつけるような言葉が平気で口にされた。国民主権の原則や人権を軽んじ、核武装や戦争を正当化するような言葉が政治家の口から飛び出したこと、そして彼ら彼女らがあろうことか当選見込みであることに寒気がした。政治が生み出した不安に付け込み、その不安の原因はここだと「敵」を作り上げる、そのためになら現実を捻じ曲げ、過去を捏造し、ありもしない未来をでっち上げることすら厭わない人たちが国政に携わろうとしていることに目眩がした。日本国籍を持ち、日本語を理解し、日本人だとみなされる我々が、この国でファースト扱いをされなかったことがあっただろうか。
気候変動対策に関する議論さえ十分になされなかったこの選挙期間のフィナーレにふさわしく、焦げ付くような灼熱の道を歩きながら投票所へ向かう。踏み締めるアスファルトの熱が、靴底を通してジリジリと伝わってきた。同じタイミングで投票所に集まってきたのは10人程度だっただろうか、彼らはどんな思いでここに辿り着いたのだろう。会場で投票用紙を受け取り、一画一画、慎重に候補者の名前を書き込んでいく。角ばった鉛筆の面は、どの角度で握っても座りがわるい。いつもは雑に書いてしまう文字も、ここでは「とめ・はね・はらい」に気をつけて、ゆっくりと、自分の選択を確かめるように、黒鉛をすべらせていく。お世辞にも綺麗とはいえないその筆跡は、不格好ながらも迷いはないように見えた。そっと折りたたんだ投票用紙を手でつまんで、投票箱の真上でパッとその手を離す。その瞬間から、その投票用紙は僕が書いたものだという判別がつかなくなり、他の票と同じ「一票」として、カウントの対象となってゆく。僕と同じタイミングで来た人たちが、ちょうど同じタイミングで会場から出てくる。彼らが誰の名前を書いたのかはわからない。わからないまま僕たちは、近所のスーパーマーケットで同じ買い物カゴを共有し、野菜の値段の高さに同じように驚いたりしているのだろう。
炎天下から逃げ込むようにして戻った自分の部屋は、エアコンの冷気に満ちていて、罪深いほどに快適だった。夜に韓国の映画を見に行く予定があったので、積読にしていた『隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ(著・斎藤真理子)』を本棚から引っ張り出し、読み始める。日韓翻訳者である筆者が、韓国語と日本語のあいだで二つの声に耳を澄ませながら、言葉にできるものは言葉にし、言葉にできずにするりとこぼれ落ちたものたちからは目を逸らすまいとする心情を綴った本だ。ふたつの言葉のあわいの只中に取り残される筆者の孤独と、そこに静かにとどまり続ける誇りに想いを馳せる。
隣の国である韓国と日本の関係についても学ぶところが多くあった。何かと何かのあいだに立って関係性の中に身を置こうとするとき、そこにはしばしば権力関係や加害関係が存在していて、加害者側があいだに立つこと自体が暴力になることもある。日本と韓国の例をとっても、両国の関係性や韓国の文化を語る上で、日本の植民地支配の歴史を抜きにすることはできないだろう。あいだの場所に立つことをやめることなく、けれど同時に、自分の立っている場所の地中に何が埋まっているのかを考えることもやめない、その危うい平衡感覚から背を向けないでいることが、旧宗主国である日本に生きる自分に求められているのかもしれないと思った。そういえば、在日コリアンとして暮らす人々にとっても、きっとこの選挙期間はさまざまな想いが交錯していたことだろう。選挙権が与えられていない人も多くいるだろう。彼らはどんなことを思い、どんなことを思わなかっただろうか。すべては想像に過ぎない、それでも、想像をする時間だけが、二つの国のあいだに自分の身を晒すことを許してくれるような気がしてしまうのだ。
日没の時間帯が訪れ、空の端から端までが、オレンジから青色へのグラデーションで覆われていく。映画館に向かう電車の中で、家族とLINEをした。親戚が亡くなり、翌日葬儀に向かうことになっていたのだが、その段取りと葬儀会場の様子を確認したかったのである。今、ばあばの体はどこにあるのか、という内容を尋ねようとして、少し考えた後「今、ばあばはどこにいるの?」と送信した。事実として、ばあばはもう息を引き取っているのだから、「ばあばの体」がそこに「ある」と言っても文法上の間違いはないのかもしれない。けれど、「ばあば」がそこに「いる」と言う方が、ずっと正しいような気がした。お骨になった姿を見ても僕は、「いる」と言い続けるのだろうか。「ある」の領域と「いる」の領域は距離をとって分布しながらも、その境目に目を凝らすと確かに重なった領域があって、その範囲においては文法というルールの効力がすこしだけゆるい。そこには「ある」でもあって「いる」でもあるようなものたちがあちこちに並んでいて、その中に横たわるばあばの姿が見える。
お目当ての韓国映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』を観に日比谷に到着。ビルとビルのあいだから顔を覗かせる空は、すでに一面が黒色に塗られていた。選挙の開票は、ちょうどこの映画の最中に始まるらしい。数時間後に明らかになる選挙結果から目を逸らすようにしてスマホの電源を消し、バッグの奥にしまい込んだ。数分して、会場が暗くなる。この映画は、ゲイの男性とヘテロセクシュアルの女性の二人が、異なる境遇に置かれながらも、だからこそ強く生まれる紐帯を描く作品だった。ゲイが置かれているホモフォビックな状況と、女性が置かれている女性蔑視的な状況、それらがときに重なったり、重ならなかったりしながら、共鳴したと思ったら次の瞬間には分かり合えなくなるような時間を重ねていく二人。それでも、相手の手を最後まで離さないという意思は終始貫かれていて、互いの幸福や不幸の大小を比べることなくラストシーンまで全力で駆け抜けていく。終盤は涙が止まらなくて、けれどそれが何の涙なのかは最後まで不明だった。大人になってからというもの、一つの感情だけで泣くことはほとんどなくなり、愛おしいのか憎いのかわからないときや、ハッピーエンドなのかバッドエンドなのかわからないときにばかり泣いている。この映画を見ている時の僕もその例にもれず、社会に対する絶望の気持ちも希望の気持ちも、どちらもないまぜになっていたのだと思う。それは、絶望の中の希望とも言えるし、希望の中の絶望とも言えるのだが、この時だけは、絶望の中の希望なのだと言い切れる強さを自分の中に感じた。
映画館から駅までの短い距離を歩きながら頭の中で感想を整理し、地下鉄に乗車するやいなやスマホの電源をつけた。おそるおそる選挙速報のページを開くと、危惧していた結果がまさに現実として飛び込んできて、この事の重大さと、僕の手中に収まるスマホの小ささがあまりにも不釣り合いだった。もちろん良い結果もいくつかは見られていたのだが、その光がか細く見えてしまうほどに分厚い暗雲があたり一体に立ち込めているように思えて仕方がなかった。生きている人間に優先順位をつけ、分断を煽るような発言をしていた候補者の名前のそばに、美しい花が次々と添えられていく。僕の隣の席に座っている人たちは、今この瞬間、何を考えているのだろう。僕と同じように絶望している人が、僕以外にもどうかいてほしい。他人の絶望を祈っている自分は、ひょっとすると悪魔なのかもしれない。それでも、同じ暗闇の中で手をつなげる人がいることだけが、この時は希望に感じられたのである。臆病な悪魔たちが輪になって踊っているところを頭の中で想像して、絶望の中でちいさな可笑しさが込み上げてくる。
23時から、友達と一緒にXのスペース「ウチらのサイゼ会」を開いた。毎週土曜に開いているスペースだが、きっと選挙結果に打ちのめされている人たちも多いだろうと思い、事前に曜日を変更していた。このスペースでは匿名のチャット欄をいつも設けているのだけれど、いつもは100人ほどの参加者が700名近くいて、孤独な悪魔たちが身を寄せ合うようにして、各々の想いをそこに綴ってくれていた。苦しさ、苦しさの中でも前を向こうとする健気さ、嬉しさ、嬉しさの中で立ち込める不安、そのどれもが真実だった。話は、これからどうしようかという話題へと移る。分断を生まないように目の前の人と話すこと、誰かと自分のあいだに身を置こうと努めること、言い古されたような、けれども一度も成功したことがないような結論へと行きつこうとしていた。
自分とは全く異なる立場にいるように見える人たちだって、最初はきっと同じ場所にいたのだろう。「なぜ自分の暮らしはままならないのか」、そんな問いを抱いて社会の激流に飲み込まれんとした瞬間に、えいとつかんだ藁が何だったのか。それによって流れ着いた先は大きく異なって見える。僕たちが流れ着いた川と、彼らが流れ着いた川のあいだにはすでに大きな山があって、二つの支流は平行線を辿りながら、勢いを増して進んでいく。いずれかが主流となって片方を飲み込む以外に、海に出るまでに交わることはないのではないかとさえ思える。であれば。僕たちがもう一度出会い直すためには、分岐点となったあの激流にさかのぼるしかないのかもしれない(山を越えようとする勇気が、僕にないだけなのかもしれないけど)。はじめの「なぜ自分の暮らしはままならないのか」という問いに立ち戻って、激流の中で辛抱強く、隣に浮かんでいる人と言葉をかわす。なぜ自分はこの藁を掴むことにしたのか、なぜあなたはその藁に手を伸ばそうとしているのか。自分がつかんだ藁が正しいなんて断言はできないけれど、せめてデマでできた偽物の藁にはすがってほしくないのだ。
僕はもう一度、あの分岐点に向かって、川の流れに逆らいながら足を進める。今まさに藁を掴もうとしている誰かのことを想像しながら。そして願わくば、山を隔てた向こう側で同じように激流へと逆行している誰かと、出会い直せることを夢見ながら。もっと願うのは、そもそも藁をもすがりたくなるようなこの激流がおさまることだけれど。
二手に分かれる手前の場所で、まだ見ぬあなたと出会いたい。まだどちらでもあって、まだどちらでもないあいだの場所で、まだ見ぬあなたと話してみたい。