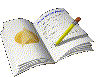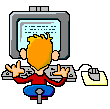愛という言葉は、わたしにはとても重く感じる。わたしはもともと広く面倒見の良い方ではないし、人と付き合うこと自体、それほど得意な方ではない。でも、これまでの人生を振り返ると、いつも何か大切なことを教えてくれたのは、多くの人が憧れる有名な人でも、美しい作品でもなく、目の前に現れる一人の“普通”の人の言葉や生活だった。そう考えると、結局わたしは人が好きなのだとは思う。
どんな場所でも「王様は裸だ」と言ってしまうわたしは、日本によく起こりがちな、長いものに巻かれた方が楽でよいとする状況に居心地の悪さを感じてきた。大人になると、立場や責任が生まれるとともに、そうも言っていられない状況になることはわかる。それでも、異なる意見や価値観があってこそ、わたしたちは自分では辿り着けない場所に行くことができる。どうにも分かり合えない人たちが、それでも互いのことを想像しようと努力し、何とか共有できる領域を見つけようとする過程こそが、人と人のあいだに社会が存在する意義ではないだろうか。そして、とても手間で時間のかかる、面倒なその過程にある営みこそが、愛なのだと思う。
タクシーの乗車拒否、入店拒否、イベントの参加拒否……さまざまな形で障害のある人が社会から拒絶されてきた場面を数多くともにしてきた。たとえば先日は、盲導犬を連れた友人と食事をしようと店に入ったら、衛生的に問題があると入店を拒否された。残念ながら珍しいことではない。わたしは合理的配慮(*)について説明したが、その日は上手くいかず、そんな扱いをされることには慣れた友人になだめられながら、次の店を探した。そのお店は靴を脱いで畳に上がるタイプの老舗の和食屋さんで、一見さらにハードルが高くも思われた。ダメもとで入ると、受付の女性は最初戸惑いながらも、玄関の土間のところに犬を寝かせ、犬が見える距離の席にわたしたちを案内することを提案してくれた。その時の食事は、いつもよりもとても美味しく感じた。
わたしは、これまで15年ほど障害のある人とともに展覧会やパフォーマンスなどの活動を続けてきた。たとえばアートや映画、ゲームなどを、これまでに構築された規範の外から見つめ直す活動をしてきた。それは“わたしたち”や“みんな”と言われるとき、そこにしばしば含まれない人たちが存在することを知ってしまったからだ。そして彼らの感覚がわたしたちの当たり前を塗り替える面白さを目の当たりにし、今まで活動を続けてこられた。正義感や倫理的責任感のような感情は、活動をするなかで後から付いてきたと言ってもいい。
そのなかで、自分の活動の一端を「アクセシビリティ」という概念で語ることができることに気づいた。アクセシビリティは、アクセスできる可能性の名詞形であり、これまでアクセスを阻まれていた人たちが、マジョリティと同等に物事にアクセスできるための手法の意味でも使われる。そのなかでもわたしが興味を持ってきたのは、多くの人たちが同じように物事にアクセスするための方法を考えることよりも、「アクセスする」ということに含まれる人間の身体や感覚の多様さを通して、体験そのものを見つめ直すということだ。
日本では、アクセシビリティが正解のあるチェックリストのように捉えられがちだ。ルールを守るのが好きで、そこから外れる人に厳しく、一度決めると変更するのが苦手な人が多い。でも、障害の状態は人によって違うし、それよりも重要なのは、一人ひとりが持っている欲望は異なるということだ。一人の人間と捉えれば当たり前のことが、生身の人間として出会う機会が限られていることで、想像されないままに型にはまったアクセシビリティが提供されていることも多い。
アクセシビリティについて調べるなかで出会った「アクセス・インティマシー」という概念がある。それは、アクセスを提供する側と受ける側という形で切り分けるのではなく、人と人のつながりの中でともに状況に寄り添う態度を求める考え方だ。作家であり当事者のミア・ミンガスによって書かれたエッセイの一部を紹介したい。