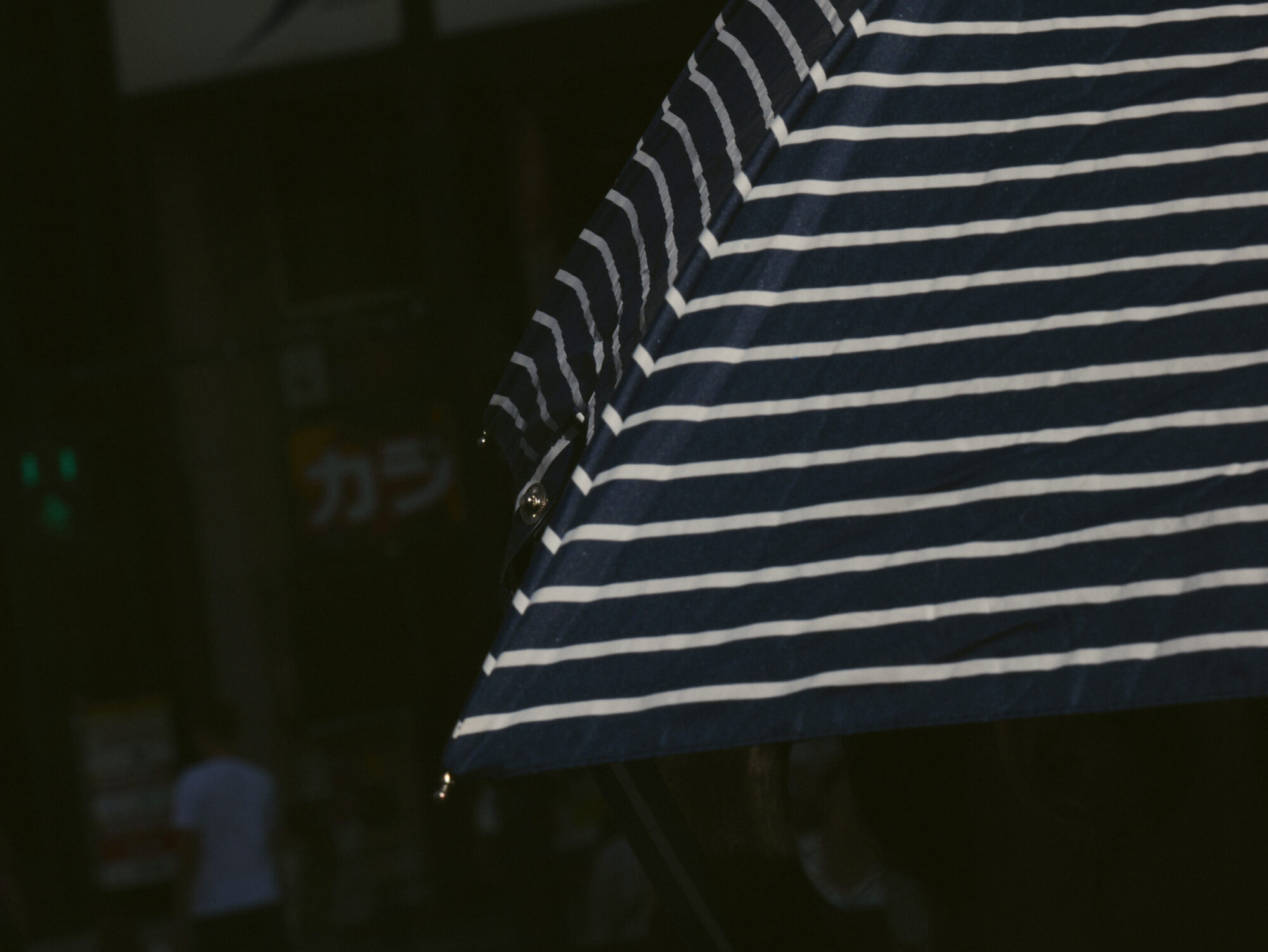連載
斎藤真理子さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」
日本から言葉を学びに韓国へ。移動しながら考え書くこと、生活と文学
2024/10/31
「生きていくの大変じゃないですか?」――そんな実感を出発点に、作家の鈴木みのりさんがこの社会で生活し、生き延びていくための方法を、さまざまな会いたい人に聞きに行く連載が始まります。
お金の話、暮らす場所の選択肢、コミュニティ形成の仕方……。安全を確保しながら生活を成り立たせるためにそれらは必要不可欠ですが、「一つひとつどう対処しながら暮らしているのか?」という具体的な話については、社会におけるマイノリティ性が重なっていくほど、ひらかれた場所で共有されることが少ない状況にあります。この連載では、鈴木みのりさんが自分とどこか近いところがあると感じる人たちに、「実際にどうやっていますか?」と率直に問いかけ、対話を行い、その内容を後日振り返って考察した文章をお届けします。「生きていくの大変じゃないですか?」と感じたことのある人のもとに、届きますように。
vol.1:能町みね子さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」
vol.2:チョーヒカルさんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」
vol.3:佐野亜裕美さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」
わたしは2024年2月末から4ヶ月、韓国・ソウルに住んでいた。ソウル大学の語学堂に通うためだった。語学堂とは、留学生が韓国語を学ぶための、大学が運営する語学学校だ(いわゆる民間の語学学校は「語学院」と呼ばれる)。
ファンから友人になった、シンガーソングライターのイ・ランのように、韓国の友達たちと韓国語で話したいというのが大きな理由のひとつ。それから、韓国の映画やK-POPなど音楽や文学について、もっと知りたいから。早くやればいいのに、ずっとぐずぐずしていた。
2022年の4月に発売された『早稲田文学』の特集「家族」号で、わたしは小説「ほころび」を執筆した。発表から1年以上経った2023年8月に会った編集者から、その作品について、日韓の小説翻訳で知られる斎藤真理子さんが褒めていた、という話を聞いた。それから斎藤さんが、ご自身が翻訳した小説の本を送ってくれた。斎藤さんが訳したもの以外にも、わたしの棚には元々韓国語で書かれた小説がいくつかあった。小説を書く際に、何度か読み返した本もあった。
それらを眺めているうちに、韓国に住んで韓国語を勉強するのがいいのではないか、と思うようになった。日本で生きていける自信がないというのはずっとあって、他の地域で暮らせるように、すでにある程度できる英語とは別に、何か別の言語を学ぶ機会を作りたいと考えていた。
1991年から韓国に留学していた斎藤真理子さんは『隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ』で、韓国語を学ぶようになったきっかけは? と尋ねられる経験について、〈さまざまなことがひと束になっていて、束の中から一本だけとりだすと別のストーリーになってしまう〉と書いていた。わたしもそうだと思った。

『隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ』(著:斎藤真理子、発行:創元社/2024年)
会って話しはじめた瞬間、斎藤さんは「おめでとうございます」と言った。わたしは、2025年1月から半年間ニューヨークに行くことになった。アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)のニューヨーク・フェローシップを文学部門で受賞し、本部のあるニューヨーク滞在の支援を受ける、そのことに対する斎藤さんからの「おめでとう」だった。
褒められ慣れていないわたしは恥ずかしくて、そんなことより今さっき斎藤さんが話していた、地元の新潟で訪れた墓地で見かけたという、流しの尼僧みたいな人についてもっと聞きたい、と返した。新潟に、韓国の文豪のお墓があるというお寺の存在を聞いた斎藤さんが、その場所を探しているときの話だった。
「すごい暑いのにちゃんと袈裟着てらして、それで、お墓参りに来る方に『読経しましょうか?』って声かけてるんですよ。何人かに断られたら、木の下の椅子に座って、ポーカーフェイスな感じでハンカチで、こう、汗を拭いて。尼僧の方は肌が綺麗っていうのはよく聞くけど、あんな暑かったのに、すごく血色のいい方で。私、そういう業態っていうか、仕事の仕方を初めて見たから……」
わたしは、尼の話から、高知県と徳島県の県境にある、山間の母方の実家のすぐそばに作られたお墓のことを考えた。自分の周りの同世代の人たちから、墓を閉じる/閉じないという話をたまに聞くようになってきた。当たり前だけど、自分より「キャリアがある」書き手の人たちも誰かの子どもで、生まれた地域、育った地域があって、それらをめぐるいろいろを今も持っていたり持てていなかったりする。
「もしも自分がフランス人の文化人類学者だったりしたらね、張りついて、“『あなたの話を伺いたい”』って言って、宮本常一のようなことをするだろうなーと思ったんです。ああいうの見ると、やっぱり日本だって一皮剥いたらすごく、その、昔と変わっていないというのか、いや、変わってないのか新しいのかすら見当がつかないようなところが変わってないところも見えてくるけど、機会がないと表出してこないじゃないですか? そういうことをすごく思った夏でした」
夏でした。夏がまとまった。
斎藤さんの魅力は、こういう着眼点と、それを話すときの語り口だった。言葉のチョイスはもちろん、字面が並ぶ以上に抑揚があって、スピードがある。10代の頃の学校の休み時間に、雑誌を広げて、好きな映画や俳優についておしゃべりしていたときみたい。
「3世代ぐらい上の、おばあちゃんおじいちゃんの世代に聞いたら、その頃の常識が全然、私たちの予想もつかないものがあるかもしれないですよねえ。あっという間になくなっちゃったものって、やっぱ語られないから。変化したものじゃなくて、ほんとになくなったものって語られない。日本は水面下でじわじわ変わりつづけていてすごい変わってて、変化が長いスパンで穏やかなの変化で、韓国みたいに、こう、目に見える形でドドドドドドドッて街が変わったりはしてないので」
「こういう曖昧な話をしてしまうとわからなくなる(笑)」「それがいちばんおもしろいんだけどね」
2月末から6月末まで4ヶ月のあいだソウルにいたとき、이태원(イテウォン:梨泰院)と同じ용산구(ヨンサンク:龍山区)にある해방촌(へバンチョン:解放村)で撮られた映画を、韓国で暮らす友達から教えてもらった。それは、ソウルの若い電子音楽家やその仲間たち(かれらを紹介してくれたのは、日韓のミュージシャンやDJを呼んで、ソウルや東京でイベントを開いている内畑美里さんだ)がSNSで紹介していた服屋を見に、へバンチョンに行った、という話をわたしがしていたときだった。남산(ナムサン:南山、正確には「ム」と「ン」のあいだの音だと思う)の南西に、高低差の激しいヘバンチョンはある。その、南と西にかけて広がる용산어린이정원(ヨンサン児童庭園:旧ヨンサン公園)や용산가족공원(ヨンサン家族公園)のある土地は、かつて在韓アメリカ軍のソウル・ヨンサン基地の跡地だった。
「今、あの映画がYouTubeに公開されてるじゃないですか? タイトルが『爆弾』……違う、なんだったっけ? 日本語の字幕もちゃんとついてるやつなんですよね。爆弾ってついてる映画……」
「違うの。あのね、私に言わせて! 本にも書いたの。この映画はね、タクシーに乗ってね、どこ行くかわかんない男の人の話なんだけど……」
「石原裕次郎が出てた映画みたいな感じがして」
「そう、影響を受けてるんですよ。1961年の映画で……ええとね……わかった! 『誤発弾』だ!」
「そう! 『誤発弾』! 『오발탄(オバルタン)』です!」
「そうそう、마자요(マジャヨ:韓国語で「そうです」「合ってます」)。『誤発弾』って、60年頃に本当に残ってた、ソウルのすごいバラック街でロケしてたんですよ。私DVD持ってる」
「そういう記録的な面もある映画がYouTubeに無料であるんですよね。日本の映画配信サイトだと、JAIHOでも観られるようだけど。韓国の映像資料の施設、映像資料院がいろんな古い韓国映画をけっこう公開してる」
「映画史上、大事なものは全部無料で観られるようにしてるんです」
「『オバルタン』が作られた当時は、確か日本の……え? あれってなんで日本語字幕がついてるんでしたっけ?」
「あれは、えーとね」
「日本の影響なんでしたっけ。あの時代はまだ」
「いや、日本では別に公開してないと思うけど、字幕つけたのは資料院じゃないのかな。違うのかな?」
「この映画を教えてくれた友達が理由を言ってた気がするんですよね……。1960年代あたりは……なんだっけ? 日本が……こういう曖昧な話をしてしまうとわからなくなる(笑)」
「それがいちばんおもしろいんだけどね」
そう言う斎藤さんのニヤリとした声色を聞いて、「話に花が咲く」という形容が良さそうな気がした。「そうそう」と「マジャヨ」、日本の言葉と韓国/朝鮮半島の言葉を混ぜるちゃんぽんのおしゃべりも。言葉だけでなく、思考とテーマの枝葉が広がる感じには快楽がある。どうやったらこのおしゃべりの快楽を文章にできるだろうかと考えると、歯がゆい。
知識が豊富で、冴えてるけど権威的なプレッシャーはない、楽しい人だと思う。ただし、「みんな対等」などと思うような迂闊さはなく、自分も他人も過小評価せず、非対称性にも配慮があって敬意も感じるし、気楽にお話しできるけどある程度の緊張感がある。可憐だけど凛々しくて、過剰な期待は控えようと思うけど、ちょっとだけ憧れる。
「今、割と韓国が記念館とかそういうもの作るの積極的だから、どさくさに紛れて、こんな人の文学館まであるのか? みたいなことがあるんです。いや、その“こんな人”は、私の感じてることなので、向こうから見たらきっと大事な事業なのかもしれないんですけど」
その話をしているうちに、わたしは去年の今ごろ、2023年9月に斎藤さんに教えてもらった、전태일(チョン テイル:全 泰壹)のことを思い出す。韓国で労働運動をしていた人で、1970年に22歳の若さで亡くなった。チョン・テイルは、ソウルの동대문시장(トンデムンシジャン:東大門市場)の縫製工場で働くことになった際、そこにいた女性労働者たちーーその多くが少女ーーが置かれる劣悪な労働環境の改善を、独学で労働法を学び、行政や雇用主に訴えてきたなかでの、抗議のための焼身自殺だったという。
わたしは、自分の一部であるマイノリティ性から、学内のインフラなどで学生生活がままならず、大学を中退したこと、仕事もうまく続けられなかったこと、ずっと非正規雇用であることも影響して、自分にできる仕事がなかなか見つからなかった。そうしたなかで文章を書く仕事をするようになった。これまでの、そして今の労働環境や、生活において不当な処遇を受けていると感じられるという個人的な動機を中心に、執筆のなかで、自身のマイノリティ性とも関わりのあるジェンダーやセクシュアリティの知識を使うこともあった。自分のため、自己肯定や自己防衛、否定的な言い方をすると自分が「できない」ことの言い訳のためでもあるのに、「社会のための発信」だとか、「性的マイノリティの人権」みたいな記号化された集合に貢献するものだと理解されることも多い。目の前の個人である「わたしのため」の話をしにくい、そうであると伝わらない、と徒労感を感じてきた。
その、個人として立っている労働の現場において、高等教育を受けて、言説構築能力が極めて高く、またトランスやノンバイナリー、ジェンダークィアの人々の言語表現や文化の醸成がされている英語圏にアクセスできる能力がある人に仕事がいきやすい、という不満を持っているのだと斎藤さんに話したところ、チョン・テイルの存在を教えてくれたのだった。
2019年には全泰壱記念館が、종로구(鍾路区:チョンノグ)の을지로(ウルチロ:乙支路)にできた。종로3가역(チョンノサムガヨック:鍾路3街駅)を北に、을지로3가역(ウルチロサムガヨック:乙支路3街駅)を南に、ちょうどあいだを走る청계천(チョンゲチョン:清渓川)沿いにあった記念館を、わたしは2023年の9月にはじめて訪れた。韓国を最初に訪れた2016年以来、何度も訪れていたのに、わたしはチョン・テイルのことを全然知らなかったし、トンデムンを訪れる多くの観光客もきっと知らない歴史だと思う。記念館で再現されている、非常にせまいかつての縫製の作業場を見ると、トンデムンの市場の安価な服や、ユニクロやH&Mといったファストファッションの服が、どういう人たちの、どういう労働環境下で成立しているのか、という現実と地続きだとわたしは思った。
そして、そのあたりは、斎藤さんがくれたファン・ジョンウンの小説集『ディディの傘』にも出てくる場所だった。
加湿器、モッケンディ、世運商街、ソウルの街のあいだで
『ディディの傘』は難解だと感じたけど、「d」と「何も言う必要がない」というふたつの短編を読むと、ファン・ジョンウンという作家がどうしてこういう小説を書こうとしたのかが少しだけ想像できた気がした。これこれこういう話だと簡単に説明できないなりに、わからないところがたくさんあるなりに。また、わたしの小説を好きだと言ってくれた斎藤さんが、なぜこの小説集をわたしに渡してくれたのかも、なんとなく想像できた気がした。

『ディディの傘』(著:ファン・ジョンウン、訳:斎藤真理子、発行:亜紀書房/2020年)
ソウルに住みはじめた3月の初めごろ、咳が止まらなくて、眠りにつきにくかったし、夜中に何度も目が覚めた。コロナに罹ったのかもしれないと思ったけど、高熱もなかったので、もしかしたら東京より乾燥した空気のせいかもしれないと、加湿器を求めて電気屋や家電も扱う大型スーパーを探した。ソウルで知り合った若い韓国の人たちが、おしゃれな暖房器具を持っていたので尋ねると、家電はネットで買うかコストコに行くと言っていた。
「その話、前に(Twitter/現Xのスペースで)してましたよね? おもしろかった、おもしろかった。今ってそうなんだなあって思いながら聞いてました。やっぱり空気が乾燥してるから、加湿器必須っていうのはみんなが言ってて」
「あと、のど飴もよく舐めるようになりました。こんなに飴を舐めたのは人生で初めてぐらい」
「老若男女みんながのど飴を持ってて、日本来るときも持ってるから、誰かがコンッて咳したらさ、“モッケンディ(목캔디:のど飴、목がのどで、캔디はキャンディ)、モッケンディ”って、すぐ出すのね。すごいのどに気を使ってるんじゃないですか。
加湿器に殺菌剤を入れるんだったかな? それで、加湿器の水で殺菌するための薬剤が有害で、それによって大勢人が亡くなった事故があって、裁判にもなって、“家の中のセウォル号事件”って言われた事件があったんですよ。
それでね、『フィフティ・ピープル』っていう小説があるんだけど、チョン・セランって人がその事件を作品に落とし込んでるんです。一千人ぐらいの人が亡くなったんじゃないじゃないかな? それはね、冬のあいだソウルは特に欠かせないからみんなが加湿器を使ってて、衛生状態に気を使う人がその薬剤を使って、割とずぼらな人はそれを使わなかったから助かったっていう」
わたしは、自分がよく手を洗い、特に他人の部屋や生活習慣が気になってしまう自分の潔癖さのことを思いながら聞いていた(整理整頓や片付けは苦手だけど)。
柴崎友香さんの小説『続きと始まり』のなかに、家具を動かしたときにその裏から埃が出てくるというエピソードがある。わたしが東京に、正確に言うと神奈川に出てきたのが18歳で、それから数回の引っ越し時に、母が手伝いに高知県から上京して来た。動かした家具の裏から埃が出てきたとき、それについて母から言われたことやその口調から、わたしは貶されたと感じた。思えば母は、子どもへの世話に多分自分の役割を見出していて、素朴に「子どものため」と言っただけなのかもしれず、その庇護に依拠したアイデンティティと、世話をされるこちら側が「コントロールされている」「見下されている」と感じてしまう部分とのあいだで軋轢が生まれ、歳を取るごとにそのささいな注意に自分が傷ついたのだと、わたしは気づいていった。ワンルームの10平米、15平米の部屋で、家具なんてそんなに動かさないじゃないか?
そして、母にされて嫌だと思っていたことを自分も誰かにしてしまっているんじゃないか、とここ数年のあいだで突きつけられるような経験が何度かあった。
「寒さ対策で気密対策がされたソウルの家で、ですもんね」
「寒いから二重窓だし、それをかっちり閉めて온돌(オンドル:朝鮮半島や、中国東北地方の一部に見られる暖房装置。かつてはかまどや炉から出される燃焼ガスを、床下に通して暖めていたが、現在は温水を通す床暖房が一般的)をちゃんと効くようにしてるので、悪い条件が重なっちゃったみたいなんですよね」
結局わたしは、5000ウォンで安かったから加湿器はダイソーで買って、咳は改善した。加湿器を探していて、ソウルには東京みたいに家電量販店が全然ないことに気づいた。
「私はオンラインで家電買うのって、実物を試せないからちょっと怖いけどなあ……(韓国の)みんなは勇敢だと思う。街の電気屋さんみたいなの、けっこうなくなっちゃったみたいだけど、いちばん大きいのだと、ソウルの真ん中に세운상가(セウンサンガ:世運商街)っていう電気街みたいなのがありましたよね。技術者が集まって、販売者も集まって、修理する・売るの両方がそこで済む、みたいな場所で、揃わないものはないっていう」
世運商街は1967年に鍾路区の장사동(チャンサドン:長沙洞)にできた。すぐ近くにウルチロもあって、コロナ禍以前、10年ほど前からジェントリフィケーション、街の浄化と再開発が進んでいるエリアにある。そのあたりにある古い雑居ビルに作業場や事務所を構えたり、ライブ会場で公演をしたり、遊びにきたりしている/してきた、わたしの周りの若いアーティストたち、服やアクセサリーのデザイナーたち、ミュージシャンたちからも、立ち退きや家賃高騰の不満を漏れ聞いていた。
「秋葉原の工具街みたいなところ、あるじゃないですか。(世運商街には)そういうむかーしながらの店が巨大なビルにワーッてビッシリ入ってて、一見さんだとどこに行っていいかわかんないけど、詳しい人に聞けばわかる。私もそういう店に行って、レコーダーとか買ったことがある。住んでた後に、仕事で取材に行ったときに録音機がなかったんだよ。そしたら友達から、종로5가(チョンノオガ:鍾路5街)に行けば安いから、そっちで買ったほうが絶対いいからデパートとかで買わないで、って言われてタクシーで乗りつけて。絶対値切らないと絶対損するんだけど、買い方わかんないから、それも友達が全部“こうやってこうやって”ってやってくれて。すごく小さいカセットテープを使う、大昔の録音機だった。安くてよく動きましたですね」
〈生きてる者の生活がぐちゃぐちゃなのはどうしようもないこと〉(ファン・ジョンウン「d」より)
多分、斎藤さんの言っていた「すごく小さいカセット」は、10cm×7cmの、昭和から平成のはじめごろまでよく聞かれていた音楽メディアとしてのカセットより、もっと小さいものだと思う。今、世運商街にあるインディペンデントなライブ会場で活動するような、若いソウルのミュージシャンたちが出している、再ブームになっているカセット(ダウンロードコード付き)に入った音源を、わたしもいくつか買ったことがある。
かれらの周囲にある、ウルチOBべアーという店は、その周辺にいる/いた金物屋や電気屋、工場労働者といった人たちが利用客だったが、ジェントリフィケーションの影響もあってか、若い世代や観光客もよく来る場所になった。
ウルチOBベアーは1980年に開業したビアホールで、ノガリ(スケソウダラの幼魚の干物)と生ビールをいっしょに楽しむというスタイルを初めて提案し、近隣に同業他店が開業していき、ウルチロにノガリ横丁が誕生していった。2018年からウルチOBベアーは家主から契約解除を申し出られ、不服とし、明け渡し訴訟までされて店側が敗訴するも、常連客や市民運動によって退去は阻止された。しかし、その借家の所有権の多くを、横丁に別のビアホールを営む大規模な飲み屋チェーン店の社長が買い取り、対話にも応じず、ウルチOBベアーは退去せざるを得なくなったという。これは、ソウルの家賃高騰と、経済格差の問題とも関わりが深い。
そういった経緯を知ってか調べもしなかったのか、2023年にある日本のファッション雑誌がソウルを特集した際に、ウルチOBベアーを退去に追い込んだ店を、「今ヒップな場所」としてだけ取り上げて、OBベアーが広めたはずのノガリ+生ビールというスタイルをその店の看板メニューとしていた。退去の抵抗運動に参加していた、ソウルのアンダーグラウンド音楽の関係者たちからの、自分たちも影響を受けたというその雑誌への不満を、わたしは何度か聞いたことがあった。
「『ディディの傘』を書いたファン・ジョンウンさんは、お父さんがスピーカーの技師さんで、実際そこでお父さんの商売を手伝ってたことがあるそうなんです。すごく世運商街に、こう、愛着あるんだと思いますけど、ものを作って、それを売って生きてきた人たちみたいな……それこそ、オンラインの買い物じゃなくて、こう、手を動かす商売というか」
『ディディの傘』に入っているふたつの短編小説のどちらにも世運商街が出てくる。それはわたしがこれまでも歩いてきた場所で、斎藤さんも歩いた場所だった。
わたしは、斎藤さんからその小説集をもらって、読んでいる途中に、そして読み終わったときにいたソウルの街を歩きながら、ウルチロ周辺のジェントリフィケーションについてと、ソウルの友達たちの声を思った。そこに自分の住む東京の再開発とホームレスの人たちの排除が重なる。そして、そんな状況を憂う自分と、関心のない人たちの差を思って、自分は正しいという優越感を少しだけ覚えながら、同時に、自分とは異なる考え方をする誰かが生きているということ自体を否定できないのではないか、とも考えた。
さっきの埃の話や、他人の家でも掃除したくなるようなときの自分の心の動きについて、思考が滑っていく。例えばカビやダニへのアレルギーや、そのほかいろんな理由が自分のなかにあって、しかしそれらを知っていても知らなくても、パターナリスティックな、「きれいにするという規範」によって干渉や介入をされる側からすると嫌になって当然のことだし、自覚しているとか親と似ていると言ったところで、相手は言い訳されていると感じるんじゃないだろうか。
もしかしたらそれは、受け流したり目をつむったり、柔軟に対応するのが難しい性格や性質に由来するものなのかもしれないし、マイノリティ性ゆえに後ろ指をさされないようにと優等生であろうとするからかもしれないし、いろんな理由が束になっているのだろうと思うのだけど、自分のなかで、家族や家というものや生活について、きちんとしなければいけない、掃除や自炊をするべき、といった規範で自分を縛っている面があるのだろうと思う。
「私は見えるところは綺麗にするけど、見えないところはすごい(汚い)のね。だから、5、6年住んだ家(うち)から引っ越すときにタンスを動かしたら裏から埃が、こう、厚切りベーコンのブロックくらい出ててきて、あんまりおもしろいからね、すごいと思って! これ厚切りベーコンブロックだったらすごいうまそうだなって思った」
埃が出てくるのって自分だけじゃないのか。規範意識が強いわたしは、他の人は仕事も生活もちゃんとしていて、自分はすごく怠惰で、先行き不安と言いながら何の見通しも立てられずにやってきたことに問題がある、と自責する傾向があるけどもう少し気楽に構えてもいいのかもしれない。ただし、コンセント周りの埃は火事になりやすいから、命のために気をつけたいけど。
「あとね、その前に西荻に住んでたときは、冷蔵庫の後ろに卵1個落としちゃったことがある。あれ取れないじゃないですか? それでそのまま5年経って引っ越すときに見たら、炭化して、ほんとに炭みたいになっちゃってて」
「たまにやりますよね。あと冷蔵庫の下とかもけっこう鬼門です(笑)。あそこの下に野菜のクズとかけっこう入ってたりする」
「炭になるんだなあと思って、無限の可能性を見たみたいな気持ちになりましたね。住み方って、好きでやってるかどうかってわかんないんですよね。たまたまこうなってるけど、それ選んでるんですか? って聞かれたら、別にそうじゃなくて、成り行きで、でも我慢できる住み方をしている人が多いと思うんですよ。計画通りに“こういう家で、物は全部自分が気に入って買ったもので、あらゆることに自分の意志が行き届いてる”っていう人は少なくて、みんなが割となんとなくこうなっちゃって、自分だから我慢できるけど、第三者から見たらこれ変だろうなみたいな生活習慣ってすごい多いし、ほとんどがそうな気がするんだけど」
わたしはファン・ジョンウンの「d」に書かれてあったいくつかの文章みたいだと思った。
〈生きてる者の生活がぐちゃぐちゃなのはどうしようもないことだろ、恥じゃない……〉
〈こんなふうにごちゃごちゃに混ざったまま……少しずつ壊れていくイ・スングンとコ・ギョンジャの人生についてdは考え、ddが生きていたら、そして彼らの共同の生が続いたとしたら、自分とddもついにはこんな光景にたどりついただろうかと考えてみた。残酷な光景だった。見るに耐えない、厭わしい眺めだった。しかしそれは同時に、何と美しいのか。ddと一緒に、人生にうんざりするということ。二人分のものたちに囲まれたまま、少しずつすり減って、消えていくこと。生命がなく、すり減ってなくなる物理的な形もないのだから、ddにはついに到来するはずのない光景だった〉
「人をあげられる家のハードルがなんか上がったんだよ、日本では。そんな気がする。私、80年代とか、若い友達同士でもしょっちゅう泊まり合ったりしてたけど、本当にいろんな部屋あったんですよね。
ある女の子が遊びに来てって言うから行ったら、食器棚もないし、食器もね、自分のごはん茶碗とカップしかない。そういう部屋もありました。それでね、自分はお茶もコーヒーも飲まないのに、“何にもないんだけどこのカップ使って”って言って、お湯は沸かせるから“クリープがあるんだけど、飲む?”って(笑)。すごいいい人だったんだよ。
今まで見たうちでいちばん謎ですけど、こうやっても生きられるんだなって。でも、普通に会社通ってんだよ、その人。だから、その、お洋服とかは押し入れの中にあって、とにかく床に何にも出てない。多分みんなが想像するようなソリッドな空間じゃなくて、畳でね、ミニマムな生活っていうよりは、生活自体に、多分家で生活することに興味がない感じでした。もう何も欲しくないんだって、あんまり。
とにかくね、そのうちがやっぱり筆頭ですけど、あらゆるうちが、いろんなうちが変なんだと思う。誰かと話してるときに“どこのうちのどの親もみんな変だ”って話になって。
ある方からあるとき、“自分の母親は流しの収納棚を開けるとぎっしり小豆が詰まってるんですよ。わけわかんないんですよ”って言われて(笑)。いっぱいあると安心するとか、そういうのがあるんじゃないですかね。で、多分お母さんは自分が変わってるってのはわかってるんだけど、子どもは“これが普通だ”と思って育つ。それで他所に行ってあれ? って疑問を持つんですよね。ライフスタイルっていうのは、なんとなく決められちゃうもので、そんなに選んだもんじゃないような気もするんですよね」
「ここ数年、長編を読むのがとても難しい」「小説読むってほんとはすごく大変なことなんですよね」
どこの家族もどこか変。みんなどこかおかしい。誤解はそこらじゅうに転がっていて、すべてが正されるわけではない。斎藤さんが好きだと言ってくれたわたしの小説「ほころび」はそういうことを書きたい、と思ったのだった。
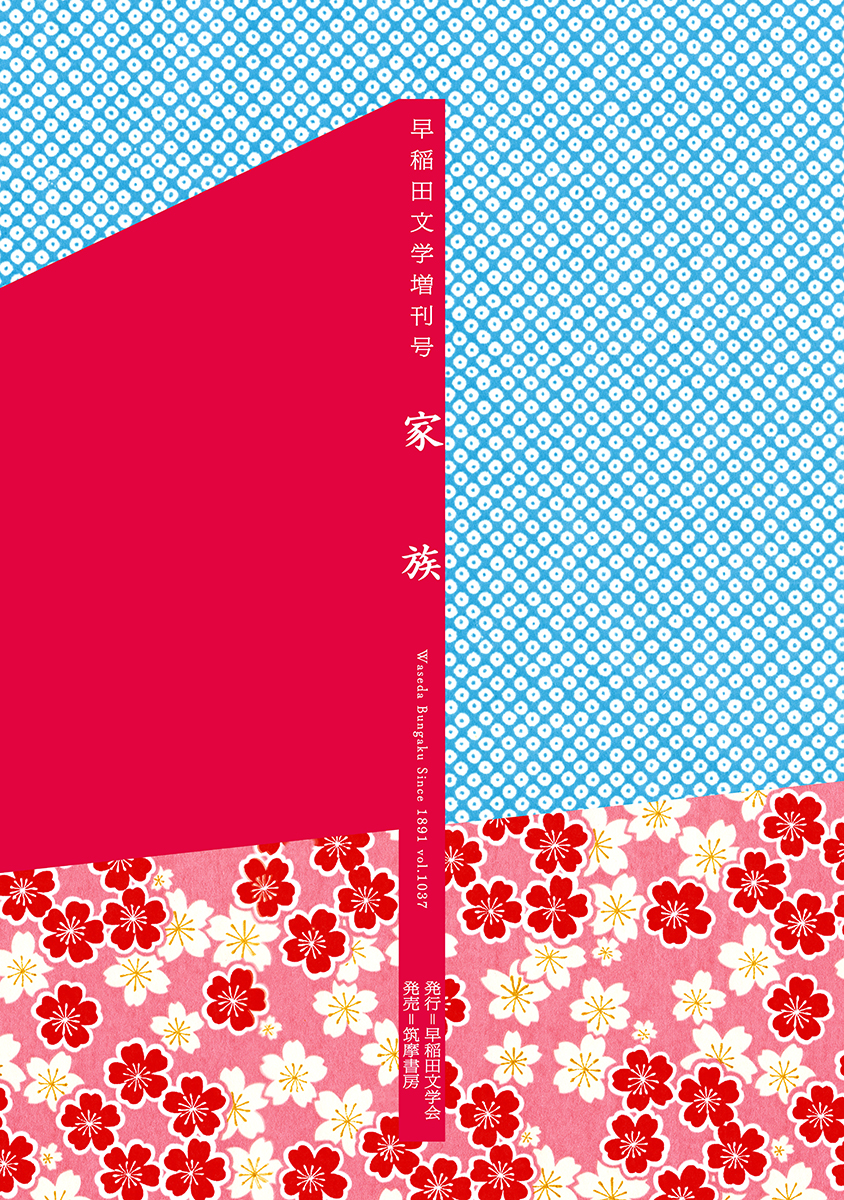
『早稲田文学増刊号 家族』。小説「ほころび」が収録されている
ここ数年、長編を読むのがとても難しい、しんどいと感じるようになった。おそらくSNSに慣れてしまって短文を読む程度の集中力になった面もあるけど、そのネット空間に広がっていく差別言説、とりわけトランスジェンダーに対するデマや曲解、フェイクニュースなどに、自分の生活する現実にも大きな影響があるから無視できないと、対抗したり、周囲の誰がそういう言説に影響を受けているかを知ったりして、疲弊しているのも大きかった。こうやって文章を書くメディア業界の労働において、誰との仕事ならば安全にできるのか? そう考えると、書く気力も読書をする気力も湧かなくなってくる。
学歴も職歴も乏しい自分が、必死に編集者に訴えて、真に受けてもらえない、うまく伝えられないという葛藤のなか書く場を作ってきたと自分では思っている。その一方で、すでに正規雇用で安定した、同じようなマイノリティの人たちの話は聞くし書く場所が得られている様子を見ると、その人たちの努力を否定したり腐したりするつもりはないけど、依頼する側や評価する側に、権威主義や能力主義への無自覚さがうかがえて、しかし能力を発揮する必要のある職業なのだとわかっているから、アンビバレントな感情がずっと拭えずにいる。
『ディディの傘』は短めの中編がふたつの本で、また自分の小説や批評的なエッセイを評価してくれている、読みたいと言ってくれる斎藤さんが薦めてくれたから、がんばって集中して読めたのだと思う。
「『ほころび』を書いていた頃は、ペク・スリンの短編集『惨憺たる光』と、あと、チョン・ヨンジュンの『宣陵散策』を読んでいたんですね」
「ああ、そっか! あのね、みのりさんの小説を読んでると何人かがね、こう、乱反射するんだよね。小さめに他の人が乱反射してたんだよね。ペク・スリンはわかる! なんか補助線が引かれた。わかったー! わかったー!」
「あとね、CUONが出している“韓国文学ショートショート”シリーズは、気楽に手に取りやすくて好きです。アメリカのブラックの作家の人とかの小説も読んでました」
「『フライデー・ブラック』(ナナ・クワメ・アジェイ=ブレイニヤー)とか?」
「そうですね。あと、トニ・モリスン、ジェームズ・ボールドウィン、タナハシ・コーツですね。長編が体力的にきつかったときに、かれらの短編を読んでたら、短編の依頼が来たのでちょうど良かったです。一日一編読めたらもう満足みたいなときでもあったので」
「他人が書いた物語、一人の人の脳内だけにあるものにね、頭から没入するって本当はすっごい体力いることで、誰かが書いたテキストを読むっていうのは(自分の頭のなかの)何かを入れ替えるぐらいしないと入れられないはずなので、小説読むってほんとはすごく大変なことなんですよね」
「『韓国文学の中心にあるもの』も、『本の栞にぶら下がる』もそうですけど、斎藤さんはたくさん読んでると思ったんですね。読んでるし、見てる。で、これとこれをこう繋いでいくみたいな手法じゃないですか」
「うん、なんか自分の勝手な法則(笑)」
「わたしも、me and youでのもうひとつの連載(「語る言葉のない声を響かせる」)、三回で止まってるんですけど、映像作品について書いてるその連載でも割とそういう、別の作品を自分のなかで繋ぐっていう手法を取ってます。たまたま同じっていうか、たぶん他の方もやるような手法だと思うんですけど……その類似性の話をしたいっていうよりかは、物理的な体力も落ちてて、目もなんかしょぼしょぼするし、自分がいろんな意味で読むの大変だなっていうなかで、もちろん年齢や経験の差があって読んできた量に違いがあるのは当然だと思う一方で、さっき斎藤さんが言ってたように、他人の考えとか物語を自分に入れるっていうときに、どうやってその時間を捻出しているのか気になりました」
「もう、もう入らないときは入れないし……四十代の頃はほとんど小説とか読んでない時期がありました。(言葉が)滑っちゃって入ってこないんですね。四十代はね、編集の仕事をしてたんですけど、仕事に関係がある実用書以外ほとんど活字が読めてなくて。仕事してうちに帰ってきて、子どものことやって何してってやってたら、文学どころじゃなかったですね。でもね、そんななかでもね、時々読んだ本があって、(W・G・)ゼーバルトとかそういう時期に読んでたんです。自分で探したんじゃなくて、道で偶然会った先輩が本持ってて、“おまえこれ好きだと思うよ”とか言って教えてくれたの。そういう、偶然出会った本を読んだらすごい良かったりするんですけども、でも、そんな毎月コツコツいろんなもの読むとか、もう全然そんなの関係ないときがありましたね」
「翻訳って多分、その文章を読解しながらやるわけですよね? だから、ある種の批評的な作業もしてるわけじゃないですか。この文章は、この物語は何を言おうとしてるか? とか考えることになる。そうするとただ“読む”とは違う筋肉使ってるんじゃないかと思ったんですね」
「“読み”が必要になりますよね。ただ翻訳はね、なんていうかな、翻訳の読み方、業務に切り替わるんですよ」
「生活してるとやっぱり読めなくなるというのはありますよね」
「生活してるとね、他人の物語とかどうでもよくなる(笑)。自分の現実が大変なのにさ、やっぱりちょっと自分に空白がないとね、他人の物語って入って来れないし、自分も入って行けないじゃないですか?」
「入って行く」という斎藤さんの言葉を聞いて、韓国語で들어오다と들어가다、「入る」と、「来る」と「行く」でできた二つの動詞のことを、わたしは思い浮かべた。行動の指向性に関する言葉。日本語でも、指向性が動詞に含まれている言葉があるのに、慣れてしまっていて、そんなふうに考えたことがなかった。
「書くにあたって、編集や評論の方から“量を読みなさい”って散々言われてきたんですね。いや、わかってるんです、わかってて読めないって話をしてるのに、それが伝わらないのがしんどいことが何度かありました。書く業界での差別の蔓延のせいで、自分がダイレクトに労働において危機的な状況にある、その改善をしようっていう話には焦点が当たらなくて、能力や努力の話にすぐなってしまうことにもどかしさを感じています」
そういう差別による危機的な状況下で、攻撃のターゲットになる懸念も引き受けるかどうかということまで考えながら、書き方を選んだり、どういう言葉なら、表現なら、自分の身を守りながら自分にとって切実な問題に切り込んでいけるか? という課題を、ほとんどの人たちと共有できないような感覚がわたしにはあった。ただの能力のなさ、努力の足りなさの言い訳にしているんじゃないか? ということも常に考えている。
「マイノリティである自分が何を書いても読んでもらえないんじゃないか、評価してもらえないんじゃないかという不安があるという相談を、ある評論や書評をしている友人・知人にしたとき、“あなたは読むのは楽しい? 書くのは楽しい?”みたいなことを言われた経験もあって」
「楽しいっていうときもあるんでしょうけどね」
「あるんです。でも、そういう話を今はしてない、楽しむための安全をどうやったら確保できるかっていう話をしてるんですけど、そこが通じなかった、かわされたと感じられる経験が重なると、この業界でやっていけるのかな? みたいな不安にけっこう苛まれます」
「そもそもゼロに戻したら、やっぱり読んだり書くのが楽しかったから、そういう仕事に接近していったんだと思うんですけど、それがどんどん奪われてしまう。そうなると、なおさらきついんですよね。元々好きだったかもしれないことがね」
「そう考えていると、この仕事がけっこう、ある程度恵まれた人……っていう言い方が適当かどうかわからないというか、苛烈な状況下でもハイパーな努力をされた人もいると思うんですけど、葛藤はやはり残るんですよね。もちろん仕事として、書く・読む・出す側の人っていうこともそうだし、読者もそうではないか? みたいなことはずっと考えてます」
「私も思うときがあります。もう本を読むどころじゃない人たちの存在っていうのを考えないと、本読んでる人たちだけのあいだで議論してても、本の未来は見えないんじゃないかなっていう気がするときがあるんですね。それをどう繋いだらいいかって誰もわかんないので、みんな苦労してると思うんだけど……」
スーツケースを「イミン カバン」と呼ぶ言葉もある、韓国の人と移動の関係。移動しながら考える
わたしがACCのフェローシップを受賞し、ニューヨークに滞在するのは、苛烈な状況から少しでも距離を取るため、日本語で生活する空間から離れ、日本語で発信されるネット空間からも距離を取るためでもある。また、なかなか稼ぐ余裕がないなかで、半年はひとまず暮らせるまとまったお金を手にするための応募だったし、自分と似たような被抑圧属性を持つ別の国の人たちが、特に、文化やコミュニティを作っているように見えるアメリカの、ニューヨークの人たちがどうしているのかに、生活を通してふれたいと思ったからだった。自分とは異なる厳しい状況下であっても、何かの参考になるんじゃないかと。
移動する自由、移動できる安全が担保された都市空間、安全が保たれなくても歩く必要のある人間の視点に、わたしは元々関心があった。
もともと、こういった助成を受けて書く、書くための取材をするといった発想を得たのは、ドイツ・ケルンで2018年に知ったベトナム系アメリカ人の作家モニク・トゥルンの存在を通してだった。モニクは、アメリカの複数の財団やレジデンシー、イタリア、フィンランド、日本などの文化助成団体やレジデンシーのサポートを受けて、8年かけて最新作『かくも甘き果実』を執筆したという。
ペク・スリンは、フランス・パリ、ドイツ・ベルリンを舞台にしたり、ソウルを訪れたオランダから来た人を登場させたりしている。わたしが訪れたパリでは、植民地化していたベトナムの料理屋でおいしい店がたくさんあるのを知っているし、ベルリンで中華系の麺屋に行くと、ロウ・イエの『天安門、恋人たち』のように本国から逃げてきた人たちがこうして地元に根づいたのだろうかと想像してきた。日本から、政治的な迫害を受けたり、ここにはいられないと別の国に移動せざるを得なかった人たちの声をもっと聞いてみたい。
「韓国の人って世界中に行くよ。スーツケースのことを移民カバン(이민 가방:イミン カバン)って呼ぶ言葉もあるんですね。韓国人で海外に親戚いない人いないんじゃないかって言い方もしますね。一時期、英語教育熱が韓国でヒートアップしたときは、インターナショナルスクールに入れればどこでもいいと、世界中の学校を探して、子どもにすっごい勉強させて、子どもとお母さんだけで行く、で、お父さんは韓国に残って仕送りをする、みたいなのがあったんです。だから、“インドネシアのインターに”“上海のインターに”って空いてる枠について情報がすごい飛び交ったようです。今は落ち着いたと思いますけど、今でもやる人はいると思います。とにかく“外に出て行くのはすごくいいことだから”っていう考え方って感じ」
わたしがソウルで3ヶ月滞在したコリビングスペース(ソウルの家賃高騰などの影響で、特に若年層が借りられる部屋がないという問題がある。そんななか、共同のキッチンやワークスペースなどがあり、プラベートスペースには寝室とトイレがある、という現代の共用住宅が増えているようだ)には20歳前後の若い人たちもいて、かれらはできたばかりのネット大学の一期生だった。同じ施設で個室を持った共同生活を送りながら、いっしょにオンラインの授業を受け、学年ごとに住む都市を変えるそうで、来年は日本に、その次はアメリカに行くと言っていた。
わたしはかれらを思い出し、移民カバンの話を聞いて、ペク・スリンの小説を想起していた。
「ペク・スリンの小説は、移動しながら考えてるっていう感じはすごく濃厚にありますよね。さっき、みのりさんの“自炊しないといけない”っていう規範の話があったじゃないですか。韓国人って“移動しないと人間じゃない”的な、“止まったら死ぬ”みたいに思ってるのかな、って思うときがあって。よく引っ越すっていうのもそうですし、機動性が高い感じがする。基本的にものすごい体力あってバイタリティある人たちなので、移動しながらでも、自炊するのが苦にならない、どこに行ってもの勉強する、習う、がんばる、それをデフォルトにしているっていうのはちょっと感じません? 日本の学生運動って、大学解体が最大のスローガンだった時期がありますけど、韓国はそれはないです。常に、学ぶことはいいことで、それが否定されたことは1度もないと思う。そのへんは本当にすごいと思います。とにかくみんなが、機会があればよりいい学びを手に入れたいのは当然というような感じなので。だから受験の競争は厳しいですけども、みんなでより良い目標に向かってがんばってるって感じが強くて、ライバル意識みたいなものはあるけど、ドラマではちょっと強調しすぎている気がする。見てると、親も子もすごいがんばるし、(自分には)絶対できないって思うけど」
わたしは、ソウルに行こうと考えていた時期の直前に、通いたいと思っていた大学の語学堂に受け入れを断られた。理由は伝えられないと言われたけどおそらく、申請の際に必要があって開示した自分のジェンダーに関する情報や書面上の履歴が原因だと思う。
その後に問い合わせたソウル大学は受け入れてくれたので、その語学堂に通った。夜のクラスで、しばらくして気づいたのが、インド、インドネシア、ケニア、ドイツ、フランスなどからきた大学院生や、国の行政機関所属で研修のために来た人や、ソウル大学に勤めるドイツ語の教員や、コロンビアから来た医師といった人たちばかりだった。わたしもお金を払って授業受けに来ているのに、ハングルが読め、ある程度独学で学んでから来て、比較的文法の近い日本語が第一言語だから、なぜかお金もらって授業を受けている人たちに、先生が端折っている箇所を何度も教えた。格差を感じつつ、おもしろい経験だった。
会って話した日、斎藤さんはいくつかの韓国語の本を持ってきてくれていた。K-POPの幕の内弁当とかつて菊地成孔さんが呼んだような、多彩なパッケージの音楽アルバムのような、さまざまな形態の「本」たちだった。移動しながら読んでねという、USB形式のオーディオブックもあった。
「発想してからね、プロダクトにするまでが短いんですよね。日本は会議ばっかりやってて、なかなかOKが出ないけど、韓国って、すごいおもしろいねってすぐやっちゃう。走りながら考える。だから失敗もするけど、割とみんなそうだと思う。作家もやっぱり作品にするの早いもん。で、これはね、文芸誌も出してる出版社から出たパク・ソルメの本なんですけど、ひとつ中編が入ってて、それを俳優さんが朗読した音源がUSBでついてるっていう。これを読んでるのがキム・セビョクっていう私大好きな俳優さん。『はちどり』って観ました? あの漢文の先生」
「はい、観ました。あの俳優いいですよね! タバコを吸うシーン、すごく好きです」
「すっごい声がいいから、朗読もめちゃくちゃいいの。これ全部で一万ウォンだから、安いんだよ。“通勤のときなどにお聞きください”って書いてあって。車で聞いたりするとかね。小説ね、耳で聞くといいんですよ」
「인터내……インターネット? ……ショノル??? 셔널が뭐예요?(ショノルがモエヨ?:ショノルが何ですか?)」
「ああ、んとね……これはインターナショナル(인터내셔널)」
「あ、インターナショナルか」
インターネットは인터넷。ハングルの母音のはㅐとㅔはほとんど同じ音(エ)だし、形も似ていて、覚えている単語も少ないわたしは、まだまだ瞬間的な判別が難しい。
「出退勤のとき、運転するとき、眠る前に気楽に聞いてください、って書いてるね」
「あ、ほんとだ。“운전할 때(ウンジョンハル ッテ:運転するとき)”」
「小説もね、持って歩くものみたいな感じ。私オーディオブックね、けっこう好きで。相性がいいこれとかね、単に本を読む五倍ぐらいの幸せ感があって、キム・セビョクの朗読はほんとに幸せ感あった。ずーっと聞いてました」
「アメリカとかだと今もうオーディオブックがすごく多いって聞きますよね。わたしもオーディオブックに切り替えた方が本をもっと読めるんじゃないかってよく考えます。ラジオでニュース解説番組を聞くとき、研究者とか、その道の専門家の解説を聞いてから、その人の専門書や記事を読んだらもっとスッと入ってくるみたいなことがあります」
「声ってすごいなって思うんですよね。だから小説を、すごく静的なものというより、持ち歩いて」
「移動しながら聞く、読む」
「これからみのりさんは移動して書く生活をするわけですよね? 私はそれをすごく楽しみしてます。もう今日はそれだけを言いにきたんですけど。なんかこう、“あいだ”をね、正解がありそうなところの“あいだ”を歩き続けるという、そういうことになると思うので……と、まとめようとしてるんです(笑)」
鈴木みのり
1982年高知県生まれ。ジェンダーやセクシュアリティの視点、フェミニズム、クィア理論への関心から小説、映画、芸術について執筆。“早稲田文学増刊号「家族」” (筑摩書房)、“すばる”2023年8月号で小説を発表。第22回“AAF戯曲賞” (愛知県芸術劇場 主催)審査員を担当。近刊に“‘テレビは見ない’というけれど” (共著/青弓社)、和田彩花と特集の編集を担当したフェミニズムマガジン“エトセトラ Vol.8 (特集‘アイドル、労働、リップ’)”。アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)2024年度ニューヨーク・フェローシップ(文学部門)を受賞し、2025年1月よりアメリカ・ニューヨークに滞在予定。
斎藤真理子
韓国語翻訳者。主な訳書にチョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』、ファン・ジョンウン『ディディの傘』、パク・ソルメ『未来散歩練習』、李箱『翼 李箱作品集』、ハン・ガン『別れを告げない』など。2015年、パク・ミンギュ『カステラ』で第一回日本翻訳大賞受賞。著書に『韓国文学の中心にあるもの』『本の栞にぶら下がる』『隣の国の人々と出会う――韓国語と日本とのあいだ』など。
撮影・増永彩子
プロフィール
『エトセトラ VOL.8 特集:アイドル、労働、リップ 鈴木みのり・和田彩花 特集編集』
発行:エトセトラブックス
価格:1,300円(税別)
発売:2022年11月30日(水)
書籍情報
me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら
*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。
あわせて読みたい
連載
チョーヒカルさんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」
2019年からNYに移住。日本に生まれ育ち、国籍は中国というマイノリティ性から考える
2024/02/08
2024/02/08
連載
能町みね子さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」
社会や政治の話は大事。けれど、トランスである人の生活はそれだけでは語り得ない
2023/11/02
2023/11/02
連載
佐野亜裕美さんと話したい。「生きていくの大変じゃないですか?」
『大豆田とわ子』『エルピス』などを手掛けるテレビプロデューサーと、生活について話す
2024/06/15
2024/06/15
創作・論考
Miu Miu「女性たちの物語」21『Shangri-La』;欲望と祝福のブルックリン
連載:語る言葉のない声を響かせる/鈴木みのり
2022/12/09
2022/12/09
創作・論考
『セイント・フランシス』と『シャープ・オブジェクツ』;ないものとされる血を描く
連載:語る言葉のない声を響かせる/鈴木みのり
2023/01/31
2023/01/31
創作・論考
『キャンディマン』の都市空間;「いつ誰に攻撃されるかわからない」不安をどこで誰が抱いてきたか?
連載:語る言葉のない声を響かせる/鈴木みのり
2023/03/20
2023/03/20
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。