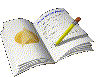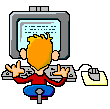私は人々の生活の中に入り、一緒に踊り、太鼓を叩き、料理を作り、食べ、漬物を漬け、泣き、林檎の花を間引き、薪を集めて運び、ココナツの実を削り、植物を探し、山菜を採り、キノコを摘み、ワカメを採り、タコを釣り、捌き、岩から小さな貝を取り、煮て、酒を飲み、語り、たくさん語り、聞く。ずっと聞く。彼らの、そして彼女たちの話を聞く。何度も、何十回も、何百回も。私は一瞬、彼女になるまで、彼女の人生を生きるまで聞く。「まで」と書いたけれど、その後も物語は続く。
私は男性よりも、女性の話を聞くのが得意で、好きだ。男性の話を何年も聞いてきた後、ある時、彼女たちの声をさらに深く聞こうと、心の中で大きな切り替えがあった。それは偶然にも、私が母親になった時期と重なっていた。憧れていた研究者の世界に飛び込むと決めていた頃、モデルとなる女性研究者がいたが、どうしても男性中心の世界だったことに、諦めの悪い私は気づかずにはいられなかった。ほとんどの民族誌は男性によって書かれ、知らず知らずのうちに、フィールドワークでも男性中心の民俗芸能や男性の話ばかりを集めていた。数少ない女性研究者も、テーマや対象が女性であっても、その声を学問の「男の声」に近づけようとし、男性の理解を求めているように感じられた。論理的な世界と、フィールドワークで出会う世界。西洋的な思考と解釈。私が育った村と、そこで見た一人、一人の人生の物語とのズレに、絶望を味わった。
そんな中、私が憧れていたのは『ニサ:カラハリの女の物語』(マージョリー・ショスタック著)。原題には「物語」ではなく「言葉」とある。カラハリに住むニサという女性の言葉を、女性人類学者のショスタックがほぼ編集せずに、何ページにもわたってそのまま載せている。彼女の声は、遠慮なく、ありのままに、全世界に届く。書かれた言葉なのに、聞こえ、見える。彼女の目を通して見た世界は、透明で、魂まで共鳴するように伝わってくる。
この感覚を忘れられず、大学院の受験で「影響を受けた本は?」と聞かれたとき、私は「ニサ」と答えた。男性ばかりの教授たち(当時の著名な人類学者も含む)から涼しい風が入ったように「お」と声が漏れた。その声は今でも覚えている。どんな驚きが込められていたのかはわからないが、私はショスタックのように、一人の女性の声を書き留めたいと思った。ショスタックのように、現地の女性と親密な関係を築き、彼女がすべてを語り、魂を裏返すまで、私と彼女が溶け合うまで。
そして、本当にその夢が叶った。青森で、バヌアツで、私は彼女たちと深く語り合い、互いに自分が誰かわからなくなるまで過去を語った。ニサのように、愛の話、恋人の話をよくした。私はどこかで、夢や映画のような恋の話は存在しないと諦めていたが、彼女たちの一番印象深い話は、いつも恋の話だった。林檎畑と愛、深い、青い太平洋と愛、骨と愛。彼女たちが愛した人は死別しても、彼女たちの中でなお生き続け、光として、風として、夢として存在する。
彼が愛した髪の毛を棺に入れ、夜遅く寂しく道を歩き、大好きな人が目の前にいても彼に声を掛けることができず通り過ぎていくだけ。彼女たちはそんな人生を歩みながらも、大きな愛を生きたことをほとんど誰も知らない。愛は頼りにならないかもしれないが、毎日彼女たちの目を輝かせ、生かし続け、「思い出に満足」と言わせる。満足という言葉には「足」が入っているけれど、愛は頼りがないが彼女たちは決して愛を足で踏むことはなかった。