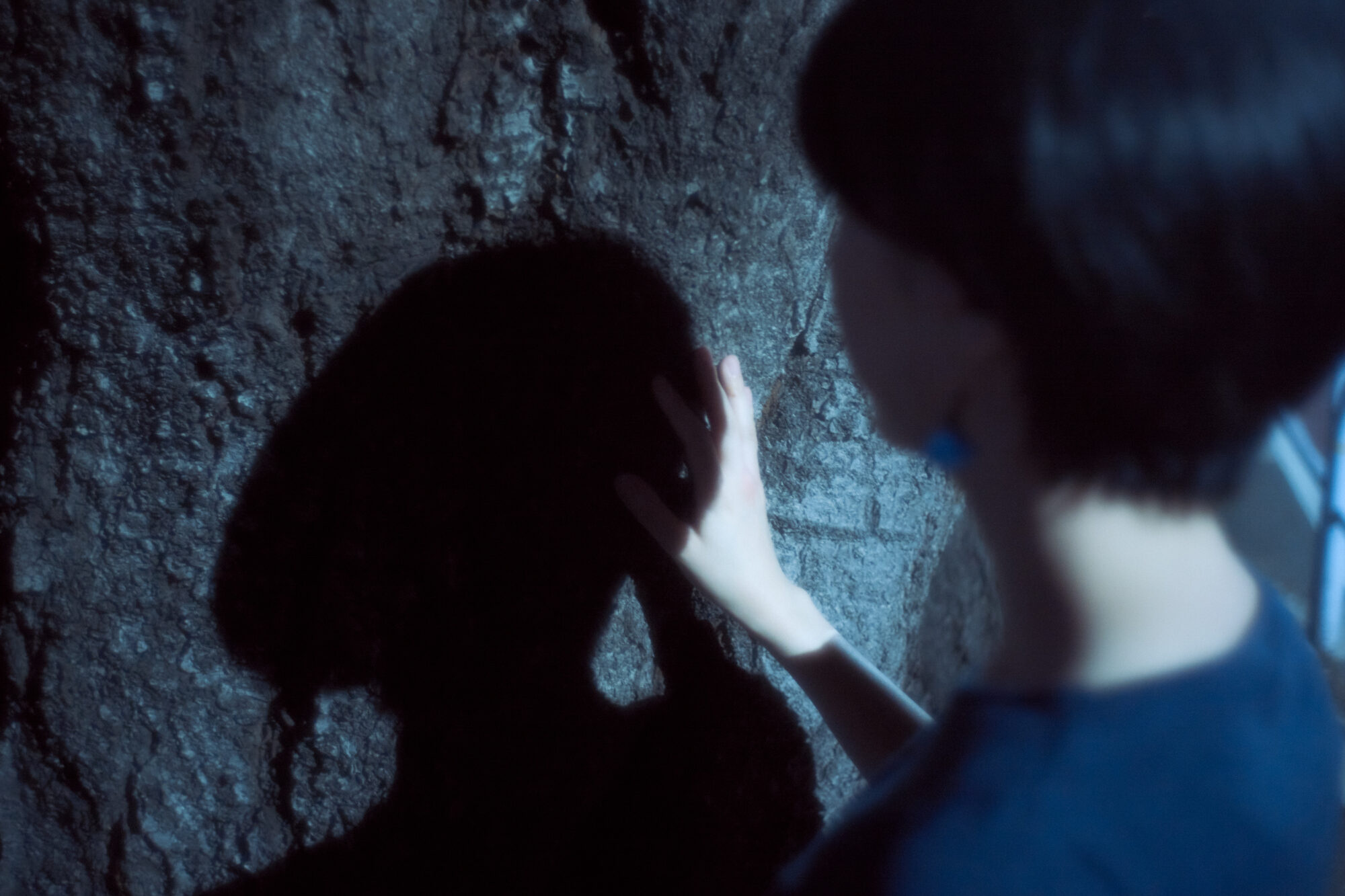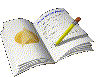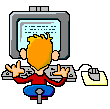永井玲衣が考える、愛。あなたが暴力を振るわれていいはずがない。忘れられていいはずがない
戦争、暴力、同じことと違うこと。「全部一緒だったら生きられない」
2025/7/30
人々と考えあう場をひらくために、学校から企業、路上まで、さまざまな場所に足を運び、対話をおこない続けている永井玲衣さん。スピード感のあるコミュニケーションや、わかりやすい言葉が求められる社会のなかで、相手の話をさえぎらずに待つことをルールに取り入れ、「よく聞くこと」に重きを置く永井さんのてつがく対話は、一人ひとりのなかに本来あるはずの複雑さや奥行きに光を当て、その人の持っている豊かな力の断片を前景化させるような試みでもあります。
写真家の八木咲さんとともにおこなっている「せんそうってプロジェクト」や、戦争体験者の聞き取り調査。歴史のなかで喪失や搾取、踏みにじられることを経験してきた人たちの声や証言に耳を傾ける取り組みを通して、「暴力ではない仕方」で一緒に生きていくことを考え続けているひとりです。
お互いの違いや、あまりにも折り合えないことに混乱して、ときには最悪だと絶望しそうになりながらも、それでもわたしたちは、すでに一緒に生きてしまっている。常にままならず、たよりないこの状況のなかで、「じゃあどうしたら一緒にいることを諦めずにいられるのか?」を考え続けている永井さんと、他者を愛することや、戦争を愛という視点で考えることなどについて、ともに頭を悩ませながらお話ししました。
─永井さんはもともと、大学の哲学研究科で「他者論」を学んでいたんですよね。「他者がわからない」ところから哲学に向かったということですが、それまでの永井さんは、他者に対してどんな難しさを抱えていたのでしょうか。
永井:哲学をやっていると、「子どもの頃から考えるのが好きだったんですね」と言われるんですけど、まったくそうではなくて。ずっとイライラ、ぐずぐずしている子どもだったんですよね。 その苛立ちをうまく言葉にできないから、誰かとわかち持つこともできないし、一緒にいる人たちの言ってることもよくわからない。おずおずと語り出してみても、「どっちでもいいじゃん/どっちでもいいんじゃない」っていうような返事をもらうことが多かったんです。
そのときはまさか、自分が抱えているものが「問い」だということにさえ気づきませんでした。当時の自分は、他者との関わりというのはある種、暴力的なものでしかないというような印象を持っていました。「どうしてわたしたちはこんなにも互いの声を聞き合えないのだろうか?」っていう問いと、「どうしてわたしたちは集まると、こんなにもハチャメチャになってしまうのか?」っていう二つの大きな問いが、たぶんずっとまとわりついている。 それが自分を対話に向かわせているんだろうなっていうのが、思い返すと見えてくる問いなんです。
永井:一対一でゆっくり話すならまだわかるのですが、3人以上になると急にめちゃくちゃになってしまう。そのはじまりはもしかしたら家族かもしれないし、教室かもしれないし、部活かもしれないし、企業かもしれないし、何かしらの組織かもしれない。大きく言えば、社会かもしれない。 だから、「わたしとあなた」という関係性もそうだけれども、「わたしたち」という共同体のなかで、互いの声をどうやったら聞けるのかっていうのはずっと考えているし、いまも探しています。
─今日話をうかがっているわたしたちも、学校という組織にそれぞれの難しさを感じていた時期がありました。永井さんがどんな10代の頃を過ごしていたのか、無理のない範囲でお聞きしたいです。
永井:ハプニングは多かったですね。(笑)。
─それも気になりますね……。
永井:自分の置かれた場所ではあまりうまくやってこれませんでした。視野も狭かったので、身近な集団に対する感情が、世界への憎しみにつながっていってしまうというか。本当にどうしたらいいかよくわからなくて、学校帰りに植え込みにずっと座っているような子どもだったんです。渋谷に東横のれん街ってあったんですよ。再開発でいまは移転してしまっているんですけど、そこに「あなたのために祈らせてください」っていう人がよく通るっていう噂があって。で、「なんかその人に祈ってほしいな」と思って、植え込みに座ってその人のことを永遠に待っていました。
自分の人生を自分でどうしていいかわからないし、自分で自分のことを祈れないから、誰かに祈ってもらいたかった。めちゃくちゃじゃないですか。他者との関係性の取り結び方として。でも、何時間もずっと座って待っていたんです。いま考えると不器用ですけど。
me and you 竹中:クラスや学校では、当時どんなことを感じていましたか?
永井:どうだったんですかね。あんまり覚えてなくて。学校では、なんとかやっていた気がしますけどね。
ちょっと話が飛び飛びになるんですけど……。このあいだ神戸で、てつがく対話をしたんです。そのときに、インドの人と働いているという話をしてくれた人がいて。その人は最初、相手のことをわからないと思ったそうなのですが、わかるとかわからないとか、そういうことでジャッジすることをやめたらすごく楽になったと話していました。「わたしたちは、わかるとかわからないとか以外の仕方で、一緒にいられるんだ」と言ったんですね。それは、何十年越しにもらえた言葉のような気がしました。当時はひとりぼっちな気がしていたけれど、一方で、わかる/わからないをこえて一緒にいてくれた誰かも、いたかもしれないといまなら思います。
対話をすると、その人に暴力をふるえなくなる
─『水中の哲学者たち』だったと思うんですけど、「他者を愛しながら他者をめんどくさがる」「どうしてあなたを全身全霊で愛せないんだろう」と書かれていました。自分の周りには、人間が好きだと言っている人と、人間が嫌いだと言っている人がいます。両方が共存することもあれば、割合が変化するものでもあると思いつつ、「他者を愛したい」と永井さんが何度か書かれているのが印象に残りました。永井さんは人間が、好き……?
永井:好きになりたい……? ここも錯綜しているんですけどね。『水中の哲学者たち』を書いたときはまだ学生で、いまほどいろいろな場所に足を運べていなかったので、考えもかなり変わってはいるものの、変わっていないところもあって。わたしが対話を10数年やっていて思うのは、10代の頃は自分の考えていることをうまく話したり聞いたりできないし、周りからも変だと言われて変なのかなと思っていたけれど、場をひらけばみんな変なんですよね。めちゃくちゃ変。それで、いや、ふざけんなよ……と思って。そんな変でおもしろいところ、隠してんじゃないよ、悔しいなあ、みたいな。でも考えてみると、隠さなくちゃいけない構造の問題があるんですよね。そこはここ数年で実感していることです。
だからわたしの周りの人たちだって、絶対変だったし、おもしろかったし、きっとすごく素敵だった。でもそれを受け取れる場を自分はつくれなかったし、つくり得るとも思っていませんでした。対話をすると、その人に暴力をふるえなくなるというのがわたしの手触りです。それはもしかしたら、他者を愛したいみたいなことなのかもしれない。愛したいというか、愛さざるを得なくなるみたいなことが、対話をすると起こる。だから対話したいみたいな循環になってくるし、その循環に自ら入っていきたい。そうやってわたしたちは一緒にいておきたい、みたいな感じですかね。
─普段の社会のなかでは、個人が持っているでこぼこなところをある程度、押さえ込むことがよしとされたりもします。それは他者にとって理解しやすい、飲み込みやすい状態であるとも言えるような気がするのですが、てつがく対話の場では、個々の手触りが外側に滲み出してくる驚きがあると感じます。対話の場をひらくと暴力を振るえなくなるという感覚について、詳しく聞きたいです。
永井:不思議ですよね。 なんなんでしょう。わたしのすごく好きな言葉に、ある企業で対話をしたときに社員さんが言った「部長って人間だったんだ」というものがあります。笑ってしまうし、悲しくもなる言葉で。すごい社会だと思います。記号みたいなものにされていたものが、無限の奥行きを持ったひとつの命だったということが、そこでわかることのおののきが、たぶん暴力を振るえなくさせるということなんですかね。なんかとてつもなく大事なものが出現しちゃう、みたいな。それを到底壊せないみたいな感覚でしょうか。
─昨日、me and youでてつがく対話をご一緒しましたが、永井さんは自己紹介で「学校や企業、そして路上でてつがく対話をひらいている」とお話しをされていました。世の中では、名の知られている人や、人数の多い集団など、数の大きさが重視され、数字のついていないものや、「いますぐに役に立たないもの」は力がないものだと軽んじられかねない状況でもあると思います。永井さんが路上で生活する人たちや生活困窮者の人たちのもとに足を運び、受け取っている実感についてうかがいたいです。
永井:これはよく話すことではあるのですが、どうしてもいま話したくなっちゃったので……。『水中』を書いたときは、「哲学は誰のものか?」という問いを立て、それは当然みんなのものだという思いで書いていました。ただ、学生だったのもあって、先生についていったり、限られた研究費のなかで動いたり、そういう枠組みのなかにいたんですよね。
で、本を出して、あるときに「いや、みんなって誰?」って気づいて、すっごく恥ずかしくなりました。本当にね、顔から火が出るほど恥ずかしかった。 歴史のなかで女性が置かれてきた環境もそうですし。いや、どんだけ無邪気な問いだったんだと思って。「哲学は誰のものでなくさせられてきたのか?」って問わなきゃいけなかったのに、「哲学は誰のものか、みんなのものだ」なんて、そんな簡単なことじゃなかったと思って。自分がひらいてきた対話の場に、それまで車椅子の人が来たかっていうと、来てなかった。赤ちゃんを抱っこしている人が来たか? 来てない。それで自ら出向かなきゃいけないと思ったのがひとつ。
もうひとつは、コロナ禍に入ったぐらいだったと思うのですが、人前に招かれる機会も増えて、資本主義の限界について話したり、考えたりする機会が増えたんですよね。周りからも聞くし、自分もそういう話をしていたんですけど、じゃあ資本主義で一番割を食わされている人に出会ってきたかというと、自分は出会ってこれていなかった。だからその人たちの現場を見なきゃいけないと思って、困窮者支援のボランティアなどで勉強させてもらうこともありました。
永井:生活相談の支援にも入らせてもらったのですが、そこでは相手のお名前と年齢を聞くんですよね。そこで同い年の人に会ったり。ある若い人は、服の左側だけがうっすらと汚れていました。左側を下にして、路上や公園で寝ているんだな、とわかりました。当たり前なんだけど、本で読んだことと全然違います。特に哲学という分野は概念で遊べてしまうので、それだけは本当に恐ろしいことだと思っていて。そういうことを思い知らせてもらい続けた数年で、だから自分からいろいろな現場に行きたいし、行けばまた違う現場につながっていきます。いまはいろんなところをひたすらうろうろしたい。
しかもそういった人たちの声は、あまりにも聞き取られていない。「大変だよね、考えている余裕なんてないよね」と思われている。でも死ぬほど考えている。めちゃくちゃ問いがあるし、めちゃくちゃむかついているし、めちゃくちゃたくましいし、めちゃくちゃおもしろいことを考えている。それが聞かれていないことがまた怖くなって、より聞きたくなります。
me and you竹中:そういう構造の問題があるなかでは、「自分の言葉なんて」と思ってしまうこともときにはあるのではないかと思います。たとえば抑圧を受けてきた人や、話を聞いてもらえない経験をたくさんしてきた人。そういった人が対話の場に参加したときに、きっとすぐに話せるわけではないのではないかと思うのですが、どういうふうに人々は話しはじめることができるのか、できるようになっていくのか、というのを永井さんの経験から聞いてみたいです。
永井:そうですよね。対話をひらくときはなんかね、頭を下げるつもりでやるんですよね。「みんなやるぜ」という感じよりは、「お願いだから聞かせてください」って言うんですよ。聞かせてくださいって、お願いしています。
だからまあ、待つしかないですね。「なんと惜しみなく教えてくれてありがとうございます」って思いますし、言いますね。対話って、一回きりのものじゃない。「対話はいつ終わるのか」という問いは実はすごく難しい問いで。時間がくれば対話は終わるけど、あの対話の体験っていうものはずっと引き続くので。次の月に会った子どもがいきなり喋り出すこともあるし、3年喋らなかったおじさんが3年目で急に喋り出すとか、そういう感じなんですよね。そしてその過程で、人は変わっていきます。
人ってでも、そうですよね。一回ではやっぱり、魔法じゃないからすぐ変わらない。でもそう思っていると、1時間ぐらいの対話で勇気を出して話してくれることもあるから、本当に油断ならないです。こっちが決められない。予想をこえてくるというのが、対話のやっぱり面白いところ。シェルターなどに行って感じるのは、強い暴力を受けた人のなかには、もうぴくりとも動けず、ひたすら「わからないです」と言い続ける人もいます。それでも、またこの場を続けていくことができれば、と思うんです。
好きじゃないけど、愛してるって思う。対話をすると、そういうことが起こるんです
─「愛も生活も、たよりないから」という特集についても、一緒にお話しできたらうれしいと思っています。そもそも愛という言葉の抽象度が高いので、人によって思い浮かべるものが違いますよね。定義をひとつに決める必要もないし、ばらばらのままでよいと感じているのですが、この特集では自分にとっての愛や、そのたよりなさについて具体的に考えはじめることができたらと思っていて。質問が大きくなってしまうのですが……いま永井さんは愛と聞いてどんなことを考えますか?
永井:雑談からはじめるのですが、10代のときは、愛とかふざけんなよという思いがあったんですよ。所属していた哲学科は自分たちで研究会をつくったりするのですが、「ラブ研」をつくった人に対抗して、「デス(death)研」をつくったぐらい……(笑)。
─いい話ですね……。
永井:(ヴラジミール・)ジャンケレヴィッチの『死とはなにか』について考える、みたいな研究会で。そのときは、愛も暴力じゃないか? みたいに簡単に考えていたんですよね。でもそのあと対話の場をひらいて愛というものを捉え直していったときに、やっぱり「この人に暴力を振るいたくない」という感覚に近いと感じました。対話をすることは、対話で一緒になった人をある種、愛することでもあるんですよね。
相手を好きになるわけじゃないんですよ。不思議と。好きじゃないけど、愛してるって思う。ふざけんなよ、と思いながら、同時にすごく愛することができる。対話をすると、そういうことが起こるんです。
─永井さんのなかにはあらためて、暴力というものが大きくあるんですね。
永井:大きい。めちゃくちゃ大きいですね。本当に、暴力に抗するものとして対話をするというのが、たぶん自分の一貫した姿勢だと思います。
─永井さんの場合は、「ここにいるあなたに暴力を振るいたくない」という気持ちを愛と言えるように、愛という言葉を言い換えたときに、その人の大事な核のようなものが出るところが興味深いと感じました。自分が人間や世界に対して向けているひとつの強い感情が、言葉として現れるというか。願いとも近いかもしれないのですが。
昨日のme and you clubでは、「愛も生活も、たよりないから」というテーマで参加者がそれぞれに問いを立て、「見返りをまったく求めない愛ってあるのかな?」という問いが選ばれ、みんなで話すことになりましたよね。その対話を経て、永井さんが考えたことはありましたか?
永井:昨日の会で、わたしは死んだ人への愛の話をしました。「見返り」というものが「応答」であるならば、死んじゃった人からは応答がないわけですよね。でも、全然愛しているなぁ、と思いました。本当にあの問いのおかげで、結構自信を持ってそう思ったし、そこから派生して、まだ出会っていない人や、出会ったことのない人に対しても愛を持っているとも思えた。
昨日も、沖縄のひめゆり学徒隊に関する聞き取り調査をおこなったときの話をしましたが、その人たちの声を聞くたびに、「これは絶対になかったことにしたくない、忘れたくない」と思います。それはあったかい気持ちなどではなくて、もう、かき乱されるように、です。生きている人にも、死んでいいはずがない、暴力を振るわれていいはずがないと思いますが、死んだ人にも、忘れられていいはずがないだろう、と思う。わたしも愛についてそこまで深くは考えてこなかったので、昨日の対話で、かなり輪郭づいた感じがしましたね。
一対一で向き合うのではなく、賑わいのなかでごまかしながら考える
─昨日のてつがく対話で「見返りを求めない愛はあるのか」という問いが選ばれたことからも、自分と他者という関係における思いの非対称性のようなものが、違和感や苦しみにつながることがままあるのではないかと思いました。
また、そのときに想定されているのは「一対一」の関係であることが多い気もします。永井さんは、そのあたりについてどんなことを考えますか。
永井:なんかわたし、あれなんですよね。ごまかすって、すごい大好きで。
─ごまかす?
永井:ぬるりと考えるみたいなのも大好きで。直球とか本音とか向き合うっていうのがね、超苦手で。一対一の……わたしとあなたの愛ということを考えると、もう、うわあああとなってしまう。なので、最初のほうに話した「一対一だとうまくいくときもあるのに、複数だとめちゃくちゃになる」という問いと矛盾しつつも、「複数にすることでごまかす」みたいなところがわたしにはあります。ちょっと迂回することによって、愛を考える。だから死者との愛だとか、全然違う方向から迂回して考えることで息をするようなところが、わたしには結構あって。
きっと、愛は自分には扱いきれないぐらい大きなテーマなんですよね。わたしがよく言っているのは、創世記のなかで、神がアダムをつくったあとに、「人がひとりでいるのはよくない」と言ってイブをつくったと一行書いてあるのですが、わたしはもう一行書くべきだと思っていて。「人が一人でいるのはよくない。だが、二人でいるのも絶対よくない」って書き込まれたほうがいいって言っているんですよ。二人きりだと出口なしになってしまう。賑わいのなかでごまかしながら考えることが大好きだから、対話をやっているっていうのもあるかもしれません。
哲学対話なんてまさに迂回なんですよね。直球で悩みを話すのではなく、問いにしてみることを挟むので。そうすることで、ごまかしごまかし、喋ってくれるんですよね。一番言いたいことって、一番言えないことだから。被災地に足を運ぶことが多いのですが、多くの人は、震災の話を積極的にはしたくないと感じます。だから、「ぬいぐるみがかわいいってどういうことだろう?」みたいな一見震災とは関係のない問いを出したりします。これは例ですが、それによって、倒壊した家のなかに置いてきてしまったぬいぐるみの話がぽつぽつはじまったりする。そういうことに希望を持っているのかもしれないし、自分も迂回するほうが話しやすい。ちょっとヘラヘラしながら、小出しにしながら話すことが好きなんですよね。
─一対一の閉じられた環境で向き合ったり、問題を解決したりしようとすることを極めていくと、どうしても互いの影響力が強くなりすぎたり、窮屈になってきたりすることがありますよね。それに難しさを感じたときには、もう少しひらかれた場で、複数の時間軸を取り入れながら、愛の応答や反響を捉えるというのは大切なことだと感じました。
永井:そうですね。だから「話を聞いていて大変じゃないですか?」ってよく聞かれるんですけど、大変じゃないですね。場が受け止めるので。わたしが受け止めるわけじゃないですよ。わたしだけが担うものじゃないんです。しかもその人も、場に言葉を置いてくれるというかたちなので。「この場に置いて、帰ろうね」っていうふうにしたいし、だから喋れることがある。そういう意味で、すごく対話を信じているんだと思います。
声を聞かせてくれた人たちのことを本当に絶対に忘れないし、絶対にこんなことを二度と起こさせない
─今日の撮影を担当してくださっている八木咲さんと一緒に、戦争について表現をとおして対話の場をつくる「せんそうってプロジェクト」を試みていますね。身近なできごとばかりでなく、地理的に遠い場所で起きていることや、本当は遠くないはずだけど遠いと思われていることを手元に引き寄せる場でもあるのではないかと思います。
戦争と愛を結びつけて考えることは危険な場面もあると感じます。戦争は、愛があればとか、愛がないから、というような枠組みで語るものではないと思うためです。そのうえで、人に暴力を振るったり、人の命を奪ったり、もとに戻れなくしてしまったりすることを止めたいという気持ちがこの特集をつくりたかった理由でもあって、永井さんにとって戦争ということについて、愛という視点から話しはじめられることがあればうかがいたいです。
永井:戦争は、愛があれば/なければどうこうみたいな話じゃないというのは、おっしゃる通りだと思います。なので、ここに置いておいて。そのうえで、八木さんとの「せんそうってプロジェクト」や、日頃から自分がやっていることは、愛とは絶対に関係があります。それはやっぱり、忘れないとか、なかったことにしたい、という感覚なんですよね。継承とか記憶することとか、引き受けるということを愛と言っても構わないというか。えらそうですけど、これは先人たちに言っているのではなく、愛に対して言っています(笑)。
先日、沖縄に行ってトークイベントをしたときに、客席でポロポロ涙をこぼされた人がいて。「自分たちはなにも残せなかった」って。平和運動をしている教員の方だったんです。その方が、「あなたたちみたいな若い人たちがやってくれてうれしい。でもいま日本がこんなことになっていて、本当に自分たちはなにも残せなかった」って言ったわけですよ。
「絶対にそんなことないです、安心してください」って、あえて言いたいと思いました。それは愛なのかもしれないし、愛だとしたら荒々しい愛ですけど。その人たちがいたから、絶対に踏みとどまれているものがある。「あなたがいたことに感謝している」みたいな話でもなくて、「あなたが残したものを受け取りたいと思っているし、そのうえで絶対にやれることをやります」と強く思う。そういうふうに愛を返したいと思う、というか。
特に先の戦争に関しては、当事者が少なくなってきています。それでも先人たちは「絶対に忘れるなよ!」という記憶をたくさん残しているわけですよね。自分も以前は、「いやわたしなんて」とか「とんでもありません」みたいな変な謙遜のようなものを抱いていましたし、到底担えるものでは実際ないというのももちろんそうです。それでも「絶対忘れないですから」と言いたい欲望がどんどん強くなっています。
永井:核廃絶の運動をやっている人たちと活動することがよくあって、この前も一緒に対話の場をつくったんです。核廃絶の運動をしている人たちは、若い人も含めて他者の声をやっぱりすごく聞いていて、だからこそあの活動量や姿勢なんですよ。戦争について人が語るとき、よくあるのは「戦争はしょうがない」とか、「核兵器はどうせなくならない」といった言葉です。でも核廃絶の運動を続けている友人が「顔の見える被爆者の人たちの話を自分はずっと聞いてきて、大切な人たちの頭上で炸裂したあの核兵器を、しょうがないなんて言葉で済ませられるわけがない」って言ったんですね。それは本当にそうだと思います。それをわたしは、愛と言ってもいいと思います。声を聞かせてくれた人たちのことを本当に絶対に忘れないし、絶対にこんなことを二度と起こさせないという感じ。戦争を愛という視点でもしなにか語るとするなら、こういうことを想像しますね。
─聞かせてもらった声を受け取り、行動していくことを、少しでも多くの一人ひとりがやっていくにはどうしたらいいかについて少しお話ししたいです。永井さん自身にも、かつては謙遜のようなものもあったという話がありましたが、受け取った声を大切に思いながらも、場合によっては、重積や重荷のように感じて動けなくなることもあるかもしれません。行動にうつすときの思いや葛藤のようなものがもしあれば、もう少し詳しくうかがってみたいと思いました。
永井:聞かせてもらった声に対して、義務感や重責、「わたしにできるだろうか」というふうに思う人もいるかもしれませんね。でもわたしは、重いけど、荷物だとは思わない。だってその経験を伝えることって、めちゃくちゃしんどいことじゃないですか。それなのになんて惜しみなく教えてくれるんだろうって。「こんな目に遭ってほしくない」って思いで伝えてくれるわけです。本当にありがたくて、だから忘れないよって言いたいんです。
もちろん、おののきもあります。たとえばパレスチナの状況を見ていると、本当にそう思いますね。状況は悪化していて、それは本当に苦しいです。それでも、「あなたという人がいます」ということを言い続けるしかないし、それをしている人が周りにいっぱいいるのを知っているから、やり続けることができるというのはあるかもしれません。
世界は常に、わたしに先立ってみんながいる
竹中:この特集のなかで戦争と愛というようなことについて考えようとしたときに、「自分の国を愛する」という文脈が思い浮かびます。もちろんそこに大切な人がいたり、思い出があるからこそ愛したいというのは、自然なことだと思います。そのうえで、だからと言って、自分の国の生活を守ったり保ったりするために、同じように大切な人がいて、大切なものがあるはずの人たちを排除したり、殺したりする動きがこの世界には存在していますよね。愛のなかにある、ポジティブで優しい気持ちのように捉えられる面だけでなく、愛というものを掲げながら、他者を排除することが起きてしまっていることについて、永井さんが考えていることはありますか。
永井:その文脈もありますよね。「せんそうってプロジェクト」の対話でも、「戦争が起きたとき、自分の家族を守るためだったら、相手を殺してしまうかもしれない」みたいな話が出てこなかったわけではありません。
でもそれって、愛の話なのかな? なんだか愛の話のようで、愛の話じゃないような気がするんですよね。「これは愛の話だということになっているふう」だけれど。あらゆる戦争は自衛のためだったと言われますよね。イスラエルだってそうです。自衛であり、大切な祖国を守るためだ、と言う。それもわかるけれど、なんだか若干怪しいぞ、みたいな。もちろん、市民レベルの感覚としてはあると思います。でも、「祖国を守らないと大切な人が殺されるかもしれない」と国が誘導することは、ある種のプロパガンダでもあるわけで、その扇動を誰がしたのかという問いは大事なような気もする。そこには、自分たちのなかにある愛を利用されるという構造がどこかに潜んでいて、そっちが問題な気がする……というふうに思います。
─大切な人やものが失われること、脅かされること、自分が死ぬこと、どれも恐怖がありますよね。だから「このままだと愛する人や、自分が死んでしまいます」と強い感情を引き出されると、「やられる前にやる」と思ってしまいがちだけれど、その言葉に注意深くありたいとあらためて思います。
怯えさせられる前に、そうなるもっと手前で、政治における外交や、普段の自分たちの日常のなかに、ともにあれるやり方があるかもしれないということを、もっと日頃から考えないといけないというか。自分たちを守るために誰かを追いやったり殺したりすることを「しかたないことだよね」としてしまわない世界に、やっぱりしたいというのがあるなと思います。
永井:自分には、一緒にいることをあきらめない、あきらめたくないというのがあります。その前提には、「もうすでに常に一緒に生きている事実が確実にある」ことが大きいと思います。わたしたちは生まれた瞬間に、「わたしより先にみんながいる」んです。世界は常に、わたしがいてみんながいるんじゃなくて、わたしに先立ってみんながいる。ある種、もうこの世界が与えられてしまっている。
「この人はちょっと気に入らないからデリート」みたいなことはできないと思うんですよ。もう生きちゃってるんだから、一緒に生きるしかないじゃん、みたいな感じですね。それが社会だから。だから繰り返しになりますけど、暴力を振るわない仕方で、どうやって一緒に生きていけるのかというのがすごく気になるんです。
違うことが楽しいわけではないけど、全部一緒だったら生きられない
─いまはSNSなどの状況もあって、考えが近い人と付き合うことができる心地よさがある一方、似た思想ばかりが強化されていく環境でもありますよね。自分も気をつけなければと思っているところですが、たとえば、「このイシューの意見が違うからもう付き合えない、全部だめ」みたいに関係を手放してしまうこともしばしば起きていると感じます。
もちろんそれが自分の実存に関わる話題の場合、差別的であったり、脅かすようなことを発信している人に近づくべきという話ではありません。そのうえで、「もう一緒に生きちゃっているから」ということを、他者とかかわるうえでのベースとして感じておくことは大事であるというか。
永井:トークイベントの質問で、「違う意見の人と話せません。話すのが怖いです」とボロボロ泣きながら言う人が、必ずひとりはいます。「じゃああなたは、同じ意見ってなんだと思う?」とそのときは聞くようにしているのですが、かなり危険な状態だとも思うんですね。このあいだ大学で話したときには、「意見が違うのは平気だけど、感情が違うと絶望してしまう」と話していた人がいました。自分がなにかを見て、「あ、これきれいだな」と思っても、相手がそう思わなかったら耐えられないという話です。
もちろん自分も、違う意見にぶつかるなかで、しんどいことはたくさんある。しんどいし、ままならない。でも、不幸じゃないと感じます。大変だけど、不幸じゃない。「めちゃくちゃ違うな」と思いますけど、だから生きられるというか。そうすると「違いを楽しもう」みたいな話になっていきそうなのですが、「違わなきゃ困る」という感じですね。違うことが楽しいわけではないけど、全部一緒だったら生きられないと思う。「全部一緒じゃなくちゃ」とか、そういう価値観がいいと思わせる社会のほうがまずいと思います。
永井:対話の場をひらくと、「違う」や「同じ」は、そんなに簡単なことじゃないと毎回思います。たとえば、死刑制度や改憲のように、賛成か反対かでわけられそうな議題でも、話してみると、同じように賛成派でも理由が全然違うこともざらにあります。あるいは、賛成派と反対派の人が話しているうちに、お互いの意見が重なることもあります。
重なるけど同じじゃない。違うけど重なる。それがずっと繰り返されることが、聞くことのおもしろさです。「核兵器をもっと持ったほうがいい」と言う人と、自分の意見は異なりますが、理由を聞いてみると「まあそこの感情は自分も重なるな」ということが起こるんですよね。SNSでは「この発言をしたからアウト」となりやすいけど、生身だとそこがあまり気にならなくなって、「とりあえず聞くか」になるのが大きな違いだと思います。
─とりあえず聞くか、いいですね。永井さんは対話の場でも、話すということより、聞くということに重きを置かれていますよね。
永井:無理やりそういう場をつくるんですよね。対話の場はわたしにとってすごく人工的なものだし、非日常的なもの。「みんなで試みるもの」って言い換えていますけど。でも、対話の中で起こることは、とても自然的な人間の感情がベースにあります。
いまの社会のなかで、あまりにも声が聞かれていないなという感触があります。「聞くとなにが見えるか」という以前に、あまりにも自分の声が聞かれていないし、相手の声を聞けていない。そんなアンバランスさが気になるから、「聞く」を試みようという感じです。
でも、「対話しよう」って普通に言っても誰もやらないですよね。そんなことを言われても、怖いし、気持ち悪いじゃないですか。自分だって絶対に嫌だって思う。でもそういうふうに、対話にはキラキラしたところばかりでなく、「嫌だ」という思いがみんなあるよねっていうところからはじめないと、というふうにも思います。
─非日常性や、迂回という言葉もさきほど話されていましたが、永井さんにとって日常から少し離れることは、生きるうえで大切だという感覚がありそうですね。
永井:不条理って言葉が好きなんです。ままならなさと言い換えてもいいと思います。子どもの頃からずっと、「こういうもんだ」とか「ここが行き止まりだ」「これが正解だ」とかがしんどかったので。「正解があったらいいよね」ってよく言われるけど、わたしは正解があるほうがしんどいと思っている。「まだわからんぞ」ということに希望を感じるんです。
対話に関しても、去年ぐらいに、「やばい、もしかしたらこのままだと対話とはなにかがわかってしまいそう……?」という瞬間がありました。「対話ってこういうことです」と言えそうになっている……? やばいやばい……!! みたいな。でもそのあと、対話の場をひらいたときに、まったく予測不可能なできごとが、どっかーんと起きたんです。「よかった、まだ全然わからなかった」と思いました。他者もそうですよね。他者は自分にとって常に意味がわからないし、不条理で、めちゃめちゃ脅かされるけど、それがないと生きられない。八木さんとだって、こんなに一緒にいても「ああこんな一面があるのか」とよく思う。それを100パーセント最高だとも思わないけど、本当によかった、と思う。不条理というのは、本当に最悪だけど、最高でもある、そういう感覚ですね。
─昨日のてつがく対話でも「相手のことが理解できるから、愛しているということではないよね」といった話が出ていました。永井さんのなかにも、「めんどくさいけど愛してる」とか「最悪だけど最高」というような、人間関係を結ぶときの「でも」「けれど」をたずさえ続けるところがある気がしました。「めんどくさいけど、たよりないけど、ままならないけど」の「けど」の部分を否定しないでいることが、愛を考えるうえでも重要な気がしたんです。
永井:多くの人は、対話はいいよねと言うけれど、「思考力やコミュニケーション力が上がりそう」といった対話の妙にきらきらしたところだけが需要され続けている感じがあります。大変そうだし、なんだか怖いしという理由で、つくり手にはあんまりなりたがらない。
だから、対話をするときには必ず最後に、あなたが対話の場をつくってくださいってお願いします。そうすれば、この世にひとつ増えるから。わたしの場がもっとたくさん増えてほしいというよりは、小さいものが増殖してほしい。もっと言えば、それはてつがく対話じゃなくてももちろんよくて。福祉や学校、そういった場でやっている人もたくさんいる。お二人がつくっているこの場もそうだと思います。それでもまだ足りない。
いま拠点をつくろうとしています。継続的にひらいておける場や、人が来られるような場をめざして。そこに言葉も蓄積していきたい。いままでは呼ばれていって、自分がいかに応答するかということを10数年やってきていて、それも続けたいのですが、自分自身も呼びかけないといけないし、一緒にやろうよと言える人でいないといけないなという思いもあって。わたしは文章を書くのが好きなので、言葉を書いてみる場や、一緒にものをつくってみる場もいい。詩を読むのもいいですね。いろんなことができる拠点をつくりたい。そして、常にすでに一緒にいる人と、どうやってまた一緒にい続けるかを試みる人を増やしたいし、暴力ではない仕方で人と一緒にいることを試みる場をもっと増やしたいです。あまりに足りないから。
永井玲衣
人びとと考えあい、ききあう場を各地でひらく。問いを深める哲学対話や、政治や社会について語り出してみる「おずおずダイアログ」、せんそうについて表現を通して対話する写真家・八木咲とのユニット「せんそうってプロジェクト」、Gotch主催のムーブメントD2021などでも活動。著書に『水中の哲学者たち』(晶文社)『世界の適切な保存』(講談社)『さみしくてごめん』(大和書房)。第17回「わたくし、つまりNobody賞」受賞。詩と植物園と念入りな散歩が好き。
プロフィール
書籍情報
me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら
*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。
あわせて読みたい
特集:愛も生活も、たよりないから
2025/07/30
2025/07/30
特集「愛も生活も、たよりないから」を読んでくださるみなさまへ
2025/07/30
2025/07/30
青葉市子×ミシェル・ザウナー 異なるわたしたちを音楽が包み込む。複雑な世界のなかで
どれだけ違う人間性でも、音楽という駅に入れば、混じり合うことができる
2025/07/30
2025/07/30
この部屋で、生きている。わたしの家の愛おしいところ
どんな家で、誰と、どうやって暮らしてる? 生活を愛する工夫を宿して
2025/07/30
2025/07/30
ままならない日々を、お気に入りの服と。一週間コーディネート
装うことを楽しみ、生活を生き抜く。7日間のファッションダイアリー
2025/07/30
2025/07/30
哲学対話×弾き語りライブ。永井玲衣・惠翔兵・惠愛由を迎えたCandlelightレポ
みんなで哲学対話をしてからライブをきく。「つながり」ってなんだろう?
2024/07/22
2024/07/22
同じ日の日記
大人になっても正月がこわい/永井玲衣
2022年1月1日(土)の同じ日の日記
2022/02/10
2022/02/10
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。