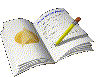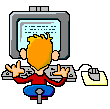3歳年上の女性との出会いによって自分を理解する16歳を描く。映画『美しい夏』監督インタビュー
1940年代に書かれた原作に、娘や祖母、母、自分自身がティーンだった頃の気持ちを込めて
2025/7/31
2025年8月1日に公開される映画『美しい夏』は、戦争の影が忍び寄る1938年のイタリア・トリノを舞台に、瑞々しい映像で若き人々の美しい夏を描きます。
地元からトリノに出てきたジーニアは、兄・セヴェリーノと暮らしながら洋裁店のアトリエで働く16歳。そんな彼女はある日湖畔で、絵画のモデルとして生計を立てる3歳年上の大人びた女性、アメーリアと出会います。
トリノに馴染めないまま思春期をやり過ごすジーニアと、自立してたくましく生きるアメーリア。対照的な二人は、互いの姿に自分の未来/過去を投影し、惹かれ合っていきます。さらに、アメーリアにモデルの仕事や社交場での振る舞いを見せてもらい、画家の男性たちを紹介されたジーニアは、大人の階段上り始め、さまざまな感情を知り、傷つき、挫折をして……。
世界中で長年愛されるチェーザレ・パヴェーゼによる1949年の小説『美しい夏』を映画化した、ラウラ・ルケッティ監督に話を聞きました。新たな出会いや初めての経験に満ちた、ティーンの物語を描くにあたって、大切にしたこととは。
─チェーザレ・パヴェーゼによる1949年の小説『美しい夏』は世界中で長年愛されていますが、今回出版から70年以上の時を経て映画化されました。ルケッティ監督はこの小説をどのように受け取りましたか?
ラウラ・ルケッティ:チェーザレ・パヴェーゼはイタリアで有名な作家ですが、映画化はほとんどされていないんです。それはきっと、彼の書く小説にははっきりとした話の筋がなく、映画化するのが難しいから。『美しい夏』も、ジーニアの頭の中の考えを中心に綴られていて、はっきりとした筋はないと言えます。
映画では、年上の女性・アメーリアに惹かれながらさまざまな経験をして大人になっていくジーニアの思春期の変化を中心に描いていますが、原作小説だとジーニアとアメーリアの関係より、ジーニアと画家との間のストーリーのほうがたくさん書かれているんです。またパヴェーゼ自身は、『美しい夏』を「ヴァージンだったジーニアが自分を守ろうとする物語」と説明したこともありました。つまり、女性同士の関係性に注目することもできれば、ジーニアと画家の物語として読むことも、ジーニアが自分を守ろうとする物語として捉えることもできるくらい、さまざまな切り取り方ができる作品なんですね。
私もこの本を何度も読み、映画化にあたって複数のアイデアを持っていたのですが、そんななかでページが燃えて感じられるように私を惹きつけたのは、ジーニアとアメーリアの親密な関係について書かれている部分でした。なので、一番感情に訴えかけてくると感じた二人の物語にフォーカスしようと決めたんです。そして、原作にある普遍的な部分を掬いつつ、アメーリアという一人の人間との出会いから、16歳の女の子が自分を理解していく成長譚に仕上げました。
─新たな出会いや初めての経験、その喜びと痛み、そして自身の変化に対する期待と戸惑いが丁寧に描かれているところに普遍性を感じました。舞台は1938年のイタリアですが、違う時代、違う場所で生きる私もかつてティーンエイジャーであった頃を思い返し、それまでの日々を一変させるような出会いや、憧憬や羨望や惹かれがないまぜになったような気持ちには、共感する部分がありました。
ルケッティ:そういうふうに言ってもらえるのが一番嬉しいです。チェーザレ・パヴェーゼが書いた原作の素晴らしいところは、ティーンの女の子の気分を、まるで実際に体験したことがあるようなリアリティで描いているところだと思います。
さらに私は、この作品の脚本を書くにあたって、当時16歳だった自分の娘のことを参考にしました。もちろん娘だけでなく、祖母や母、自分自身がティーンだったときの気持ちも込められていると思います。というのは、おっしゃったように時代や場所が違っても、少女から大人の女性へと変化するなかで狭間の時期があると考えているからです。
─ルケッティ監督は、そんな少女から大人へ変化する過程をどのように捉え、今作ではどのように表現しようと考えましたか?
ルケッティ:まず思春期の女性の変化として、身体的な欲望が生まれることが多いんじゃないかと考えました。誰かに注目されたい、触れられたい、愛されたいという気持ちですね。だけど、ジーニアの16歳という年齢だと、自分が何を求めているのかがまだよくわからない場合もあると思います。そのわからなさも映像で表現できたらと思いました。
また、ジーニアの場合、近くにいる男の子と恋愛をして、結婚して、家庭を持つのが「普通」というなかでそれまで生きてきたわけですよね。一方で、やがて親友になったアメーリアに恋をする。もともと想定していたものとは異なる、自分自身の本当の気持ちを見つけていくジーニアの姿を描くことも意識しました。
世界中の映画祭で女性たちから集まった声
─ジーニアがアメーリアに対して抱いている感情や、ジーニアとアメーリアの関係性については、どのように描こうと思いましたか?
ルケッティ:ジーニアとアメーリアの間に芽生えた愛をどういうふうに描くかという選択は必要でした。そして二人で踊るシーンを象徴的な位置付けにしました。あのシーンは、周囲にいる人たちが消えてしまったかのように二人だけの世界が出来上がって、お互いへの愛情を表現する、いわば二人のラブシーンなんです。
二人がダンスをするシーンの前にはジーニアが画家の男と行為をしましたが、それは彼女にとって素晴らしい経験ではなかった。行為中にジーニアは、それが自分が探している愛の行為ではなかったと理解しました。対して、アメーリアとジーニアの間の愛は、お互いを思いやり二人で一緒にいる時間のなかで、とても自然に育まれていった。
ルケッティ:映画の表現では、初体験が素晴らしいものであったという描かれ方も多いと思います。でも実際、最初の体験がよかったかどうか人に聞いてみると、素晴らしいものだとは思えなかったと答える人も多いんじゃないでしょうか。だから、ジーニアの初めての体験も、結果的に本人が通過しなくてはいけないことと感じてただ耐えるような行為として描いています。
世界中の映画祭でこの作品を上映してQ&Aをした際、たくさんの女性たち、かつて少女だった人たちに「よかったとは言えない初体験を描いてくれてありがとう」と言ってもらいました。
─社会やコミュニティのなかで、あるいは映画などの表象から、「こうあるべき」という固定観念が生まれ、その固定観念に苦しめられてきた人は多くいると思います。残念ながら、性的な行為を通過儀礼的に扱うことや異性愛規範は実際に現代にも根強くあるため、映画祭のQ&Aでもそうした声があったのかもしれません。
ルケッティ:アメーリアの仲間である画家たちに認めてもらうためにジーニアが無理をして服を脱ぐシーンも、観ていて悲しくなりませんでしたか?
─そのシーンも、とても胸が痛みました。
ルケッティ:ジーニアは、アメーリアに仲間を紹介される度に「君もモデルなの?」と聞かれました。華やかで芸術的なアメーリアの仲間たちに認めてもらうためにはどうしたらいいか考えて取った行動でしたが、自分の気持ちを裏切って本当はやりたくなかったことをしてしまったので、傷つきます。
─思春期に背伸びをしてしまうことがあるのはわかる気がします。一方で、社会やコミュニティ、個人対個人の関係性のなかで生まれる圧力や、圧力によって自分の気持ちを裏切らざるをえなくなることは、とても苦しいですね。
痛みを自分で理解して、乗り越えて、その後どうするか選択できるようになるために
─ジーニアは、プライベートに夢中になるあまり、それまでコツコツと続けてきて評価され始めた仕事でつまずいてしまいます。
ルケッティ:そうですね。でももしつまずいてしまっても立ち上がれば、新しい、より成長した自分になることができます。大人になるって、そういうことの繰り返しなんじゃないかと思います。
私は、失敗をすることは人生において避けられないこと、成長のために必要なことだと考えています。何歳になっても傷ついて立ち上がらなくてはいけないことや学ぶことはたくさんありますし、大人になって初めて直面する困難もありますが、若いときのほうが傷の治りが早いので、たくさん失敗して成長するのはいいことだと思います。
─何かや誰かに傷つけられること自体は肯定されるべきでないですし、一人で立ち向かうのが困難な傷つきもあると思いますが、つまずいても立ち上がれると信じることは日々を生き抜く支えになると思います。作中では、ジーニアの兄であるセヴェリーノの「いずれ慣れるさ。だが痛みには慣れるな」というセリフも印象的でした。
ルケッティ:そのセリフはこの作品のなかで一番好きなセリフの一つです。痛みに慣れてしまったら、もう痛みと闘えなくなってしまうので、痛みを感じることはやめてはいけないと思いますね。そうして感じた痛みを自分で理解して、乗り越えて、その後どうするか選択できるようになるのが私が考えるハッピーエンドです。
─ジーニアは、田舎から出てきて兄のセヴェリーノと暮らしています。食事やジェラートを分け合い、仕事の様子を聞き合い、生活を支え合う兄妹の関係にも胸を打たれました。原作ではセヴェリーノはあまり前面に出ていないそうですが、映画化にあたって二人の関係性を描いたのはなぜですか。
ルケッティ:セヴェリーノは原作では細かく描かれておらず、映画化にあたって私が人物像を作り上げました。舞台がファシズム時代ということもあり、小説で描かれているセヴェリーノは男性中心主義的で、ジーニアに「食事を用意しろ」とか「こんな夕方にどこに行くんだ」とか、そういうこと言うぐらいで、大きな役割は持っていないんですね。
でも映画では、ジーニア自身が自分の思いに気づく前に彼女の思いに気づき、どんなものであれそれを受け入れてそばにいる人物、まだいろいろなことに決心がつかず迷っているジーニアを、助けてくれる人物としています。そうした理由の一つには、私には兄がいて、兄とのつながりが深いことがあります。
─原作と映画の違いが興味深いです。ご自身の体験や思いも込められているんですね。
ルケッティ:セヴェリーノの細かい描写以外に原作に加えたのは、洋裁店のアトリエでの、ジーニアの仕事の描写です。原作では、彼女がアトリエで仕事をしているという事実くらいしか出てこないのですが、映画ではかなりその仕事内容を映し出しました。
パヴェーゼの原作がジーニアの感情をメインに描いている分、映画化する際に物語の筋や展開が必要だと考えたんです。なので、仕事で少しずつ評価されていって、もっと上手くいく可能性もあったけれど愛のために仕事を犠牲にしてしまい……という流れが重要でした。また、私の祖母がお裁縫をしていたこともあり、ジーニアがアトリエで仕事をするシーンは、私もとても楽しみながら撮影しました。
─物語は普遍的でありながら、登場人物のスタイルからは当時の空気感が感じられました。
ルケッティ:トリノという街は当時の雰囲気をかなり残しているので、ラッキーだったと思います。衣装は、スタッフのお母さんやおばあさんが持っているものや、古着屋さん、骨董市などを探してくれました。美術監督や撮影監督もたくさん努力してくれたおかげで、1930年代の雰囲気をパーフェクトに再現できたと思います。予算が少ないときは、いつも以上にパッションが大切ですよね(笑)。この映画はキャストとスタッフのパッションで完成しました。
ラウラ・ルケッティ
1969年、イタリア・ローマ生まれ。両親は共にオペラ歌手のヴァリアーノ・ルケッティとミエッタ・シーゲレ。1997年、短編映画『In Great Shape(英題)』を初監督。2004年には、第76回アカデミー賞で高い評価を得た映画『コールド マウンテン』(03/アンソニー・ミンゲラ監督) についてのドキュメンタリー『メイキング・オブ「コールド マウンテン」』を共同監督・製作。『Hayfever(英題)』(10)で長編デビューを果たした後、短編アニメ『レアの大好きなこと』(16)が30以上の映画祭で選出され注目を集める。短編アニメ第2作『Sugarlove(原題)』(18)は第33回ヴェネチア国際批評家週間の特別招待作品として上映されたほか、ナストロ・ダルジェント賞で最優秀アニメーション賞短編賞を受賞。長編2作目となる『Twin Flower(英題)』(18)が、第68回カンヌ国際映画祭に選出、トロント国際映画祭でもFIPRESCI特別賞を受賞。2021年には、10代のリベンジポルノをテーマにしたTVシリーズ『Nudes(原題)』で監督を務め、イタリアでの初回放送で100万回再生超えを記録。長編第3作『美しい夏』(23)は、ロカルノ国際映画祭のピアッツァ・グランデ部門に出品。同作主演ディーヴァ・カッセルが 出演したNetflixリミテッドシリーズ『山猫』(25)でも共同監督を務め、巨匠ルキノ・ヴィスコンティによる名作のドラマ化としても話題になるなど、現在イタリア映画界が注目する映画監督の一人として知られる。
©Fabrizio Cestari
プロフィール
作品情報
me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら
*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。
あわせて読みたい
『フォーチュンクッキー』監督が語る、アフガニスタン人の女性の物語から人間の普遍性を描いた理由
主人公のドニヤは、他の文化圏の同じ年頃の人と変わらず、夢や希望を抱いている
2025/06/26
2025/06/26
SPONSORED
創作・論考
“怖れ“を甘受し、欲望を取り戻す旅─映画『エマニュエル』に寄せて/戸田真琴
新たにエロティシズムについての映画が生まれるのならば、きっとここから、こんなふうに
2025/01/10
2025/01/10
山中瑶子監督が『ナミビアの砂漠』で描きたかった、気持ちと身体のズレと思い通りにならない他者
「いじわるで、嘘つきで、暴力的」な主人公・カナと周囲の人々との関係性
2024/10/18
2024/10/18
創作・論考
爪の先まで映画を観る幸福に包まれる。金子由里奈が綴る『墓泥棒と失われた女神』
社会批判がユーモアを持って鮮やかに読み取れるロルヴァケル作品の魅力
2024/07/29
2024/07/29
世界はいつも、ここにある。映画『Here』バス・ドゥボス&リヨ・ゴンが話す
あなたは決してひとりではない。対立ではなく、つながりの物語を
2024/03/25
2024/03/25
映画『パトリシア・ハイスミスに恋して』。監督が語る “日記から映画をつくること”
1950年代の米国でハッピーエンドを迎えた初のレズビアン小説『キャロル』の作家
2023/10/31
2023/10/31
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。