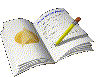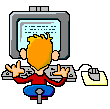バッシャール・ムラードは歌う。占領、家父長制、ホモフォビアからの解放のビジョン
自分ではもう語ることができなくなったパレスチナの人々の物語を
2025/2/20
エルサレム在住のパレスチナ人クィアとして受けるマイクロアグレッションから、アパルトヘイトや家父長制による抑圧、日常的な死の恐怖、そして求める解放についてまで、ポップにユーモアたっぷりに歌うバッシャール・ムラードさん。クィア&フェミニズムをメインテーマとする東京のDJパーティーWAIFU主催で、2024年12月20日に初来日公演が行われました。
バッシャールさんの楽曲では、さまざまなラベルと抑圧が絡まり合いながら、いくつもの現実が音に乗って立ち現れます。アーティストとしてジェノサイドに声を上げることの必然性、イスラエルのピンク・ウォッシングによるパレスチナ人クィアへの影響、一種のコーピングとしてポップミュージックを作り続けること。音楽を通して解放のメッセージを伝え続けるバッシャールさんの経験と思いが溢れたインタビューをお届けします。
―はじめての東京はどうですか?
バッシャール:滞在して1週間ほどですが、本当に素晴らしい時間を過ごしています。以前から日本、特に東京は型にはまらないアイデアに満ちた場所だろうと期待していたんです。日本のカルチャーに触れたい、パフォーマンスをしたいとずっと思っていましたが、その夢がこんなに早く実現するとは思っていませんでした。
滞在中は来日をオーガナイズしてくれたWAIFUのメンバーと一緒に行動することで、その視点を通して東京を知ることができています。WAIFUのメンバーをはじめ、たくさんの素晴らしいアーティストや個人と出会うことができました。様々なパレスチナ解放デモやイベントにも足を運んで、自分がつながるべき人とつながることができていると感じます。日本を離れたあともこの関係を大切にして、将来何ができるのか考えていくのが今から楽しみです。
―2024年12月20日にはWAIFUで初来日公演がありました。深夜の開催でしたが、会場には多くの人が集まっていましたね。パフォーマンスをしてみていかがでしたか。
バッシャール:すごく楽しかったです! ショーの計画についてWAIFUと連絡を取りはじめたのはたった2ヶ月前なんです。急ピッチで進めたにもかかわらず、これだけ多くのアイデアを実現できたのは驚きでした。
まず、会場のStudio Freedomが素晴らしい場所でした。ステージに巨大なスクリーンがあって、ビジュアル表現を取り入れることでショーに奥行きを与えることができました。
ライブ衣装はWAIFUのプロデュースと紹介で実現しました。渡辺未来さん(独立系ファッションデザイナーの服を扱うショップ「見た目!」主宰)とのコラボレーションで、渡辺さん自身のブランドWatanabe Mikuのアイテムに加えて、Trashy Clothingという友人のパレスチナのデザイナーのブランドのアイテムも取り扱っていたのでいくつかお借りしました。最後に着た衣装はアーティストの田村虹賀さんのデザインですが、これもクレイジーで素晴らしかったですね。WAIFUの緑さんのリメイクした着物やAsamiさんのBLACK TRIANGLE DESIGNのアクセサリー、メイクアップアーティストの降幡あずささんのメイクも素敵で、すべてを組み合わせて素晴らしいショーを作り上げることができました。
最近はヨーロッパでもショーをする機会がありますが、パレスチナ人がライブをすることに慣れているからなのか、そこまで力を注がれていないと感じることがあります。だけど東京では、ショーに向けて一人ひとり努力してエネルギーをたくさん注いでくれているのが伝わりました。
「アーティストにとっては、直接的に語らないこと自体が何かを語ることになる」
―パレスチナでは占領と抑圧が常態化していて、2023年10月以降はガザでのジェノサイドがエスカレートしています。さまざまなアーティストがこのことについて発言したり、またはしなかったりしていますが、このことをどう見ていますか。
バッシャール:「アートは政治的であるべきか?」という議論がありますが、まず私にとってアートはポリティカルである方が自然なものです。私の音楽はオートバイオグラフィー(自叙伝)的ですし、いま生きている現実が政治的な影響を受けているのだから、作品やショーに反映しない方が不自然です。
それにアーティストにとっては、直接的に語らないこと自体が何かを語ることになります。「語らない」ことは実際には政治的な選択で、現実を避けることを意味するからです。
この1年間、私は多くのアーティストの音楽を聴くのをやめました。彼らが選んだ沈黙や、ガザで起こっていることを正当化する態度のためです。多くのアーティストが自分自身を「革命的」として売り込み、世界平和や正義を気にしているふりをしています。しかし一部の人は、それをキャリアのための手段として利用しているだけなのだとわかりました。
一方で、声を上げたり、学ぼうとしたりしているアーティストもたくさんいました。彼らは自分があまり詳しくないことを認めた上で、パレスチナ人や詳しい人々と話をして理解を深めようとしています。本質的なことを言っているアーティストが誰なのかを知ることになった1年間だったと思います。
同時に、私たちはアーティストもまた人間であることを忘れてはいけないと思います。アーティストは標的になりやすく、私たちは時に過剰な期待を抱いたり、批判の矢面に立たせたりしてしまうからです。
今の世の中にはプロパガンダやフェイクニュースがあふれていて、本当のことを理解するまでには時間がかかることもあります。私の責任として、人々にパレスチナのことを伝え続けていきたいと思っています。正直なところ重荷に感じる時もありますが、やめることはできないので。
「パレスチナは分断されているから、コミュニティを形成するのがとても難しい」
―バッシャールさんはエルサレムで生まれて長年住んできました。パレスチナ人のクィアとして、エルサレムで生活するのはどんな体験ですか。
バッシャール:この1年間はアーティスト・イン・レジデンスでフランスに滞在していますが、それ以前は大学時代を除いてずっとエルサレムに住んでいました。
パレスチナ社会ではクィアでいることが依然としてタブー視されているので、変えていきたいと思っています。ただ、私たちは常に殺されず生き残ることに必死で、社会的な変革に取り組む余裕がありません。新しい動きが起こっても、すぐに消えてしまうことが多いです。
それはパレスチナが非常に分断されているからでもあるでしょう。エルサレム、西岸地区、占領下の他の地域、そしてガザ。それぞれ完全に分断されていて、自由に行き来することはほとんどできません。コミュニティを形成するのがとても難しいんです。
鍵は帰還の権利のシンボル。1948年のイスラエル建国に伴い70万人以上のパレスチナ人が土地を追われたが、いつか故郷に帰れるようにと、今も家の鍵を持っている人々がいる。“Stone”にも「鍵をずっと手放さずに持っている。いつか自由になったときに戻れるように」という歌詞が登場する。
そして、エルサレムではそもそもパレスチナ人が集まれる場所が非常に限られています。さらにクィア・コミュニティとなると、そのための場所はほとんどありません。友人同士の小さなグループで集まって、それがスペースになるというのが現状です。私が地元で行うイベントやコンサートもその一つです。クィアだけでなく、同じ価値観を持ち解放を願う人々が集まれる数少ない場所になっています
分断はされているものの、アンダーグラウンドなシーンは存在しています。ハイファ(レバノンに近い地中海沿いの街)にアンダーグラウンドなクィア・スペースがあって、私もよくパフォーマンスをしていました。ラマッラー(ヨルダン川西岸地区中部の街)にもそうしたスペースがありましたが、数年前になくなってしまいました。
というのも、コロナが音楽シーンも、クィア・スペースも、あらゆるものを終わらせてしまったんです。それがようやく収まってきて、「日常」——日常というのがなんなのかわからないけど——に戻れると思った矢先に、ジェノサイドがはじまりました。
―ピンク・ウォッシング(イスラエルがLGBTQ+フレンドリーなイメージを積極的に打ち出すことで、パレスチナで行っている占領や虐殺を覆い隠し正当化する戦略。現在ではイスラエルに限らず、自らに不都合な事実を隠すためにLGBTQ +フレンドリーなイメージを利用することを意味する)は、パレスチナ人のクィアにどんな影響を与えていますか。
バッシャール:パレスチナ人で保守的な考えを持つ人がレインボーフラッグを目にするのは、イスラエルの国旗と一緒に掲げられている時だけです。つい最近も、破壊されたガザの街と戦車をバックに、イスラエルの国旗とレインボーを組み合わせた旗を掲げた兵士の写真(イスラエル公式Xにて投稿されたが既に削除されている)が拡散されました。このような画像を見た保守的なパレスチナ人は、クィアという存在自体を否定的に見るようになります。クィアとイスラエルが結び付けられ、ネガティブなイメージを生んでいるんです。
この話題は何時間でも語ることができますが、非常に複雑な問題なので私たちは言葉を慎重に選ばなければなりません。保守的なパレスチナの社会を批判すると、イスラエルがその言葉を利用してまた私たちを攻撃しようとするからです。
私はクィアのパレスチナ人で、非クィアのパレスチナ人と同じように占領下で苦しんでいます。同時に、イスラエルがパレスチナ人のクィアにもたらす抑圧や、保守的なパレスチナ社会からの抑圧も受けています。非常に困難な、苦しい状況にいると感じます。
抵抗のためにラベルは必要。でも、それだけで定義されたくはない
—こうした状況下でバッシャールさんがパレスチナ人のポップアーティストとしてクィアネスを表現すること自体が、ピンク・ウォッシング戦略を打ち消し、パレスチナ人のクィアを勇気づける力を持つものだと思います。
バッシャール:そうですね。ただ、私はアーティストとして、音楽やアートを通じていろんなことについて話したいと思っています。もちろんその中でピンク・ウォッシングやクィアについて話すこともあるのですが、その話題が中心になることで、自分が話したい他のテーマを語る余地が奪われてしまうように感じることがあります。
私はラベルが好きじゃないんです。「パレスチナ人」だとか、「クィア」だとか、そういうことは成長する中で身につけていくもので、生まれた時はみんなただの一人の人間でしょう。
私がラベルに言及するのは、それが必要だからです。パレスチナ人はいつも非人間的に描かれ、野蛮で非人道的だと見なされます。パレスチナ人のクィアは「保守的な社会の被害者」として、安全を求めてイスラエルに避難すべき存在としてフレーム化されることが多いです。私たちが今生きているこの世界で、存在を可視化して、ピンク・ウォッシングのようなプロパガンダに対抗するためにはラベルが必要なことがあります。
でも、それは一時的なものであってほしい。ラベル自体、一種の抑圧だと思います。押し込められる感覚があるし、いつまでもラベルに縛られて生きることは望んでいません。必要性は理解しているけれど、それだけで自分を定義されたくはない。いつも葛藤しています。本当はすべてのカテゴリーを超えたいと思っています。
―2024年にリリースした“ITSAHELL!”という曲があります。この曲の最後では、まさにラベルという抑圧から解放されたビジョンが歌われていました。
バッシャール:この曲を作ったのはガザのジェノサイドがはじまる前です。アイスランドのユーロビジョン・ソング・コンテストのための曲で、ビートを作ってくれたのはWAIFUのショーでもDJをしてくれたハタリ(Hatari)のエイナル・ステッフ。彼からもらった曲を聴いた時、「このビートからは地獄が思い浮かぶ」と思って歌詞を書きはじめました。
Bashar Murad- ITSAHELL! (LYRIC VIDEO)
最初は「ISRAEL」というタイトルだったんです。でも、もっと曖昧にすることにしました。曲の前半で歌っているのは、クリスチャン・シオニズム(イスラエル国家と聖書の「約束の地」の解釈を意図的に結びつけることで、パレスチナにおけるイスラエル国家設立を正当化するイデオロギー)やパレスチナ人の非人間化といった、私の故郷にある文字通りの地獄のような現実についてです。でも、最後は希望が持てるトーンで終わりたいと思いました。暗闇だけでなく、光を描きたかったんです。そこで、私が思う自由や解放のビジョンを表現しました。占領、入植者植民地主義、家父長制、ホモフォビア、あらゆる抑圧からの解放です。
私たちは誰かを傷つけない限り、すべての人が自由と尊厳の中で生きられるべきだと思います。最後のポジティブなメッセージに、その思いを込めました。
「音楽を通じて、自分ではもう語ることができなくなった人々の物語を伝えなくてはならない」
―“Stone”という曲では、お父さんのバンド、サーブリーン(SABREEN)の“On Man”をサンプリングしていますね。まず、お父さんからどんな影響を受けたか教えてください。
バッシャール:父は意図して何かを教えようとしていたわけではないかもしれませんが、一緒に過ごす中で自然と多くのことを学びました。
サーブリーンの曲はすべてパレスチナの詩人、たとえばマフムード・ダルウィーシュやフセイン・バルグーティらによって書かれた詩を元にしています。私は幼い頃からそれらの詩に触れていましたが、当時はその価値に気づいていませんでした。単に歌として覚えていただけで、それがどれほど豊かなものかを理解するのはずっと後のことです。でも、その言葉は私の潜在意識に刻まれていたと思いますね。
サーブリーンはその後、エルサレムを拠点として、パレスチナの音楽やアートの発展を促進するNGOも発足しました。NGO発足の段階では、音楽のもう一つの側面も間近で見ました。つまり、曲を作って演奏するというクリエイティブな側面ではなく、どうやって資金を調達するのか、政治的な抑圧の厳しい状況下で音楽を作り続けるにはどうしたらいいのか、といったロジスティックな側面です。
パレスチナでアーティストとして音楽を作り続けるのはものすごく困難なことですが、私は父から音楽を通じて自由になる方法を教わったと思っています。エルサレムの抑圧的な現実や、占領下のパレスチナという厳しい状況の中にいると、簡単にそこに飲み込まれ、外の世界が存在することを忘れてしまいます。それでも自由を夢見ること、現実を超えていくビジョンを持つことを学びました。
―“Stone”で“On Man”をサンプリングしたのはどうしてでしょう? それから、ガッサーン・カナファーニー(『太陽の男たち』『ハイファに戻って』を書き、パレスチナ解放運動でも重要な役目を果たした小説家)がパレスチナ解放について話している音声も使われていますね。WAIFUのショーでも、この音声の直後にひときわ大きな歓声を上げていた人がいたのが印象的でした。
バッシャール:ポップミュージックが素晴らしいのは、過去の要素を取り入れて新しいものを生み出せるところです。“On Man”はサーブリーンの中でもお気に入りの曲で、自分の子ども時代やエルサレムを象徴していると感じます。でも、若い世代はこの曲を知らないと感じていたので、自分の音楽を通して再構築し、この曲を紹介したいと思いました。
Bashar Murad – Stone
ガッサーン・カナファーニーを引用したのは、彼の言葉が「解放とは何か」のイメージを的確に表現していると感じたからです。ポップミュージックにはたくさんの人に広く届ける力があります。新しくこの曲を聴いた人はパレスチナについて何も知らないかもしれませんが、私の音楽にあるヒントやリファレンスが、きっと知識を広げていってくれるはずです。
―YouTubeで、バッシャールさんがリフアト・アルアライールの「If I must die」に曲をつけて歌っている動画を見ました。“Stone”もそうですし、自分の作品にパレスチナの他のアーティストをよく引用していますね。
バッシャール:他の作家のアートを引用するのが好きで、いろんな国のアーティストを参照します。ただ、その中でもパレスチナのアーティストを引用するのは特別な意味があります。
「If I must die」は私にとって特別な詩です。リフアト・アルアライールが2023年12月にガザで殺されたあと、世界中の人にとっても大切な詩になりました。この詩は、私にアーティストとしての自分の役割を思い出させてくれました。彼は「物語ることが抵抗である」と信じていました。私は、その抵抗を音楽で続けなければいけないと思いました。音楽を通じて、自分ではもう語ることができなくなった人々の物語を伝えなくてはならない。
Bashar Murad – If I Must Die – A Poem by Reffaat Alareer (Palestine Vision 2024)
パレスチナには豊かな歴史と文化があります。そして、音楽やアートはそれを生き続けさせることができる。それが自分の役割でもあると感じています。
「ダークなユーモアは自分が現実に対処するのを助けてくれる」
―2021年ごろは“Antenne”など、ポップでユーモアのある曲とMVも多く作っていました。こうした曲についても教えてください。
バッシャール:ポップさやユーモアを取り入れるのは、まず一種のコーピング・メカニズムなのだと思います。こんなにひどい現実の中で毎朝目を覚まし、仕事へ行き、生き続けるためには、面白がって笑い飛ばさないとやっていけないというのが大きな理由です。
次に、私は音楽に風刺やダークなユーモアを取り入れるのが大好きです。“Antenne”が収録されているEPは“Maskhara”というタイトルで、これはアラビア語で「嘲笑」「くだらないこと」といった意味。このEPでは、私たちの現実がどれだけ馬鹿馬鹿しいかを面白がることをテーマにしています。
Bashar Murad – Antenne Ft. tamer Nafar
MVでも、ポップな色彩と美しいショット、ユーモアに包むことで、私たちの現実がどれほど馬鹿げているかを最大限に示しています。私たちの現実とはつまり、「イスラエルは占領国家か?」「パレスチナ人はアパルトヘイト下で生きているか?」「ガザで起こっていることはジェノサイドか?」といったことを、いまだに世界と議論し続けているということですね。
こうしたダークなユーモアは自分が現実に対処するのを助けてくれますし、観客にとってもつながりを持つきっかけになると思っています。一聴すると軽くてユーモアに満ちていますが、聞き込むことで歌詞やビジュアルに隠された暗い意味に気づくでしょう。
「私たちは物理的に遠く離れているように見えるかもしれませんが、抑圧はすべてつながっています」
―2023年10月以降に発表される曲は“ITSAHELL!”“Stone”など直接的なメッセージのものが増えています。別のインタビューでは、現在のガザの状況を見て「音楽を作っている場合なのか、という葛藤がある」と語っていました。
バッシャール:この1年間にリリースした曲の多くはジェノサイドがはじまる前に書いたものですが、リリースしたのはジェノサイドがはじまってからです。比べてみると、以前の作品よりもずっと暗いトーンで、直接的な言葉を使っていることがわかるでしょう。
今はユーモアを保つのが難しいと感じています。こんなふうに人を踊らせていていいんだろうか? と罪悪感を感じたり、ショーで歌わない曲があったりします。
私たちには皆、喜びを感じて、わずかな時間でも現実から逃れる権利があります。だけど同時に、ガザの人々は今、現実から逃れられない状況にいることも考えます。とても葛藤しています。
未来の夢や希望について、考え続けたいと思っています。ただ、今は直接的に訴えていく表現が求められていると感じています。メタファーや曖昧な表現に隠れるのではなく、はっきりと言う必要がある時期なのだと思います。なぜならジェノサイドを止める方法を見つけ、この悲惨な状況を終わらせなくてはならないからです。
―最後に、音楽をはじめ文化にできること、日本の人々がすべきことはなんだと思いますか。
バッシャール:自分の声を使い、プラットフォームを活用して発信することです。私たちは物理的に遠く離れているように見えるかもしれませんが、抑圧はすべてつながっています。この闘争は決して無関係ではありません。特にアーティストや文化に携わる人たちは自分がどのように加担してしまっているかを認識し、それを避けるべきです。
最近、日本の年金の一部がガザのジェノサイドに関与しているイスラエルの武器製造会社のエルビット・システムズに投資されていることを知りました。日本で生活していることで虐殺に加担してしまう状況を知り、抗議して変化のために行動する必要があります。
日本の年金による、虐殺に加担する国家や企業への投資をやめるよう厚生労働省などに求める署名。Change.org「日本の年金による虐殺と民族浄化への投資をやめさせたい!」
また、パレスチナとつながりを作ることも大切だと思います。たとえば、コミュニティに参加したり、友達を作ったり。存在を身近に感じて直接話を聞くことで理解が深まりますし、共感が生まれます。そうすればきっと、政治的に何もしないことはできなくなるはずです。
アーティストには、「政治的な発言はキャリアに悪影響を与えるかもしれない」というプレッシャーがあるのは理解しています。でも、考えてみてください。もし自分たちが同じ状況に置かれたとしたら、世界に何を望みますか。「私は政治的ではない」という態度でしょうか。殺される恐怖とトラウマを抱えている状況への共感的な行動でしょうか。
日本で暮らす人々が享受している自由、平和、安全。同じように生きる権利が、パレスチナの人々にもあります。
Styling : Bunta Shimizu
Shirt : sat
Pants : Watanabe Miku
Accessories : BLACK TRIANGLE DESIGN
Special Thanks : 見た目!
Sabreen / ‘على فين’ (Ala Fein) 『何処へ』日本版CD
発売日:2002年02月03日
価格:2500円
10曲入り(日本語解説・訳詞付き)
Produced by Sabreen Jerusalem September, 2000
Manufactured by ACT・AIN
Distributed by Meta Company
Bashar招聘時にご縁があり、Basharの父Saidが’80年に結成し、第一次インティファーダの時代に興隆したバンドSabreenが2000年に発表したアルバム ‘على فين’ (Ala Fein) 『何処へ』の日本語版CD(日本語解説・訳詞付き)の希少在庫を引き受け、WAIFUで販売させて頂くことに。伝統的なアラブ楽器を使用したアコースティックなアンサンブルを基調としながらも、ロックやジャズ、様々な世界のモダンな音楽要素を取り込み独自のスタイルを確立した、パレスチナのオルタナティブ音楽シーンのパイオニアであるSabreen。
経費を除いた収益は全額、現在はバンドからNGOになりパレスチナのアーティストを支援し子ども達へワークショップを行うなど地域の文化活動の礎となるSabreenへ運営費として寄付します。
リリース情報
Bashar Murad x WAIFUコラボレーショングッズ
・ロングスリーブTシャツ(ブラック/ホワイト2色展開)7700円
・トートバッグ(レッド/グリーン2色展開)3750円
Bashar Murad初来日公演 at WAIFUを記念して販売されたBashar Murad x WAIFUのスペシャルコラボグッズが、お問い合わせ多数につきオンラインストアでも発売開始。
Basharの曲「ITSAHELL!」の歌詞、どんな人でも自由になりたい自分でいられるユートピア的ヴィジョン、それがパレスチナ解放だということを歌った部分が、属性を問わずセーファースペースづくりを参加者とともに目指すWAIFUのポリシーとも親和性が高く、フロント/バックともにプリント。アラビア語の歌詞は今回のコラボのためにBasharが特別に翻訳したもの。Tシャツ右腕にはアラビア語でBashar Muradとプリント。デザインはWAIFUのロゴやイラストでもお馴染みのsuper-KIKI。エコや労働環境にも配慮されたボディを使用。売上の一部はガザの医療従事者へ寄付されます。
グッズ情報
me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら
*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。