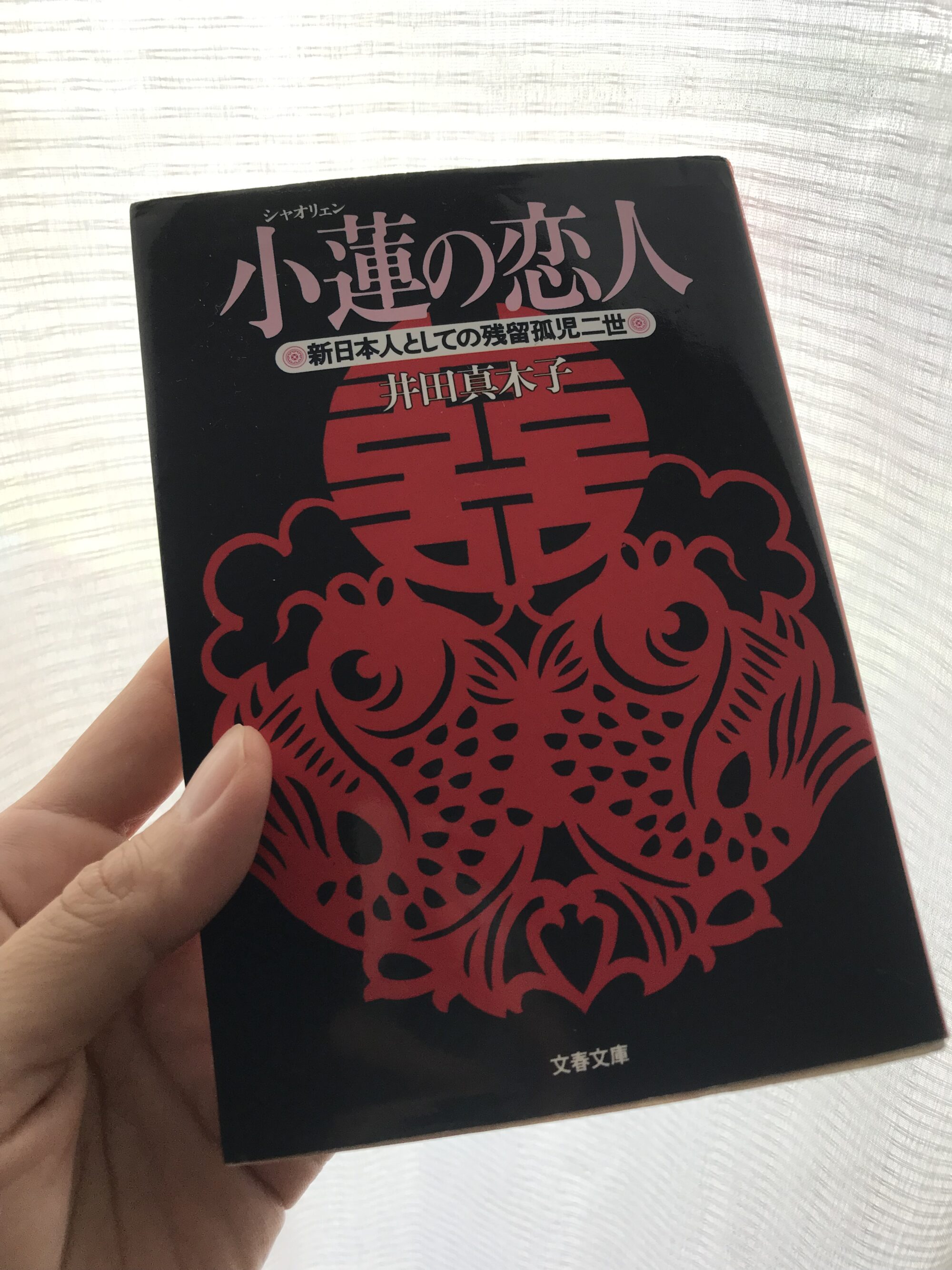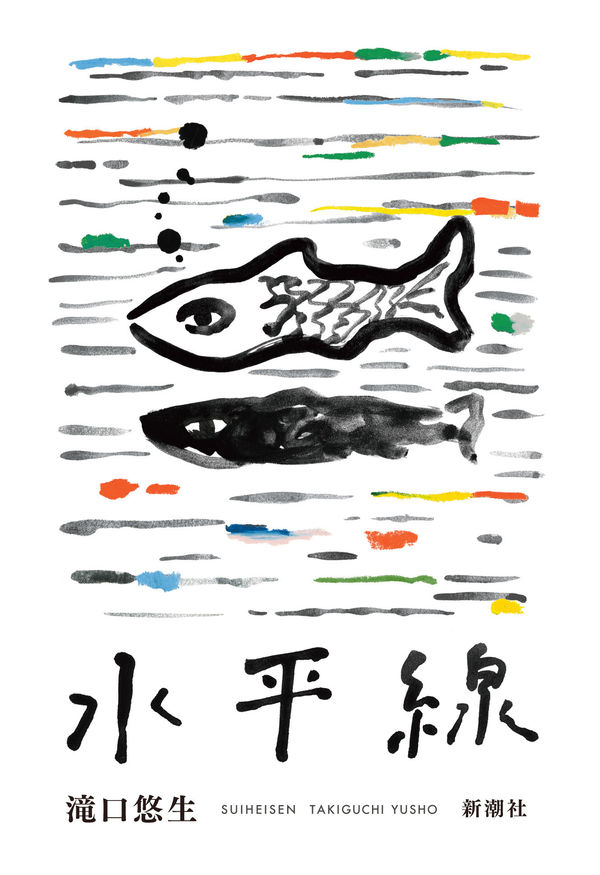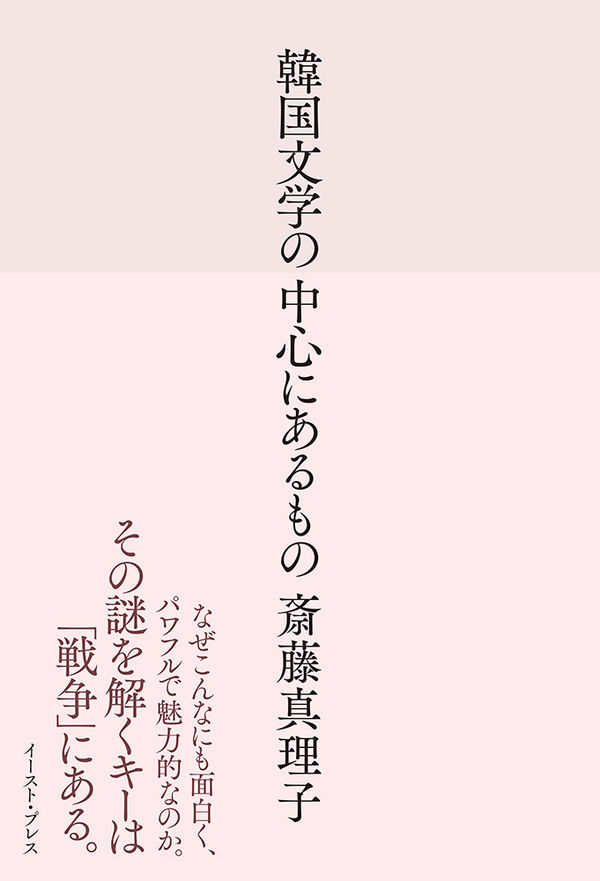斎藤真理子×中村佑子 煌々とした蛍光灯では照らせない声に耳を傾ける
韓国文学翻訳者と、社会からかき消されそうな存在の声を聞く作家
2023/8/4
「話を聞く」ことは、日常のそこかしこにあるありふれた行為ですが、「聞かれていない」という思いが心を翳らせることがあります。そう考えると「聞く」を見つめなおすことが、人の想いや存在がそこに「在る」ことを肯定する行為にもつながるのかもしれません。
今回は、「聞く」という行為をめぐって、翻訳者・ライターの斎藤真理子さんと、映像作家・作家の中村佑子さんをお迎えして話を聞きました。斎藤さんは、日本におけるいまの韓国文学の盛り上がりを翻訳を通して支えてきた立役者でもあり、朝鮮の歴史を丹念に追いながら、隣の国の声を日本に届けてきました。中村さんは、母や病をテーマにしながら、眩しい光のもとではかき消されそうな声や存在にまなざしを向け創作をおこなっています。
文学や映像の分野で活動をしながら、ともに子どもを育ててきた/育てている二人は「聞くことは難しい」と声を揃えます。それでも同時に、他者の声に耳を閉ざさずに生きていくことには、可能性があるとも話します。聞き書き、ケアと回復、韓国文学の奥行き、死者の存在、安心して話せる場所づくり、そしてバスや喫茶店で人の話を聞くこと……などのトピックに話の翼を広げながら、聞くことと生きることの関係についてたっぷりお届けします。お二人がおすすめする本もたくさん登場しますので、あわせて読んでみてくださいね。
―お二人は、お会いするのが初めてなんですね。
斎藤・中村:そうなんですよ。
中村:斎藤さんが訳された韓国文学作品を読んで、なんて素敵な日本語なんだろうと思っていました。だから、自分が『すばる』で『マザリング 現代の母なる場所』(著:中村佑子、発行:集英社/2020年)の連載を終えたときに、斎藤さんが「連載を読んでたけど本になるのかな」とつぶやいてくださったのが嬉しくて。編み物をしながら読んでくださったとツイートにありました。
斎藤:そうですね、それが最初の接点で。2019年の末でした。年が明けたら世の中がコロナになってね。
中村:そうでしたね。斎藤さんが連載されている『水牛』の「編み狂う」も楽しみに読んでいました。
斎藤:ありがとうございます。編み物が好きだから人の服を見るのも好きで、じろじろ見てしまうんですよ。やめてくださいって言われるんだけど……(笑)。
中村:(笑)。訳した本を送っていただいたり、DMのやりとりを重ねたり。ハン・ガンの『引き出しに夕方をしまっておいた』(著:ハン・ガン、訳:きむふな、斎藤真理子、発行:クオン/2022年)も大切に読ませていただきました。わたしには小さい子どもが二人いるのですが、韓国文学を読む時間が、自分を取り戻す時間になっているところがあります。
斎藤:中村さんとは会うのは初めてなのですが、言葉はたくさんやりとりしてきたんですよね。
「聞くというのは、自分の足で話を聞きに来たことの責任をとることだとも思っている」(中村)
―斎藤さんは、韓国文学の翻訳を通して大文字の歴史からこぼれ落ちてしまう声を聞き、届けていらっしゃると思います。一方中村さんは、精神病棟で過ごす女性や、出産前後の母という存在など、社会的/政治的な役割から時にはじきだされる場所にいる人たちの声を聞き、表現されていて。お二人の「聞く」行為は、消えそうなものや、埋もれてしまいそうなものを「ある」ことにされているように感じます。
斎藤:中村さんの文章を読んでいると、「どうしたらこんなふうに聞けるんだろう?」って思いますよ。
中村:ありがとうございます。ただ、自信はないんです。今日も井田真木子さんの『小蓮の恋人 新日本人としての残留孤児二世』を読んで自信を喪失してからここに来ました。井田真木子さんの文章を読んでいると、一見、井田さんの「私」はあまり登場しないのですが、相手の話を聞いている背後で、心をふるわせて、その人の感情そのものまで感じ取っている井田さんを感じるんです。
読んだ当時は「聞き書き」を読んでいるという感覚はありませんでしたが、あらためて「聞き書き」という形式を考えると、自分は井田真木子さんから読み始めたんだと思えます。大学も、専攻も、一緒だったことをあとから知りました。そういう偶然も嬉しかったですね。すごくかっこよくて、憧れていて。
斎藤:井田さんはすごいですよね。本当に特別だと感じます。
中村:井田さんは、女子プロレスラーの神取しのぶや長与千種たちの話を聞いた『プロレス少女伝説』で世に売って出ますが、彼女たちとの距離感も、本当にすごいと思わされます。対象者とかなり近いところにいるんですが、話を聞かせてくれた相手が抱える悔しさや悲しさを井田さんも共に感じて、バネにして、相手にも力を与えて、一緒に立ち上がろうとする感じさえある。
関係性あってこその聞き取りだと思うので、相手の方を理解しようとする姿勢、勉強や努力、何度も通って時間を惜しまないこと……その姿勢にも憧れていました。
斎藤:たしかに井田さんの特別さというのは距離感によるものなのかもしれませんね。中村さんが書かれた『精神看護』のエッセイは、それに近い気がしましたよ。
中村:えっ、嬉しい。それは本当に嬉しいです。わたしは、精神科病院に長期入院せざるを得ない女性たちに対して、自分も彼女だったかもしれないという思いがあるんです。一時的に家族の付き添いで、精神科病院に寝泊りしていた日々があって。そのとき感じたのは、自分はいま外の世界に好きに出られるけれど、彼女たちも本当はそうできるかもしれないのに、できない状態にある。世界の精神科病床の5分の1が日本にあると言われていて、そこまで病態がひどくなくても、長期入院している方も多いんです。彼女たちは、心の奥底に諦めや、悲しみ、怒り、さまざまな感情を飲み込み、そこにいると感じたんです。彼女たちの代わりにわたしが何倍も怒ったり悲しんだりしながら、なんとかしたい。その気持ちで書いていました。いまその続きを書いていて、医学書院のケアをひらくシリーズから、ヤングケアラーの本として刊行予定です。
テレビドキュメンタリーの世界からキャリアを始めたのですが、そこではなるべく自分というものを消して相手の言葉を中立的に聞くという客観性や公立性が求められることが多い。だけど聞くというのは、自分の足で話を聞きに来たことの責任をとることだとも思っているんです。だから「私は」という主語は消せない。それは井田さんのように自分もやりたいという思いからきているのかもしれません。
「(『聞き書き』には)当事者性に近い無垢なものというイメージがあった」(斎藤)
斎藤:1980年代は、聞き書きの本がたくさん出ていて、わたしはそこから読み始めた記憶があります。自分としては藤本和子さん(翻訳家、随筆家。リチャード・ブローティガンなどの翻訳を行うほか、『塩を食う女たち 聞書・北米の黒人女性』などの聞き書きの作品も発表している)が大きな存在でしたね。もともと聞き書きという形式に信頼性を寄せていた理由は、そのころにはなかった言葉ですが、「当事者性」にすごく惹かれていたからかもしれません。だから、フィクションであれノンフィクションであれ、書き手の意思しか見えないものには不信感があって、せめて書き手と語り手の間にあるものを見たいという気持ちがあったと思うんです。
大学生の頃の自分はすごく偏った考え方をしていて、あらゆるマスコミはよくないと思っていたので……(苦笑)。だって当時のことを振り返ると、先輩たちの間で、新聞のことを「ブルシン」って呼ぶ言い方が残ってて。
中村:ブルシン?
斎藤:ブルジョワ新聞、ですね。最初からブルジョワのための新聞だから、「本当のこと」が書かれているわけがないと。全共闘時代まではよく使われた言葉だと思います。
中村:それは、いまよりメディアリテラシーを感じますね。
斎藤:それをメディアリテラシーっていうのが当たってるかどうかは微妙な気がしますが……、とにかくそういう言葉がまだ片隅で生きていたんですよね。いまの「マスゴミ」という言葉よりさらに運動目線だったとは思いますが。
とにかく、そんなこともあってわたしは、活字になったもの全般に対して保留をつけて眺めていたところがありました。そのなかで、聞き書きは、より当事者性に近い無垢なものというイメージがあったんじゃないかと感じます。
―書き手の視点が権威的ではないことに加えて、聞き書きには複数の声が流れ込むという特徴もある気がしたのですが、そこはいかがでしょう?
斎藤:知識があって初めて視点が生まれるというのはよくあることだと思うのですが、当時のわたしはポリフォニック(多層的、重層的)という言葉は知らなかったんです。ナラティブという言葉も、まだあまり日本には入ってきていませんでした。複数の声があるという側面よりは、すごく泥臭い「聞き書き」という言葉に対して、そこに「本物」があるのではないかという気持ちが大きかった。歪められてない肉声がそこにあるのではないかと思っていたんです。
「親としては、忍耐がなくて話を聞けなくて、申し訳なかったと思うことがたくさんあります」(斎藤)
中村:斎藤さんの日本語訳からは、斎藤さんの身体というか、存在を通してハングルが聞こえてくる感覚があります。そこについて聞いてみたくて。たとえば、パク・ソルメの『もう死んでいる十二人の女たちと』の「冬のまなざし」なかで「問いの前でよろめく」と訳されていた一文の言語感覚がすごく印象的でした。
斎藤:「よろめく」は、「ピトゥルコリダ」という動詞で、辞書でも「ふらふら歩く、よろける」みたいな意味なので、本当に辞書通りの訳ですよ。ちょっと擬音語に近い感じですけどね。
翻訳者の皆さんに聞くと英語の場合、翻訳の文体をつくるにあたって、どういう人のどういう語りにするか、つまりどういう声にするかを決めることが第一段階ですよね。たとえば文体のベースを「です・ます」にするか「だ・である」にするか。その点、韓国語は日本語と文法が似てるので、英語の翻訳よりも「ボイス」をつくらないというか、つくらなくて済むんですよ。
―ボイスというのは、その人がどういう人か、みたいなことでしょうか?
斎藤:「らしさ」というか、個性、色のようなものでしょうか。韓国語には、日本語と同じく、「だ・である」調と「です・ます」調があるんです。また、その中間の、ちょっとやわらかい「です・ます」調もあります。語りの硬さと柔らかさの基準が日本語とよく似ているわけです。ですから、原文が「だ・である」調なら、わざわざそれを「です・ます」にする理由もありません。ですから、あまり翻訳者のボイスは出ていないと思うんですよね。もちろん、似ているからこそ微妙な差異をどう伝えるかが悩ましいわけですけど。
中村:とはいえ、訳す方によって、読むことを通して流れてくる印象は異なる気もします。
斎藤:そうですね……。たとえばハン・ガンさんであれば、ハン・ガンさん自身の個性が強いんです。本当に、痛みを書くのがうまい人です。ちょうどいま、ハン・ガンさんの新しい本を訳していますが、ものすごく痛そうな話ばかりで……。アタタタタ……という感じで、訳しているほど。そんなふうにハン・ガンさん自身の声がはっきりしているところもあると思いますね。
斎藤:ただ、聞くことは、本当に難しいですよね。わたしは翻訳の前に編集者として仕事をしていたのですが、ものすごく取材が下手で(笑)。人の話を聞けないんです。聞けなさにもいろいろあるけれど、自分がしゃべってしまって相手の話を聞けない人っているでしょう。わたしも初めの頃はそうだったなと思うんですね。
そこに気づいて抑制するようになったのですが、今度は制限時間が気になって、「記事にまとめるにはここを聞かないといけない」という焦りから無心に耳を傾けることができなかった。相手が話したいように話していただいて、それを聞くことに関しては、いつも目標値の20%もできていない感覚でしたね。どんなインタビューもなにも聞けなかったと焦っては、録音を聞き直して「やっぱりなんて聞けていないんだ」と思うことの繰り返し。
中村:取材をしたときのテープを聞くのって苦しいですよね。自分のできなさしか見えてこなくて。
斎藤:本当に。親として考えてみたとき、忍耐がなくて話を聞けなくて、申し訳なかったと思うことがたくさんあります。子育てしているときに、子ども関係の雑誌に仕事でかかわっていたことがあるのですが、不登校の子どもの支援をしている団体の代表の方が「親が聞きたいことを聞くんじゃなくて、子どもが話したいように話してもらい、それにとことん耳を傾けることが大事」と教えてくれて、全然できていません、と思っていました(苦笑)。
子どもはアニメや趣味の話を1時間も2時間も話すけれど、親からするとそれを聞きたいわけではない。だけど、子どもは本当はアニメに寄せて自分自身のことを話しているんですよね。そこに親は気づかないから、いつになったら本題が始まるのかな? って内心思いながら、聞いているようで実はなにも聞いていない。そういうことを繰り返していました。
中村:ああ……。
斎藤:だけど2〜3回ぐらいかな。どうしようもなく聞かなければいけないときがあって。子どもがいろいろ悩んで苦しんでいて、だけどわたしは明日の朝仕事に行かなければならない。時間は夜中の2時で、子どもは語り始めたら止まらないけれど、ずっと話し続けているわけでもなく、ぽつりぽつり話して、10分黙ってまた話す、みたいな。もう覚悟を決めるしかないなと思って。
中村:その2〜3回のタイミングというのは、子どもが少し大きくなってからですか。うちは下の子が1歳半、上が小1で、言葉で表現できることはまだ限られているので、覚悟の瞬間は訪れていないような気がします。妙に荒れているな、などはありますが……。
斎藤:そうですね。高校生の頃でした。いままでのわたしの聞き方は全部だめだったなあと思うような、ここでこの話を途中で切っちゃったら、この人との関係は切れるな、と思うような時間だったと思います。そういう「のっぴきならない聞き方」というのが子どもに対しても、仕事に対してもあった時期で、そのときは苦しかったですね。聞く人間として全然だめだと思っていました。
それに比べると、翻訳というのは作家が書いたことをただ聞いてればよい、というところもあります。だから、こんなハッピーなことはないとも思う。翻訳ならば「今日はここまで聞いて寝てしまおう」と決めても、誰も泣いたり怒ったりしない。
「自分と他者のお互いの殻が溶け合う瞬間を、欲望に近いレベルで求めている」(中村)
中村:最近、気づいたことがあって。わたしは、人間が自分ひとりの殻に閉じこめられ、孤独な存在であることから逃げられないからこそ、自分と他人の境界が溶け合う「自他未分」の状態に、本来ならずっと身を置きたいと思っているみたいなんです。
―というと?
中村:わたしは子どものころから、精神的に不安定で寝こみがちな母をケアしてきた、いまの定義で言うと、いわゆるヤングケアラーだったのですが、子どもながらに母の苦しみを取ってあげたい気持ちと、自分が苦しみから解放されたい気持ちが両方ありました。ケアの気持ちと欲望が混じり合っているんですよね。自分がかかわってきた、ケア、看病、そして聞くこと、子どもと向き合うこと……いずれにも、「自他未分」の感覚があって。「自分と他人」「自分と胎児」「子どもと大人」……そういった自分と他者のお互いの殻が溶け合う瞬間を、欲望に近いレベルで求めていて、溶け合った瞬間にある種の快楽さえ覚えているんだな、と。『マザリング』を書いているときには、その愉悦の感覚までは、はっきりと気づかなかった!
斎藤:たしかにさっき話した、子どもの話をのっぴきならないようなやり方で聞かなければならなかったときは、最終的にはどちらが話して聞いているのかよくわからなくなるぐらい空気が濃密になっていました。いつも住んでいる部屋がちょっと別の空間になるような。
子どもには苦しみから早く楽になってほしいけれど、自分も楽になりたい……というように、「してあげたい」と「してほしい」が一体化するんですよね。どちらも親のエゴだけど、その願いは双方向に作用して初めて叶うものでもあって。誰の欲望かもうわからなくなるって、めったにないけれど、あることですよね。
谷口(河出書房新社/中村佑子さんの連載『午前3時のソリチュード』の編集担当):興味深いですね。だけど同時に、中村さんのなかには、自我をもったひとりの人間でありたいという欲望がありますよね。
中村:たしかに、me and youで連載している『午前3時のソリチュード』はそういう連載ですもんね(笑)。たしかに、必死になって自分を取り戻そうとしているところもあります。
谷口:自我をもったひとりの大人としての個体でありたい気持ちと、自他未分でありたい欲望が共存してるってものすごいことじゃないですか?
斎藤:欲張りなんじゃない?
中村:そうかもしれません、欲張りかもしれません。
一同:(笑)。
斎藤:基本的に、中村さんはものすごくエネルギーがあると思いますよ。わたしは子どもが小さいときに本は読めませんでした。毎日食べていくための仕事を回すのと、子どもをみるのでキャパオーバー。文化的なことは十何年もできなくて。
中村:翻訳を精力的にやられるようになったのは息子さんが成人になってからですか?
斎藤:そうですね。わたしはケアと仕事のバランスをとることができなかったけれど、とれる人はいらっしゃるんですよね。
韓国文学に奥行きがある理由。イ・ランさんの母にまつわるエッセイから受け取った驚き
―癒しやケアというところから派生してお話しすると、斎藤さんが翻訳される韓国文学や、中村さんがつくるものには、苦しみの側に体重を乗せるところがあると思います。読んでいる側は、苦しいものを読んでいるはずなのに、自分がしまいこんでいた傷に向き合う機会にもなり、なぜか癒えていくようなところもあって。
中村:以前、『VOGUE』の書評(韓国文学を貫く“浩(ひろ)かさ”の正体を探る──ファン・ジョンウン著『ディディの傘』ほか 【VOGUE BOOK CLUB|中村佑子】)にも書いたのですが、韓国文学には自分を深く治癒してくれる特有のなにかがあるんです。そんなことを今日斎藤さんに訊いてみたいなと思っていました。
わたしにとって、夜中に韓国文学を読むことでしか癒えない大事な時間があるんです。なんというか、すごく言葉自体と、書かれていることの「間」の空間が大きいと感じるんです。登場人物の感情の流れだけでなく、韓国の方が書いているものには、より大きな川の流れがあるような気がします。大きな川の上に、いろいろな人がいる感じというか。
斎藤:わかります。ずーっと翻訳したり下訳をしたりしていると、韓国のものばかり読むのですが、しばらくして日本の文芸誌を読んだりすると、眼鏡を変えないと焦点が合わない、というような感じがあります。縮尺の違いというか。不思議なのは、日本以外の翻訳文学を読んでいるときにはそれをあまり感じなくて。
中村:わかります、わかります。
斎藤:韓国文学は、奥行きが広いですね。たとえば、『文藝』(2022年春季号)の「母の娘」特集のイ・ランさんのエッセイ(「母と娘たちの狂女の歴史」)は、「お母さんは私を、自分の感情を捨てるゴミ箱として使う」という文章から始まります。そして、どうしてお母さんがそうなってしまったのかを、イ・ランさんが直接お母さん本人にインタビューしていくのですが、その背景に朝鮮戦争が関係していたことがわかってきます。これにはもうびっくりしてしまって。
―奥行きというのは、時間軸の長さや、歴史を捉える視座がある、ということもあるでしょうか?
斎藤:多くの人が似たような体験をしているという前提があるので、奥行きも面積も広くなると思うんですよ。イ・ランさんのお母さんが経験したことって、朝鮮戦争で息子を亡くしたお父さんが、後継ぎがいないと家の存続が危ないからと無理なことをしたために、娘たちがすごく苦しんだというストーリーなんですよね。それは多分、イ・ランさんの家だけじゃなくていろんな家で起きたことじゃないかと思うんです。韓国人が読むと、「ああ、ここもか」って思うようなことかもしれなくて、共通体験の強さみたいなものがある。でも日本では、戦争に起因するいろんな困難が、個人の体験としてぶつ切りになっている気がします。
中村:そうかもしれません。朝鮮半島はまだ戦争が終わっておらず、戦間を生きていると、ファン・ジョンウンが書いていて、なるほどそうか、と思いました。戦前でも戦後でもなく、韓国はいまもまだ「戦間」を生きている、と。社会や歴史のヒリヒリとした否応なさに、いまもリアルに接続されている。
斎藤:イ・ランさんの家では、おじいさんが、二人の息子を北朝鮮に拉致されてしまったんですよね。後継ぎがいなくなった怒りと悲しみの傷はまだ癒えていない。その傷を癒すよりも先に、後継ぎ問題の解決のために家族を苦しめてしまった。それは歴史の罪だから、おじいさんひとりを責めても仕方がないという状況が普遍的にあって、みんなが共有している。その共有している土台が広いので、土台の底面積の分だけ広い塔が立つ。韓国文学を読んだときの奥行きと広さというのは、そういうことじゃないでしょうか。
「死者たちを含めた大きな流れのメンバーの一人として生きている実感を持ちたい」(中村)
中村:日本は、過去の傷をしまいこんでしまっているのでしょうか?
斎藤:しまいこんじゃってるんでしょうね。本当は、家族が体験した戦争の傷はそれぞれの人のなかにあるはずだと思います。たとえば朝鮮半島からの引き揚げ体験や故郷の喪失は多くの人に共通する傷だけれど、文学の世界においては朝鮮で生まれ育った作家の森崎和江さんが傑出したものを書いたので、朝鮮に対する贖罪意識は森崎和江ひとりがいればいい、みたいなことになってしまったところがある。
中村:そうですね。だから森崎和江さんの本を読んで初めて、「朝鮮に対する贖罪意識を日本人は持っていて、帰国してからもその贖罪意識とともに生きていたんだ。朝鮮戦争もその贖罪意識のなかで見守っていた」という事実を知ったし、朝鮮半島と日本との関係を自分の感情で背負いながら、生きて書いている人の作品を他に読んだことがなかったことに驚きました。
―『韓国文学の中心にあるもの』(著:斎藤真理子、発行:イースト・プレス/2022年)のなかで、斎藤さんは「歴史を知ることは未来のためになる」ということを書かれていました。短い時間軸で、現在の視座でしかものごとを考えられなくなってしまうと、この先すごく危険な気がしているんです。どうしたらわたしたち一人ひとりが長い時間軸でものごとを捉え、過去に生きた人たちの声に耳を傾けることができるでしょうか。
斎藤:変わりかけていると思うんですよ。そういうのって、揺り戻しがあると思うんですね。日本は経済が回ることに注力して、政治のことはさほど考えなくても社会が回ってきたと思うのですが、それは平和だったということ。わたしは城内平和が悪いとは思わなくて、幸運だったと思います。だけど、いまは政治のことを考えなければ立ち行かなくなっている。
小説の話だと、先日、戦争中の硫黄島を舞台にした滝口悠生さんの『水平線』を読んだんですけど、複数の声が独特に混じっていくような書き方で、その混じり方が、今まで読んだどんな日本の小説とも違っていて、すごく好きだった。あれは韓国文学にはないものだと思いました。うまく言えないんだけど、混じるほど透明になっていくような、すごく遠くまで聞こえる声だと思ったんです。まだ読んで間もなくて、言語化できないんですけど。
中村:『韓国文学の中心にあるもの』には知らなかったことがたくさん書いてあって勉強になりました。なかでも全国的に市街戦があって、戦線が半島全土でローラーのように何度も行き来する。そのたびに大量の死者が生まれ、朝鮮半島全体で300万人も亡くなったというのは、大変なことです。韓国では街や公共空間のなかに死者の存在や、目には見えない過去の風景が漂っているという感覚は、韓国文学のなかにいつも感じます。韓国文学に感じる射程の広さというのも、そのことと関係がある気がしています。
斎藤:どんな戦争でも死者の数を正確に知ることはできませんが、朝鮮戦争は特にそうだと思います。戦争が始まる前にも、始まってからも人が南北間で移動しているので、統計がとれないんですよね。それと、その後韓国では軍事独裁政権が長く続いたこともあって、口を塞がれた状態だったので、死者を充分に悼めなかったんですね。例えば、敵軍ではなく味方の軍隊による一般人の虐殺などについては語ることが禁止されたので、死んだ肉親のことを正直に言えなかったり、肉親が北(朝鮮)に行っていることに対して嘘をつかないといけなかったり。傷の記憶を正直に言えない時代が長かったことは、いまの社会における死者への態度に影響しているかもしれません。一方で、日本でも多くの人が亡くなったし、大変な目に遭ったけど、やっぱり終わったこととして語られているように思います。
中村:そうですよね。東京大空襲では現在の原宿にも死体が積み重なっていて、山の手大空襲のときは、表参道の石灯籠に死者が立てかけられていたという。沖縄をはじめとした土地では市街戦があって、日本人は沖縄の人々に大きな犠牲を強いたうえに今の社会を成り立たせた。先日の広島サミットを見ていても、あの平和記念公園は原爆の多大な犠牲者の上に築かれた場所です。そこでウクライナへの武器供与の採択を行うことに違和感を覚えました。あのときの死者が、このサミットを見たら何を思うだろうと。
わたしはこの世を去った人たちのことを見えないものにせず、ともに生きていきたいという思いが強いです。だから、韓国文学に流れる大きな川のようなものに治癒を覚えるのかもしれません。自分ひとりの世界や言葉の価値を発信するだけでなく、同時に権威に飲み込まれるのでもなく、死者たちを含めた大きな流れのメンバーの一人として生きている実感を持ちたいというか。それが、自分が韓国文学から受け取る癒えの感覚なのかもしれません。
「煌々とした蛍光灯の下に晒せることだけじゃない言語化できない暗闇が、それぞれのなかにたくさん沈んでるはず」(中村)
―斎藤さんや中村さんのつくるものや、聞き書きの作品などに触れるなかで、光の当たる人だけではなく、市井の一人ひとりの声を語り継ぐ行為が、未来のために本当に大事なのではないかと感じています。ではそれをどう一人ひとりがやっていくのかということをお二人に聞いてみたいなと思います。
中村:わたしは大学でシネエッセイ(映像で綴る日記やエッセイ)の授業を持っているのですが、自分の話をすることに罪悪感をもっている人が少なくないんです。だから「ここはアジール、聖域である」って伝えていて。就活に突入したり、行き過ぎた資本主義やネオリベ化が進む社会に出たりすると、自分の長所や、成果や有用性みたいな数値的に目に見えるものばかりが求められて、自分の弱い部分や個人史など、言語化しにくいものの行き場がなくなるし、とるにたらないものだと思われる。そのストッパーをとっぱらって私的な会話をしてもいいんだという場をつくると、皆すごく自然に話していくんです。この時間が、のちにきっと彼/彼女たちのお守りのようなものになるのではないかなと思っています。
斎藤:すごく大事なことだと思います。
中村:me and youやShe isにあがっている言葉たちもきっとそういうものですよね。もしかしたら独り言でもよかったかもしれないけれど、そばに誰かがいてくれて、そっと聞いてくれているというような。初めは呟きだったものが、誰かがいてくれるから、もう少し深く話ができた、というような。わたしはそういう聞き書きもありえると思っているし、いまの時代にすごく求められていると思います。
たとえばいま、性的マイノリティの人たちの声が聞かれるようになってきて、誰かがなにかの当事者である、という考えはすごく高まっていると思いますし、見えないことにされていたものに対して言葉が現れて、さまざまなグラデーションが存在することが見えるようになってきています。自分がどこかのメンバーのひとりだと思えるような時代になってきていると感じるから、そういう人たちが安心して話せる場が生まれていったらいいと思う。
斎藤:そう思います。やっぱり若い人のために場をつくるのはほんとに大事だと思うので。中村さんは相当やっていらっしゃいますよね。
中村:授業ではオープンダイアローグを採用してるんですけど、これが面白くて。統合失調症など精神疾患の急性期の患者さんの治療に使われる、フィンランドで採用された手法です。投薬と比べても、患者さんの状態が良くなると実効性も報告され、注目されています。この手法を知ったとき、コロナを経た今の大学生たちの自閉的な状態に採用できると思いました。一人が悩みをオープンにして、「リフレクティング」という特有の段階に入ると、他の人たちはその人のほうを見ずに、悩みをどう受け取ったか話し合うんです。それは、自分の話を真剣にテレビのなかで討論してくれているような感覚で、「側聞」や「善なる噂話」とも言われる対話の力です。それを何度か繰り返すことで、本人は自分の悩みや苦しさ、思考のもつれが腑に落ちたり、癒えていったりする。それで最後に作品をつくります。今年も切実でその人らしい、すばらしい作品が多数集まりました。
わたしはよくバスや喫茶店で見知らぬ人の会話を聞くのですが、本音を話している人は少ないと感じます。生きていくことには、労働人口のコマとして扱われる有用性からこぼれ落ちるような、簡単に解消できない暗い部分も汚い部分もたくさんあります。それをすべて、全部個人のなかで飲み込まなきゃいけないように、現代の社会ではなってしまっているのかなと。それがSNSのなかで悪い形で噴出したりして……。
だけど煌々とした蛍光灯の下に晒せることだけじゃない言語化できない暗闇が、それぞれのなかにたくさん沈んでるはずで。その領域が、自分にも他者にもあることを感じながら生きていきたいなと思います。
「他の生命と折り合いをつけて生きていくためにどうしたらいいか。答えはやっぱり『声』にあると思うんです」(斎藤)
中村:そういえば『文藝』(2021年冬季号)の「聞き書き、だからこそ」の対談で斎藤さんが紹介されていた堅田香緒里さんの『生きるためのフェミニズム パンとバラと反資本主義』を読んだんです。すごく面白かったです。路上生活者の人たちと過ごしたり、ベーシックインカムを推奨されたりしている堅田さんが「セーファースペース(Safer Space)」という概念を話していました。安心して話せる場所というのは、マジョリティのなかに一部分だけ安全圏をつくるのではなく、安心して過ごせる場をマジョリティ側に引き伸ばすような態度だというふうに受け取りました。誰もがより安心して過ごせる場を広げていく。
斎藤:そうですね。わたしは自分で選んでシングルマザーになって、自分の選択だから満足してたんですよ。でも、ばかみたいなんだけど、シングルマザーになると貧乏がデフォルトでついてくることをわかっていなかったなーと思います。本当はそのこと自体、あっちゃいけないことだと思うし、そうでなくなるべきですけどね。でも現実に、お金との闘いが一番大変でした。常にお金のことを考えていなければならないのはかなりストレス。でもまあ当時は、単純に言えば、頑張れば何とかなるという部分がまだまだあったのよ。でもいまの時代はその部分がすっかりすり減っちゃって、頑張ってもお金にならない。若い人たちはほんとにお金がなくて。だから若い人たちが、本を買ったりすることもなかなか難しいですよね。
中村:『生きるためのフェミニズム パンとバラと反資本主義』には、まさに社会運動における、お金の部分への視野の重要性が語られています。バラは文化的なもの、パンはお金。フェミニズムや思想的な運動は、どうしても文化のほうに傾きがちですが、パンが大事なんだと。ブルジョワの話だけにしてはいけない。貧しさの解消が絶対に外せなくて、そうしないと特権階級だけの話になってしまうから。
斎藤:本当にそうですね。質問にあったような「声」ということで言うと、話せる場所でなければ、話す意思は出てこないんですよね。いまはどこにいっても不安がいっぱいで、日本もどうなるか本当にわからない。だけど世界中、どこを見てもうまくいっていないとも思います。現状維持で安定走行できる地球や世界ではなくなっているんですよね。
そう思ったときに自分の身ひとつを、崩れていくかもしれない世界のなかで保つにはどうしたらいいか。他者がいることが苦痛だという自分ではなく、他の生命と折り合いをつけて生きていく自分になるためにどうしたらいいか。答えはやっぱり「声」にあると思うんです。活字で読む声だったり、街ゆく人の声だったり。わたしもよく人の話をこっそり聞いてるんですけど、面白いですよ。本音でものを言わない人ももちろんたくさんいるけれど、ふとしたときに言っていることもあって。それを聞いた記憶というのが、随分と頭に残ったりします。声に支えられるってことがある。だから自分のシャッターを閉めてしまわないで耳をオープンにしておくことが、免疫力を高める気がしています。
もちろん、いろんな声が入ってきちゃって嫌なこともいっぱいありますけどね。だけれどそれを解毒するものも人の声のなかにあるんじゃないかなと思います。こういう会話にも、文学作品にも、歌にもあるしね。やっぱり人間から面白さやおかしみがなくなることはないみたい。これまで生きていて、本当にそう思います。いろいろな局面でそれを見て、聞いて、なんとか自分を保っていきたいなあと思いますよね。
斎藤真理子
韓国語翻訳者。主な訳書にチョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』、ハン・ガン『すべての、白いものたちの』、チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』、ファン・ジョンウン『ディディの傘』、パク・ソルメ『未来散歩練習』など。2015年、パク・ミンギュ『カステラ』で第一回日本翻訳大賞受賞。著書に『韓国文学の中心にあるもの』。
(撮影:増永彩子)
中村佑子
1977年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒。(株)哲学書房にて編集者を経て、テレビマンユニオン参加。美術や建築、哲学を題材としながら、現実世界のもう一枚深い皮層に潜るようなナラティブのドキュメンタリーを多く手がける。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』、『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』(HOTDOCS正式招待作品)、テレビ演出作にWOWOW「はじまりの記憶 現代美術作家 杉本博司」(国際エミー賞・アート部門ファイナルノミニー)、NHK「幻の東京計画 首都にあり得た3つの夢」(2015年ギャラクシー奨励賞受賞)、NHK「建築は知っている ランドマークから見た戦後70年」等がある。シアターコモンズにて、スーザン・ソンタグ『アリス・イン・ベッド』リーディング演出、AR映画『サスペンデッド』脚本・演出。2020年、初の単著となる『マザリング 現代の母なる場所』を出版。立教大学映像身体学科兼任講師。
プロフィール
連載「午前3時のソリチュード/中村佑子」
早めに就寝して、真夜中にふと目覚める午前3時。映像作家の中村佑子さんにとってその時間は、日常の雑事や役割から解き放たれ、自分の中心と向き合う大切なひととき。そんな「午前3時」をテーマに、中村さんに日々のモノローグを綴っていただきます。母である属性を抱えながら生きる、ひとりの女性の折々の記録。
連載
『マザリング 現代の母なる場所』
著者:中村佑子
発行:集英社
発売日:2020年12月16日
価格:2,420円(税込)
『マザリング 現代の母なる場所』│集英社
『韓国文学の中心にあるもの』
著者:斎藤真理子
発行:イースト・プレス
発売日:2022年7月12日
価格:1,650円(税込)
『韓国文学の中心にあるもの』│イースト・プレス
書籍情報
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。