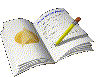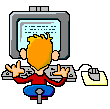映画『Lilypop』青石太郎×鈴木理利子。iPhoneで映し出す、関係性におけるラブとポップ
実在する美大生たちの関係性から着想を得て、照明も録音もないミニマムな体制で
2025/11/18
2025年11月22日(土)からシアター・イメージフォーラムで上映される映画『Lilypop』。この作品は、脚本・監督の青石太郎さんが授業をおこなう武蔵野美術大学で出会った実在する美大生の親密な関係性から着想されました。人と人とが時空間を共にすることの喜びと困難が描かれた物語を、当時学生だった本人たちが演じています。
美大で写真を専攻しているが最近は撮りたい被写体が見つからないりりかと、その同居人で、心の調子を崩して部屋にこもっているエナ。「ラブ&ポップ」とタイトルをつけた、りりかが昔撮ったエナの写真は授業のなかで評価されるけれど、今、二人が過ごす時間はばらばら。そんななか、りりかはエナの“分身”と出会い……。
キャストもスタッフも少人数。機材はiPhoneのみで、音声はアフレコ。小さなカメラが、複層的な関係性と、登場人物の心の機微を映し出しています。脚本・監督の青石太郎さんと、りりか役を演じた鈴木理利子さんに話を聞きました。
─まず、インディペンデントで作品を制作・発表していらっしゃる青石さんのこれまでの歩みを伺いたいです。
青石:インディペンデントな在り方は、選んだというより、結果的にそうなったというか。もともとは商業の作品から映画に興味を持ちました。中学生のときによく屯していた友達のおばあちゃんのお家があって、そこに泊まりに行って、みんなでレンタルビデオを観ていたのがきっかけです。窪塚洋介が出ている作品やホラー映画など比較的メジャーな作品を観ていて、多分、その集団のなかでもとりわけ僕が映画に興味を持っていました。
その後、高校生のときに将来どうやって生きていこうかと考えたときに映画をやってみようと思い、自由な雰囲気だった武蔵野美術大学の映像学科に進学しました。
─現在のようなミニマムな体制で映画を撮るまでには、どんな経緯があったのでしょうか。
青石:大学とは別で、何度か規模の大きい作品の制作現場に手伝いに行ったことがあったのですが、楽しいこともあればひどい目に遭うこともあり、映画制作をどう成立させればいいのか考えさせられました。当時から映画の制作環境を考えようという動きもあって、商業映画の体制を真似するのではなく、小さなコミュニティでプロセスを考えながら作ろうとするなかで、インディペンデントな在り方になったという経緯があります。
─大規模な作品の制作環境において、青石さんが疑問を持ったのはどのような部分だったのでしょうか。
青石:僕は一つの作品に関わる全員がお互いを認識していなきゃいけないと思っています。でも、参加した作品では、監督がその日に来るお手伝いのスタッフのことを知らないのも普通でした。全体の人数が多く、スケジュールや役割に縛られていて、基本的なコミュニケーションも生まれにくいんですよね。
─制作環境のプロセスを考えながら映画を作るにあたって、どのようなことを大切にしていますか。
青石:今、自分のなかで定着しつつある一つの映画制作の体制は、被写体の他には小さなカメラしかないという環境です。照明・録音はなく、撮られる状況と撮るもの(カメラ)だけがある状態です。僕は記録映像やホームビデオが好きで、脚本も演出も照明も録音もないなかで撮られた映像にも、強く心が動かされることがあります。
映像は複製可能ですが、撮られる世界は常に唯一です。僕は映画において、視覚的な美意識よりも、撮られた時間への直接的な感動を大切にしたいと思っています。その記録としての機能に映画の価値を託すために、こうしたミニマムな体制をとっているのだと思います。
他人と一緒にいることに利益を求めない、三人の美大生の仲の良さや楽しみ方に救われた
─『Lilypop』は、青石さんが授業を行う武蔵野美術大学で出会った鈴木理利子さんたち美大生から着想を得て制作されました。彼女らからどのような着想を得たのですか。
青石:『Lilypop』に出てくる三人はもともと仲良しで、僕は、講師をしている実習の授業で三人に出会いました。その授業では映画を撮るので機材も使うんですけど、機材の使い方は説明書を読めばわかることでもあるので、どちらかというと明文化できないところ、グループワークの関係性やコミュニケーションにおいて問題があったら一緒に考えるというのが僕の立場でした。
その後、僕が映画を撮るときに、三人はほぼ毎回の撮影に欠かさず手伝いに来てくれて。映画を手伝いたいというより、その三人でいるのが楽しいから来ているという雰囲気だったんですよね。僕は、映画制作に関わる時間自体に楽しさやなにかしらの価値を感じてほしいと思っているから、三人の仲の良さや楽しみ方に救われました。頼む仕事があるか微妙で呼んで良いのか迷うときもあったんですけど、それでも三人はそこにいること自体にストレスがなさそうでした。
他人と一緒にいることにおいて利益を求めない、損得勘定しないのがいいなと思って、その正体みたいなものを映したいと思ったのが最初の着想かな。
─青石さんと鈴木さんは、一般的には、講師と生徒、監督と出演者という関係性です。縦の関係になりがちななかで、どのようにコミュニケーションしてきましたか。
青石:特殊なことはなにもしていないと思います。ただ、聞かれたくなさそうなことは聞かないとか、人として普段から気をつけていることにより慎重にはなりました。脚本を書いて演出をするなかで監督という決定権を持つ人間として振る舞わざるを得ないので、どうしても縦の関係にはなってしまいます。でも、なるべく許容範囲を広げることで縦の関係が固定化しないように心がけました。
大規模なチームの撮影現場では、意味や意義がわからなくても、「立場が上の人に言われたから」「流れができているから」と、疑問を感じつつもやらざるを得ない仕事が発生することがあると思います。僕自身、強制的なことにはかなり抵抗感があり、そのようなことが一切ない場が理想ではあります。
─違和感を共有することや立ち止まって考えること、トップダウンでない在り方は、映画制作以外においても大切なことだと思いますが、成立させる難しさもあると感じます。
青石:そうですね。その分、たとえば誰かが「今日は調子が悪くて撮影できない」となっても許容できるようにしておかないと成立させられない危うさもあります。実際に『Lilypop』の撮影時もそういうことがありました。でも「調子が悪いけど行かないと大変なことになる」みたいなプレッシャーがかかった状態で進めたくないので、脚本の内容に応じて余白の時間を多めに作り、失敗を含むいろいろな場合を許容できる状況を作りました。
イメージ通りでなくても「OK」と言えるよう、そもそもOKと言えるであろう人にお願いしているんですけど、最終的には被写体を信頼するしかないところまで内容共有などの準備をすることが大事でした。それでも不測の事態は起きますから、柔軟に対応可能な規模・スケジュールにして、それらに理解のあるメンバーで制作するしかないのです。
「自分のスタイルを貫いて作り続けている青石さんを見て、モチベーションにしていた」(鈴木)
─『Lilypop』の撮影時は、鈴木さんにとってどんなタイミングだったのでしょうか。
鈴木:『Lilypop』を撮影した2021年はコロナ禍でしたが、映像制作の実習はあって、対面での撮影が再開していた頃でした。私は当時、大学近くの『Lilypop』の撮影場所にもなった家に住んでいて、常に映画のことを考えながら生活していましたね。自分の作品を撮影して、友達の撮影を手伝って、いつも誰かの撮影がある生活の延長線上で『Lilypop』の撮影が始まりました。
青石:いろいろな撮影が終わるのを待って『Lilypop』の撮影を始めたんだけど、理利子が疲れてて『Lilypop』の撮影初日に来なかったんだよね。それまで連絡がつかないことはなかったから、すごく心配して何度も電話してしまった。「できないかも」と思ったけど、会ったら元気そうだった。
鈴木:その頃は本当に疲弊してました(笑)。でも『Lilypop』はやりたかった。
大学2年のとき、最初のドラマ制作の実習が青石さん担当で、そのときにちょうど『Lilypop』に出ている三人が同じ班だったんです。その頃の私は、映画撮影の当たり前の文法を知らないまま制作をしていました。他の班の人たちが撮影しているのを見て、初めて「映画ってこうやって撮ってるんだ」と気づいたくらい。一つのシーンのなかで細かいカット割をする概念がなかったので、すべてのシーンをほぼ定点で撮影しました。長回しなので編集のときにカットしようにもできず、規定の尺が5分だったんですけど、結果的に12分の作品になってしまいました。でも青石さんは講師という立場でありながら、無理にカットしなくていいと言ってくれて(笑)。
ただ、文法は知らなかったものの、中学生の頃から映像作品を作っていたので撮ることには慣れていて、撮りたいもののヴィジョンもあって。記録映像のようにその場のすべてを記録するような制作方法をやや意識していて、それに対して青石さんが共感してくれた感じがありました。高校まで美術と関係のない学校に通っていたのもあって、初めて自分が作ったものに対して共感してくれる上の世代の人に出会えたから、すごく嬉しかったです。結局、その定点長回しのスタイルは卒業制作の短編映画『Episodic memory』の撮影時まで変わらないものとなりました。
─小さなコミュニティでプロセスを大事にしながら作るという点も共通しているのでしょうか。
鈴木:私も撮影にiPhoneを使ったり、自分の作品をちゃんと把握してくれる最低限のスタッフでの撮影を心掛けたりしていたのですが、特に大学時代は、ミニマムな制作スタイルだと時に軽いものとして作品を見られてしまう感覚がありました。そんなときに、自分のスタイルを貫いて作り続けている青石さんを見て、モチベーションにしていた部分もあります。
─青石さんは、鈴木さんの作品をどう見ていたのですか?
青石:理利子の作品には理利子自身の人との過ごし方が表れている感じがして、目的とか利益とかがない、ただの時間みたいなものを作品にしているところがいいなと思っていました。
鈴木:ドラマ制作の実習で撮ったのは、私ともう一人の女の子が二人で部屋で座って喋る映像だったんですけど、その距離が異様に近いと青石さんに言われたのを憶えています。
開かれた「ポップ」と閉鎖的な「ラブ」を映画のなかで出合わせられたら
─『Lilypop』は、鈴木さんをはじめとする出演者たちの実際の関係性や実生活、制作物をもとにしながら、ドキュメンタリーではなく劇映画として制作されました。
青石:脚本を書き始めてから撮影するまで半年から1年くらい期間があったんですけど、脚本を書いたときは三人の仲良しの側面しか見てなくて、その仲の良さが試されるような物語にしていました。ただ、撮影までの間に脚本に書いたようなことが実際に起きて、脚本と現実がだいぶ近づいてしまったから、そのまま撮るのもまた違うと思い、脚本を修正しました。……でも、撮影してから時間が経ってるからな。理利子から見て違ったら教えてほしい。
鈴木:私もあんまり憶えてないけど、青石さんからもらった脚本が現実と重なる部分があっても、自分としてはフィクションだと思って読んでました。
─この映画では、さまざまな形の人間関係が描かれているなかで、ラブとポップについて何度か言及されています。タイトルにもある「ポップ」については、お二人はどのようなことを考えてきましたか。
鈴木:高校生の頃から庵野秀明監督の『ラブ&ポップ』が好きで、自分の名前と「ポップ」を混ぜた「lilypop」をSNSのユーザー名にしていました。でも私は高校生までは全然ポップなキャラクターじゃなくて、予備校でも、喋らないクールなキャラだと思われてて。大学に入って「lilypop」から「リリポ」って呼ばれるようになって、本名とは別のあだ名がついたことから自分の感じが結構変わった気がします。
青石:確かに、ポップは開かれているイメージがある。「ポップスター」とか言ったり、誰にでも広く愛されるというか、ラブはもうちょっと個人と個人の閉鎖的な関係のなかにあることが多い気がして、それが必ずしも悪いわけじゃないけど、排他的で、全員と共有するものではない側面もあるな、とか。だから、ラブとポップの両立には結構厳しさがあると思います。
─ここでのポップというのは、関係性の軽やかさというか、そういったイメージでしょうか。
青石:そうですね。もともと、自分の周りにはあまりポップな関係性がなかったから憧れみたいなものがあって、理利子たちが三人で過ごしているのが羨ましいというか、混ざりたいとまではないけど、知りたいという気持ちがありました。逆に自分は、ラブの仕様もない側面をよく知っていると思うから、そんなラブとポップを映画のなかで出合わせられたら新しいなにかが生まれるかな、という意識で脚本を書いたり、被写体を見たりしていました。
─ラブとポップの両立しにくさ、ラブの仕様もなさはどのようなところに感じますか?
青石:性愛的欲望や相手を独占したいといった暴力的な感情を伴うところでしょうか。これまで自分はラブストーリーのなかで、そういうのっぴきならないごちゃごちゃしたことを描いてきたけど、『Lilypop』を撮ってポップ側にあるラブの部分により興味を持つようになった気がします。人と人との共存がポップにだいぶ支えられていると感じるようになったというか。
あとは映画を作るうえで、成り立っていた共同体が何かしらの影響で成り立たなくなって、それをもう一回更新するような物語に興味を持っていて。『Lilypop』の場合、成り立っていた共同体の関係性が、それぞれがラブとポップについて考えるなかで変わっていくということを描いたとも言えるのかもしれません。
虚実にはいろいろな層があるなかで、嘘でも本当でもない「切実なもの」が映っているか
─関係性の変化については、鈴木さんが『Lilypop』に寄せた文章で、「もう気が合わないとか、あの子は変わってしまったとか、そんなことはもはや当たり前で、それぞれが生きてきた中に、ある一点、偶然に深く重なり合った時間があるという事実だけで、十分幸せだと思う」と書かれていたのが印象的でした。関係性の変化について、鈴木さんが考えたことを知りたいです。
鈴木:それまでも映画や作品の題材として扱ったりしていたけど、『Lilypop』を撮った頃から、自分自身でも関係性について考えないとだめだと思うようになりました。もともと私は幼稚園から高校まで14年間一貫の女子校に通っていて、同じ友達と一緒に大きくなりました。そのなかで、私は常に、仲が良い友達との2人組がいくつかある状態で、関係性のゴタゴタもなくて。
『Lilypop』でりりかの同居人のエナちゃんの役を演じた絵真とは実際に一緒に住んでいたんですけど、そこで初めて、高校生の頃まで私が人と接していたやり方には限界があるんだと感じました。それまで他人の変わりゆく関係性を俯瞰しているだけだった自分が、『Lilypop』の撮影を通じて人と深く時間を共有したことで、自分の良くない部分から逃れられないことや、自分がどうしたいのかをはっきり人に伝える必要があることを初めて実感していったんです。
二人で住んでいたとき、自分ができなかったことはたくさんあるけれど、大きな時間の流れを振り返ると、お互いの人生のなかで重なり合った楽しい時間があった事実は変わりません。一度そういう経験をして、それぞれが今は別の場所で楽しく過ごしているのはごく自然なことだと思うようになりました。
─作品ではエナとエナの“分身”が出てきますが、本物と分身、現実と物語の境目がわからなくなっていくように感じました。
青石:僕も、どのシーンのエナが本物なのか、分身なのかがわからないくらいにしたいと思っていました。わからなくすることで、どっちも受け入れるみたいな。本物と偽物の境目がなくなり、他者として、どちらとも付き合っていくことを描きたかったです。
この映画は、実在の人物の関係性に着想を得ているけれど、あくまでフィクションです。その点でも、嘘でも本当でもないけれど、何か意味があるものを映したいと考えながら撮ったような気がします。嘘と本当の判断基準もいろいろで、脚本があるかないかとか、実際に起きたかどうかとか、いろんな層がありました。判定可能な嘘か本当かではなく、切実なものが映ってるかどうかが基準だったのかもしれません。そういう難しさのなかに自分を放り込んで作りました。
─確かに、エナの“分身”の存在や彼女と過ごす時間は、「あったかもしれない」「あったらよかった」未来のようにも見て取れました。
鈴木:映画を撮ってるときも、りりかを演じながらどっちがどっちかよくわかってなかったです。
青石:可能性を生きることや過去や未来を生きることができるのが映画の強みだと思うので、その試みでもありました。
鈴木:私が作ってた映画も、自分がやりたいことの再現的なものが多かったんです。ファミレスで喋るとか、自分が過ごしたい時間を映画のなかの自分が過ごしているみたいな。
─鈴木さんはその後、どんな作品を作っているのですか。
鈴木:大学の卒業制作で、やりたいことを全部やり切ってしまったんですよね。その後、フィクションで作っていた内容よりも現実の楽しさが上回ってきてしまったので、わざわざフィクションを作らなくても別にいっか、と思うようになりました。大学院に進学した後は粘土をやったり絵描いたりしてたんですけど、最近は、文章を書くことが多いです。
もともと、写真や映像を撮ろう撮ろうと思うと絶対撮れなくて。イベントで人と会うときにカメラを持っていくとか、撮ることではなく、楽しみに行くことをメインにしています。撮ろうと思って撮ってないから、みんなも撮ってることに気づいてないんですよね。だから、出てきた写真や映像を見て、またみんなで楽しむ状態が生まれます。
青石:『Lilypop』も時間を過ごすという意識で撮りました。脚本があって、演じてもらいながら過ごす。その傍らにずっとカメラがあるみたいな。自分が映画を作るときは割とそんな感じです。何かを完成させる手順というよりは、一日のなかに演技をする時間があって、過ごしていくと映画がいつの間にかできているような。
鈴木:移動するとき、青石さんはキックボードに乗って、みんなはチャリに乗って、そういう時間を含めて楽しい撮影期間でした。監督が青石さんじゃなかったらありえない、成立しない作品だと思います。
青石太郎
映画監督。1989年東京都出身。
2012年武蔵野美術大学造形学部映像学科卒。2016年より同大学非常勤講師。
主な作品、『楽しい時間』(2025/45分)、『手の中の声』(2023/18分)、『Lilypop』(2022/103分)、『交歓距離』(2019/84分)、『時空は愛の跡』(2018/158分)、『自由』(2017/227分)、『ジェット ストリーム』(2014/41分)、『PLEASE PLEASE ME』(2012/84分)。
主な上映、グループ上映会「発光ヶ所」@三鷹SCOOL(2024)、イメージフォーラム・ヤングパースペクティブ (2014、2017)、第9回 大阪アジアン映画祭・特集上映 「青石太郎という才能」(2014)、第34回 PFF・日本ペンクラブ賞(2012)。
制度的な集団制作ではなく個が生み出すものとして、映画の新たな在り方を制作や発表の場において探求している。
鈴木理利子
武蔵野美術大学在学中の『Between hate &like』(2021)がイメージフォーラムフェスティバルで入選上映。卒業制作の映画『Episodic memory』は東京学生映画祭・実写短編部門で最優秀賞を受賞。東京藝術大学美術研究科先端芸術表現専攻を修了。現在はコンテンツレーベル黒鳥社に勤めながら、創作活動を継続している。
プロフィール
『Lilypop』
2025年11月22(土)よりシアター・イメージフォーラムにて公開
監督:青石太郎
出演:鈴木理利子、渡邉龍平、松下絵真、秋田海風、大田晃
撮影:北尾和弥、藤田恵実
制作:吉本香音、塩野歩実
タイトルデザイン:あきたあもう
ビジュアルデザイン:久保心花
宣伝協力:ALFAZBET(アルファズベット)
WEBサイト:past inc.
2022 | 103分 | 日本語 | カラー | 3:2 | ステレオ
作品情報
各回上映終了後、本作監督の青石太郎とゲストのトークを開催。
【第1週(11/22-11/28)20:05の回 終了後】
11/22 (土):金川晋吾さん(写真家) 、鈴木理利子さん(本作主演)
11/23 (日):新谷和輝さん(映画研究者) 、鈴木理利子さん(本作主演)
11/24 (月•祝):七里圭さん(映画監督)
11/25 (火) :☆本作撮影部トーク 北尾和弥さん(映画監督) 、藤田恵実さん(シネマトグラファー)
11/26 (水):トークなし
11/27 (木):黒川幸則さん(映画監督)
11/28 (金):清原惟さん(映画監督・映像作家)
【第2週(11/29-12/5)20:45の回 終了後】
11/29 (土):トークなし
11/30 (日) ☆出演者トーク 鈴木理利子さん、渡邉龍平さん、松下絵真さん
12/1 (月)、12/2 (火):トークなし
12/3 (水):金子由里奈さん(映画監督)
12/4 (木):トークなし
12/5 (金) :☆青石太郎(監督)による挨拶
イベント情報
me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら
*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。
あわせて読みたい
連載
Stranger(東京・菊川):連載「あの映画館に行こう」
カフェ併設、話題の新作から独自の特集企画まで、DJイベントやオリジナルマガジンも
2025/11/05
2025/11/05
SPONSORED
女子高生カップルの主体的な別れを描いた『サラバ、さらんへ、サラバ』洪監督×首藤凜
韓国出身でレズビアンとして生きてきた洪先恵が当事者として描く女性同士の恋愛
2025/09/25
2025/09/25
ポレポレ東中野(東京・東中野):連載「あの映画館に行こう」
ひとつの物差しで測れない、インディペンデント映画の豊さを展開する
2025/08/20
2025/08/20
SPONSORED
初監督作で人生の選択とその揺らぎを描く。映画『オン・ア・ボート』ヘソ監督インタビュー
渋川清彦、松浦りょう、山本奈衣瑠出演の映画『オン・ア・ボート』が完成するまで
2025/02/17
2025/02/17
「フィクションとポエジーの力で絶望を乗り越える」川上さわ監督インタビュー
20歳で撮った初の長編『地獄のSE』。大きな力に奪われないために
2024/11/16
2024/11/16
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。