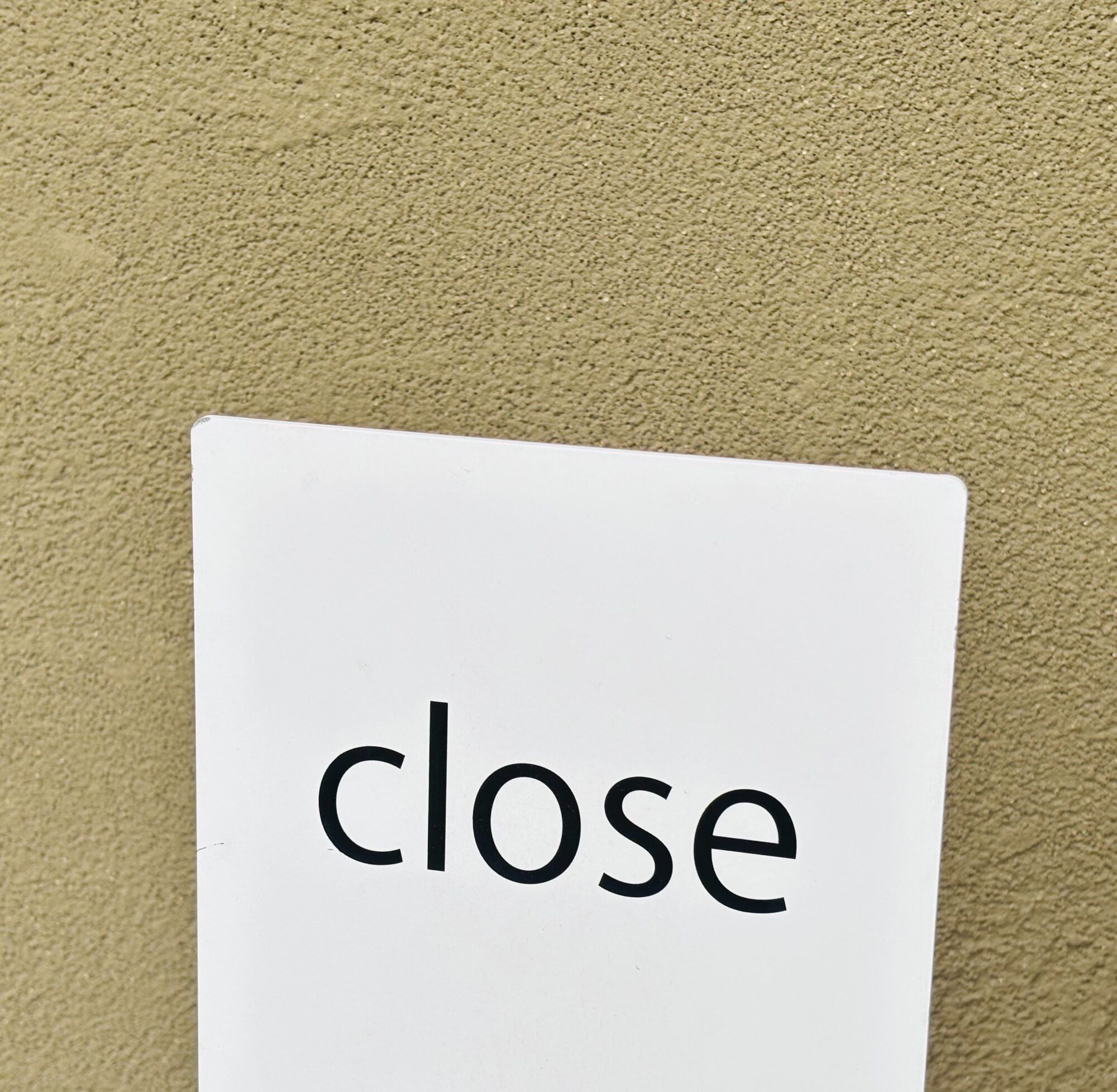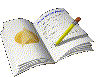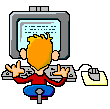9時半に起きる。同居している家族が福岡市まで出る用事があるというので、ついでに私も車に乗せてもらうことにする。今日は雨が降るらしく、空模様はいかにも「一歩手前」という感じ。私がちょうど帰る時に、雨足が一番強くなるらしくて。運転しながら家族が面倒くさそうにつぶやく。
同じ日の日記
着地しないまま漂う/セメントTHING
「偶然性と予見性は、生活のなかでモザイク状に組み合わさっている」
2025/9/8
月更新される、同じ日の日記。離れていても、出会ったことがなくても、さまざまな場所で暮らしているわたしやあなた。その一人ひとりの個人的な記録をここにのこしていきます。2025年5月は5月21日(水)の日記を集めました。福岡県出身・在住のライター、セメントTHINGさんの日記です。
今回ありがたくも依頼をいただいて、こうやって日記を書いているわけだが、実を言うと普段から日記はつけている。内容としては本当に他愛もないもので、その日食べたものがおいしかった、なんだか今日は気分が悪かった、程度のことしか書いていない。けれど、自分が感じたことの「断片」が蓄積されていくのにはわくわくするものがあり、なんとなく続けている。
SNSを何年も続けている理由も、そのあたりにあるのかもしれない。私の書き込みの一番の読者は、間違いなく私自身だ。ツイートを読み返すたび、断片的な文章からその時の感覚が生々しく蘇る。自分自身というよくわからないものに一歩迫れた気になる。日記とは、私という存在の「切れ端」を意図的に作り出す行為なのかもしれない。断片から全体を理解しようとする試みとして。
そういえば、おとといKBCシネマで観たアラン・レネ『ジュ・テーム、ジュ・テーム』(1968年)もそんな内容だった。暗い記憶を抱えた男が、新型タイムマシン実験の被験者となり、過去へと飛ばされるSF映画……なのだが、その時間旅行の仕組みが変わっているのだ。男は何回も過去へタイムリープするのだが、それには時間制限があり、一分だけしか行くことはできない。また、過去の出来事に対して行動を起こし、干渉することも不可能だ。そのため映画内で起こる「タイムスリップ」は、細切れになった自身の過去を、何度も追体験するというものになっている。
『ジュ・テーム、ジュ・テーム』予告編
これはSF的な設定を通し、追憶にまつわる感覚を探求する作品だと思う。私たちがなにかを「思い出す」時に頭に浮かぶのは、印象に残ったある瞬間、日常の切り取られた一部分だ。あの時はああいうことがあった。そういうやり方でしか私たちは過去と現在を理解することができず、自身を把握することもできない。しかも思い出すたび、受ける印象も気になる細部も変化していく。そういう心の動きを、時系列も因果関係もごちゃまぜなモンタージュで表現する。面白い映画だなと思ったし、ふと考えてしまうぐらい印象に残っている。
というようなことを考えているうちに、車はいつの間にか福岡市内に入っていた。もうすぐ降りなければならない。私はいつもとりとめのないことばかり考えていて、思考が一直線にまとまることは珍しい。夕方に行く予定の美術館の営業時間。午後2時から図書館で上映する映画の内容。これから行く予定のケーキ屋さんの住所。それらが全て頭のなかに浮かんできて、どれから確認すればいいのか戸惑う。常識的に考えれば、次に行く場所の情報を調べるべきだろう。そう理解はしているのだけれど、「調べる」という行動へと、気持ちと身体が移行してくれない。むしろ季節外れの花粉症のせいで、鼻詰まりがひどいほうが気になる。
柴崎友香『あらゆることは今起こる』(医学書院)を読んだ時、困っているのは私だけではないのだなと思った。この本で描かれる、いくつもの時間や思考が複線的に展開し、同時進行している……という感覚について、思いあたるふしがけっこうあったからだ。また、それらを具体的な日常の場面を即して語ってみせる文章の、細部へ向ける明晰な視線には感銘を受けた。私もこのように自分の感覚を解きほぐしてみたいと思う。そのためにはまとまった文章を、もっとたくさん書いていく必要があるのだろうが……
決めかねる。決め「かねる」状態が続くのはいいことだと思う。
明快な視座に整理されない状態に留まる。思考が着地しないまま漂う。
福岡市地下鉄に乗り、赤坂駅で降りて、4番出口から地上へ出る。大名のスマイルマーケットの近くにあるチャリチャリのポートから自転車を一台借りる。これは福岡市をはじめ全国で展開しているシェアサイクルサービスで、利用料金がとにかく安いのでよく使っている。雨はまだ降っていない。
自転車に乗って、今日行く予定だった桜坂のパティスリー、オーフィルドゥジュールへと行く。Instagramで見かけた季節限定のケーキ、クロケットアナナスを食べようと思う。ここのケーキにはいつも驚かされる。味わいが濃厚で、苦さや酸味がはっきりと効いている。わかりやすく「おいしい」で片付けられない、複雑な味わいを提示してくる。そんな挑戦的なものが、すこし背伸びすれば手に入るのはうれしい。あらゆるものが高くなっていき、前と同じ生活を送るのにより多くの費用がかかるようになっている。そうなるとどうしても失ったもののほうが、得られたものよりも大きいと感じてしまう。けれど新しいものが見つからないというわけではない。
目的地へ近づく。悪い予感がしはじめる。いつもだったら、もう店へと出入りする人が目に入る距離なのに。もしかしたらと思い、店の前へと足を進めると、やっぱり閉まっている。定休日。なんで私は地下鉄に乗る前にそれぐらいのことを調べておかなかったのだろう。
ただ同時にやるべきことが立ち消えになって、すこし気持ちが軽くなる。私はここに来ようと決めた時に、事前にどんな内容を日記に書くかほとんど決めていたのだが、それが正しかったのか確信がもてなかったからだ。
ここのケーキはいつも私の想像を軽々と超え、知らない世界を垣間見せてくれる。そういえば前に、ここで「イゾセル」というケーキを食べた。オーナーシェフが修行したパリの高級ホテル、「ル・ブリストル」の名パティシエが考案したケーキを、再構築したものだ。なんて優雅なケーキだろう。そう思って後日調べて、そのパティシエが数年前に亡くなっていたのを知った。私はル・ブリストルに行ったこともないし、彼の存在もその時まで知らなかった。けれど私は彼が心血を注いだものに触れていたのだ。ある人が確かに生きていたという事実は、いろんな形で世界に残る。
↑大体このようなことを新作ケーキの感想に合わせ書こうと思っていた。
この内容はすべて私が本当に思ったことである。書く意味のある内容だと思ったし、こうやって読み返してみてもそれは変わらない。
けれど「感じるべきこと」を事前に固めておくのに、違和感があったのは事実だ。「どこかへ行ってなにかをする」ことが、いつしか情報の確認作業になる。コントロール可能な範囲に、すべてを収めることを選んでしまう。どこへ行っても、自分の頭のなかから一歩も出ていくことができない。うっすらとした息苦しさ。
とはいえ、五感を開いて偶然性へと身を投じましょう、それこそが本当の意味で生きているということなのです、という立場もしっくりこない。私たちの生活は不断に変容していく。情報化の加速はただの前提だ。それ以前のあり方はもう想像できない。
結局のところ、バランスの問題なのだ。二項対立的な構図はわかりやすいけれど、それは観念的な図式化で、日々の実感からはズレている。偶然性と予見性は、生活のなかでモザイク状に組み合わさっている。重要なのはきっと、どちらも素直な気持ちで楽しんでみることなのだろう。
そんなことを考えていると、雨がぽつぽつと降ってくる。次の目的地の福岡市総合図書館まではやや距離がある。バスに乗るべきだろうか。
自転車で図書館へ向かう。雨はまだ小雨程度だったから、これぐらいなら耐えられるかなと思ったのだ。でも実際のところ、このスピードで移動していると、それなりに濡れる。あてが外れたなと思ったが、不思議と解放感がある。朝起きた時にこんなことになるとは全く思っていなかった。でもなぜかこうなっている。それがとても楽しい。
街をゆく人の雨への対応はまちまちで、傘をさしている人もいれば、濡れるまま歩き続ける人もいる。ちょうど傘を使うか使わないかの境界線なのだろう。みな宙吊りのなかで、決めかねている。すこしためらった空気に満ちた、エアポケットへと滑り込んでいくようだ。
西新駅に到着する。まだ上映まではしばらく時間があるし、昼ごはんを食べることにする。ここで再び自分の期待を裏切ってみたいと思い、駅前のフレッシュネスバーガーに入る。やや高めの価格帯なので、あまり普段は使わないバーガーショップだ。でも、だからこそ入りたくなる。ネットで見かけた、限定メニューも食べてみたかったし。
店に入りメニューに目を通す。あった。「爆草パクチーチキンバーガー」。限定ドリンクとのセットだと、クーポンを使っても1960円! けれど私にはケーキが食べられなかったぶん、浮いたお金があるのだ。それを全部突っ込む。
店員さんが言う。「爆草入りま~す!」。思わず吹き出しそうになる。そりゃそう。爆草。爆草だけれども。ふだん爆〇〇って言うことなんて、爆笑ぐらいしかないよ。あと、爆走? でもレース漫画ぐらいでしか使わないなあ……
そして爆草がやってくる。バンズの代わりに肉を挟むのは、大ぶりなサラダボウルぐらいの、ありえない量のグリーンリーフとパクチー。トレイの半分を占めるその圧倒的なサイズ感に、「爆草」が正確な表現だったことを悟る。
ほんとに爆じゃん……そう思うと自然と笑いが漏れる。やはり新しい出会いはあるのだ。ここに来るまでのすべての流れが、なんだかひとつの達成であったかのように感じる。
福岡市総合図書館に到着し、上映ホールに入る。この図書館には日本屈指のフィルムアーカイヴがあり、収蔵作品を定期的に上映している。なかでもアジア映画の充実度は素晴らしく、ここにしかプリントが残っていない作品もあるらしい。鑑賞料金も安いし、いつ来ても空いているし、そのうえレアな作品も拝める。映画ファンにとってはありがたい場所だ。
また単にあまり観る機会のない映画が鑑賞できるというだけではなく、上映企画もおもしろい。最近は「アジアの女性映画監督再考」という企画を定期的に行っている。これは女性たちによる周縁化された過去の達成に光をあてようという、世界のアート界の動きとも連動するものがある。地方都市に住んでいても、そのような世の趨勢と無縁というわけではないのだなと感じる。
今日の上映はフィリピンから、ローリス・ギリエン『アメリカン・アドボ』(2001年)。ニューヨークで暮らす在米フィリピン人5人の友人グループを描いた作品で、どことなくドラマの『フレンズ』のような趣がある。私は2000年代のロマンティック・コメディが好きなのだが、そういう作品にも通じる軽妙な雰囲気があるなと感じた。ただアメリカとフィリピンの間で生きる葛藤、おいしそうなフィリピン料理を囲んでの会話、同胞への深い愛情などには、移民映画らしい味わいがある。制作年を考慮すれば、セクシュアリティの描写において思いがけず果敢に掘り下げたところもあり、2000年前後のニューヨークの風景も含め、なかなかおもしろく観た。
けっこうよかったな。そう思って図書館から出て、どうしても頭から離れないある疑問をすぐに検索する。映画に出ていた、あのプレイボーイ役の俳優。どこかで観たことがある気がするのだ。
答えはすぐに出た。パオロ・モンタルバン。出演作を遡って驚く。ブランディ版『シンデレラ』(1997年)の王子様!
『シンデレラ』の映像化は数え切れないほどあるけれど、私がなんといっても好きなのはドリュー・バリモアの『エバー・アフター』と、ヒラリー・ダフの『シンデレラ・ストーリー』、そしてこのブランディ版である。ホイットニー・ヒューストン(劇中ではフェアリー・ゴッドマザーを演じている)が制作者に名を連ねたこのテレビ映画は、多様な人種の役者がメインキャストを演じている。当時としては異例の試みだったが、四半世紀たった今では、理想的なシンデレラの映像化のひとつとみなされている。
その理由はもちろんその先進的なキャスティングもあるし、観ていてとにかく楽しい映画であるのも大きいだろう。カラフルな美術、ウィットに富んだ脚本。ロジャース&ハマースタインの流麗なメロディ。それをパワフルに歌いこなすホイットニー、ブランディ、バーナデットの素晴らしい歌声。そしてパオロ演じる王子様の、後にブロードウェイを席巻した甘い歌声も魅力的だ。90年代の楽観的なムードを結晶化させた、とてもチャーミングな映画である。
ブランディといえば、私はティンバランドと組んだ『アフロディジアック』(2004年)が好きだ。当時から変わったことも多いけれど、2000年代前後の曲や映像に感じるノスタルジアは、あまりに強烈で抗いがたい。
Brandy – Afrodisiac (Official Video)
追憶に浸るというのは、ネガティブなことのように思える。前に進むことが正しいと言いたいわけではないが、どことなく後ろめたく思ってしまう。
けれどブランディ版『シンデレラ』が、後年の積極的な再評価によって、現代のクラシックとしての地位を確立したように。2024年に『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』でブランディとパオロが再び共演し好評を博したように。私たちが過去へと向けるまなざしは、目の前の世界を変えることのできる可能性も秘めている。
過去とどう向き合うかが、私たちの「いま」と「これから」を形作っていく。それは常に多義的な営みだ。昔の作品を鑑賞しそれについて語ることは、同時にいまを更新していく試みでもある。
そんな視点に気づけたのは、柴崎祐二『ポップミュージックはリバイバルをくりかえす』(イースト・プレス)のおかげだ。「過去の再文脈化」がもつさまざまな可能性とその意義を、音楽史を通し多角的に論じていくこの本。語られきったように感じる「リバイバル」や「ノスタルジア」という言葉について、ここまで安易な着地を避け、深く追求できるのかと驚いた。何度でも立ち返りたい一冊である。
……なんて考えながら、ついでに図書館の雑誌コーナーでもチェックして帰ろうかと思ったが、そろそろ次の目的地に行かないといけない。福岡タワー近くのバス停に向かう。海外からの観光客と一緒にバスを待ち合わせる。東京や京都ほど頻繁ではないけれど、福岡でもこんな風景はもう当たり前になった。
20分ほどして大濠公園に着く。降りようとすると、私の横にいた観光客が、すぐにどうぞと立ち上がってくれる。
福岡市美術館につくと、もう4時半。5時半には閉館するから、急いで見て回らないといけない。急いで企画展《テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする》への会場に入る。
一歩足を踏み入れると、まずは会場デザインに驚かされる。SKWATが担当したそれは、会場中央の倉庫スペースを囲むように単管パイプが空間全体に張り巡らされており、広々としたフロアが複数のセクションに区切られている。仕切りや壁はあまり多くはなく、会場内をかなり自由に移動することができる。きちんと順路が設定されてはいるものの、どこから観始めても楽しめるように構成されているのが特徴的だ。
そして本展示で語られるのは、戦後イギリスのみならず、世界のデザイン界に絶大な影響を与えたデザイナー、テレンス・コンランの業績と人生である。彼の家族や同僚などが、それぞれの角度からその人物像を語るインタビュー映像。レストランの設立や家具の制作、革新的な販売戦略から大胆な再開発計画まで、あらゆるジャンルを越境する仕事の記録。彼についてのさまざまな書籍や、いまもなお人気の「ザ・コンランショップ」の雰囲気が感じられる物販コーナー。「テレンス・コンラン」を構成する断片の数々が会場中に散りばめられ、それらを通してその人となりが感じられるような展示だった。
そもそもこれだけ多様な仕事をしてきた人物だと、その活動全体のどこに焦点をあてるべきなのか、迷ってしまうこともあるだろう。だが挑戦的な会場構成によって、そのような「いろんなことに興味をもつ」姿勢が、まさにテレンス・コンランの活動の核心をなしていたのだと、直感的に理解ができるようになっていた。
断片から全体が見えてくる。
いや、もしかしたら、とりとめのないようにみえる断片こそが、そのままでその人の本質なのかもしれない。
5時半ぎりぎりに美術館から出ると、雨はますます強くなっていて、街をゆく人はみんな傘をさしている。もうためらう余地はない。私も傘をさすことにする。
そのまま電車に乗って、家へと帰った。
この文章は5月22日から、5月30日にかけて書かれた。
me and you little magazineは、今後も継続してコンテンツをお届けしていくために、読者のみなさまからサポートをいただきながら運営していきます。いただいたお金は、新しい記事をつくるために大切に使ってまいります。雑誌を購入するような感覚で、サポートしていただけたらうれしいです。詳しくはこちら
*「任意の金額」でサポートしていただける方は、遷移先で金額を指定していただくことができます。
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。