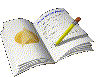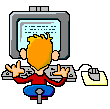都内の商業施設で子供のトイレを待っているあいだ、近くの椅子に座っていた別の子供が持っていたジュースを盛大にこぼし、母親が小さな悲鳴をあげた。ひたひたと地面にりんごジュースが広がっていく。
拭くものを何も持っていなかった私はトイレにあるペーパータオルを思い出し、それをとりに行きますねと声をかけたところ、同じタイミングでそれに気付いた百貨店の販売員さんもかけつけ、みんなでわちゃわちゃする時間があって、そのまま事態は収束に向かっていった。
驚くことにすぐ隣に座って同じく子供の授乳を待っていたであろう見知らぬ父親が、隣にいるにもかかわらず、我関せずの状態。まるでその異変に気付いていないのかと思うくらいに、スマホからひとときも目を離さずにいた。
***
子供が生まれてからというもの、まわりのことがとかく気になるようになった。公共の場所で困っている人がいたら、お節介かもしれないけれど声をかけてしまう。反対に、私が子供と二人で電車に乗っているときに席を譲ってもらったり、エレベーターや電車のなかで隣り合わせた老夫婦や旅行客と短い会話を交わしたり、そんなカジュアルなコミュニケーションも圧倒的に増えた。
しかし、東京という街はとにかくパーソナルスペースが狭く、バリアも強固である。私の場合も例に漏れず、一人の時にはイヤホンから大音量の音楽を流し、雑踏の中でどうにか自分だけのセーフティゾーンを作っていた。個を消し、群衆のなかに紛れ込んでいくことに苦心していた。
人も情報も多いからこそ、きっとそうやって誰もがアイデンティティを、安寧を保つ。だから電車で隣に座った人と話すことなんてなかったし、隣の部屋に住んでいる人の顔さえ知らないなんてことも普通。「横顔しか知らない」ならぬ、横顔さえ知らない状態だ。
***
この都市自体がそういう偶発的な会話とか出会いを許容するようなかたちをしていないのだと思う。誰かの顔を見る必要なんてなくて、群衆のなかの一人として、ただ移動したり仕事をしたりするための、じつにマーケティング的な設計がなされていて、生きている私たちそれぞれのことなんてお構いなしというか、すごくちぐはぐな感じさえする。
フェミニスト地理学(あるいはジェンダー地理学)という視点があるそうだが、いかにこの都市が男性的な設計によってできているのかということを痛感する日々。駅ではたくさんの大人たちによってエレベーターが占拠され、商業施設へ行けば子供のおむつ替えスペースの隣になぜか存在する喫煙スペースに人が群がっている。
どう考えても、実際にそれらを使いたい人にとって、最適とは思えない配置をしているけれど、きっとそれらを使う当事者以外にとってはどちらも商業スペースのおまけでしかなく、まとめてどこか端にでも置いておけばいいのかもしれない。きっと設計をしている人たちには、設備を使う人々の顔は見えていないのだろう。想像したことさえないのかもしれない。
でも、私は使う側の気持ちを知ってしまった以上、いろんな人の顔を浮かべてしまう。目の前に、隣にいる人の顔を見てしまう。困った顔をしていたら、咄嗟に声をかけてしまうかもしれない。どちらが正しいということもないし、あまりに多すぎる人々が集まって経済活動を営んでいる都市においてはある程度の合理性が必要だとも思う。それでも私は明日もちょっとばかりまわりを見ながら、のんびりと歩いていくのだろう。