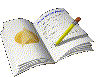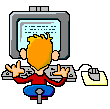創作・論考
me and youが話す『サポート・ザ・ガールズ』。道は一つじゃないから「正解」を描かない
正しさを押し付けないエンパワリングな映画。アフタートークをレポ
2022/10/28
スポーツバーを舞台に、日常の生活に蔓延する女性蔑視や人種差別、労働問題に友情と信念で立ち向かう女性たちを描いた映画『サポート・ザ・ガールズ』。10月からシモキタ – エキマエ – シネマ『K2』で上映が始まり、ゲストを招いたトークイベントがいくつか開催されました。me and youではその様子をお送りします。
今回は、映画の配給を行っているGucchi’s Free Schoolの降矢さんを交えながら、me and youの竹中万季と野村由芽が行ったトークをお届けします。なぜ、彼女たちは連帯しなくてはならないのか。ケアすること、支援することの難しさ。答えが出なくても考え続けることの大切さを投げかけられるこの映画について、me and youの活動で大事にしていることとも重ねながらお話しました。
※本記事では、映画のストーリーについても一部触れています。
降矢:『サポート・ザ・ガールズ』は2018年にアメリカで公開された映画で、Gucchi’s Free Schoolではもともと2020年頃に日本での上映の準備をしていました。コロナ禍で実際には今年の上映になったんですが、お二人には2年前からトークをしていただきたいというお声がけをしていましたね。
野村:初めて『サポート・ザ・ガールズ』を観させていただいた2年前から現在までの間に世の中の状況も変わってきたと思います。#MeToo運動が広がったのが2017年頃ですが、それから映画業界も含めさまざまな場面におけるハラスメントの問題が明らかになってきて、インティマシーコーディネーターのような仕事の認知度も上がっていくなかで、本作の見え方も変わったんじゃないかという話をしていました。万季ちゃんは2年越しに観てどうでしたか?
竹中:前にGucchi’s Free Schoolさんからお声かけいただいたときはCINRAという会社でShe isというメディアを運営していました。去年会社を辞めて2人で独立して新しくme and youをつくっていく過程で、遅ればせながら世の中に存在していた問題に気づいていった部分もあったからか、前回観たときとはまた違った感想を持ったんです。前回は、「(主役の)リサ最高、エンパワーメント映画だ!」という印象が強くて、今回も前回と同様にすごく力をもらえる映画だと思ったんですが、それだけではなく、いろいろな問題が描かれていることがより鮮明に入ってきました。
野村:たしかに。『サポート・ザ・ガールズ』ってタイトルもエンパワリングですが、エンパワーしなければいけない状況があることの方に思いを馳せるようになった気がします。なぜ彼女たちが連帯しなければならないのかということだったり。気になったのが、最後に面接を受けたシーンの後、あの3人がどうなったのか。映画では描かれていないので答えはないけれど、皆さんがどういうふうに思ったか知りたいと思いました。
竹中:明らかに差別的なオーナーの元で、リサはマネージャーとして働いている女の子たちと信頼できる関係性を築こうとがんばっていたけれど、次の面接で訪れている会社は女の子をものとして扱っているような、利益しか考えてないようなところでしたよね。行くのかな? わからない……!
野村:私も最初は、それこそ3人で新しくお店を始めたらいいじゃんって思ってたんです。でも、『サポート・ザ・ガールズ』と『アザー・ミュージック』のパンフレットを兼ねているGucchi’s Free Schoolさんの雑誌『ムービーマヨネーズ 3』に寄稿されている文章を読んで、どういった場所にいても、立ち向かっても立ち向かっても次の問題が出てくることってあるよな、と思いました。その問題に対して映画での彼女たちは「泣いて笑って騒いで叫ぶ」を繰り返していく。そうやって少しずつ進んでいくんじゃないかという感じがしたので、リサは面接を受けた会社に行くのかもしれないとも思って。
竹中:リサが行ったら、完全に資本主義社会の権化となってしまっているあの会社も変わっていくのかな。
野村:きっとすぐには変わらないし、そこで働く選択肢もあれば、独立して違う組織を1からつくるという選択肢ももちろんあると思うんですけど、いずれにしても、自分たちの守りたいものを確かめながら、やり方を考えながら前に進むだろうという感じがしました。個人を大事にしながらお金を稼ぐことがなかなか難しい構造のなかで、自分たちなりに奮闘しながらやっていくんじゃないかと。皆さんの意見も聞きたいなと思います。
竹中:ね、聞いてみたいですね! そもそもこの映画の舞台である「ダブル・ワミーズ」というお店自体が、女性たちが胸を見せて仕事をするような場所です。『ムービーマヨネーズ3』にアンドリュー・ブジャルスキー監督の声明文も載っているんですが、そこで私がはっとしたのが、「私たちのほとんどは、生活費を稼ぐために狂った『コンセプト』を売ったりしなくてはいけない」という言葉でした。
ダブル・ワミーズという場所自体が性を商品化している場所だから、主人公のリサもそれに加担してるんじゃないか、という見方もしようと思えばもちろんできると思うんです。でも、そもそもお金を稼ぐ手段がないなどの社会的な要因があり、差別的なオーナーがいるという状況で、リサは女性がお金を稼ぐことができる既に存在している場所を、精一杯いい場所にしようとしている。今の日本の社会とも重なるところがあるなと思いながら観ていました。
野村:そうですよね。割り切れなさというか、すぐに解決はしないけれど、考えていくべきことが扱われているように思いました。例えば、リサたちがお金をサポートして助けようとしていた年下の女の子(シャイナ)がいましたよね。「自分はこういうふうに考えている」と意思を持ってるけれど、その意思が傍から見ると危険に思える場合、本人に対してどう接することができるのか。映画を観ているとリサたちは心配したうえでシャイナをサポートしたり注意したりしているのだとわかるけれど、今を生きるシャイナからしたら、自分の人生で今大事なものを大事にしたいという場合もあるじゃないですか。そういうときに異なる経験をもつ人同士がどう関わっていくのかという、答えがないことを描いてるのもリアリティがあると思ったんですよね。
竹中:そうですね。ひと言では答えが出ないような、矛盾を孕んでるかもしれないけど考えていかなくてはいけない、考え続けなければいけない、いろいろなテーマが1時間半くらいのなかにぎゅっと入ってる作品だと思います。
他者をケアしながら働くリサ。組織自体がケアリングになるにはどうしたらいいのか
野村:リサは家庭でケア労働を担っている人のような役割を背負って、職場でも仕事をしていますよね。例えば「子どもを預かってもらえるところがない」と言う従業員がいるからお店で預かったりとか。リサは困っているスタッフへのサポートを全部買って出て、同時にそのことに対して愚痴も漏らしている。一方で自分のことを利己的だって言ったりもするから、周りのケアをすることで満たされている部分もあるかもしれないんだけど、でもやっぱり奉仕しているような働き方でもあって。誰かをケアするように働くことは世の中に必要だと思うから、リサにもちゃんと返ってくるような循環する形で、組織自体がケアリングになっていくにはどうすればいいのか、すごく考えさせられました。今は、他にやってくれる人や組織的なサポートがないからリサがケアするしかないみたいな状況じゃないですか。
竹中:それまでリサがいろいろなケアをしたりとか、シャイナにお金を貸したりとかもしていたけど、リサが「お金を返して」と言うシーンがありましたよね。あそこでシャイナは「誰かを助けるってことはその人の生き方に口を出すっていうこと」といったことを言ってたじゃないですか。あの言葉をどういうふうに受け取ったか、話したいです。
野村:これは私が感じたことですけど、リサ自身も「自分ももしかしたらそうなってたかもしれない」と気づくようなシーンでもあったんじゃないかなと。サポートや支援について考えながら、抱樸で困窮者支援をされている奥田知志さんとお話ししたことを思い出しました(「石原海×奥田知志対談 善と悪の両方を掴みながら、その狭間で生き続ける」)。支援の場では、なにかを解決するために相手を一方的に理解しようとすることで、場合によっては支配と変わらない関係になってしまいかねないけれど、その人自身の中に「またやってみよう」といった気持ちが湧いてきたときにそばにいられるかが勝負といった話をされていて。それを「併走型の支援」とおっしゃっていたんですけど、そのことを思い出していました。
映画の後半で、屋上でリサを含む元同僚3人で「また新しい家族になろうよ」みたいな話になったときに、「やっぱり家族じゃなくて友達で」というようなことを言うシーンがあったじゃないですか。家族でもいろいろな形があるし、決して家族的な関係を否定するわけではないんだけど、家族より友達として横にいる感じがいいというのが、シャイナの話とちょっと繋がっている感じがして。親になってあげなきゃ、面倒を見てあげなきゃ、というような気持ちは、時にうざったく感じることもありますよね。
竹中:前半のリサはみんなの親のようでしたよね。でもシャイナは「それはもういいよ」と。1回目に観たときは、リサみたいな人がああいう形で存在していてくれたらすごくいい場所だな、とリサのあの立ち位置をポジティブな部分だけ受け取っていた部分があったんですけれど、今話していたような支援の形だったり、じゃあどんな場所づくりが可能なのかのような話は、いい悪いで決めることや、これだったら正解と言い切ることが難しいということを映画から受け取りました。
野村:お店の常連のボボのキャラクターもよかったですよね。気になったことがあったら言って、でも、みんなから「口突っ込みすぎないで!」みたいなことも言われたり(笑)。でも闘うときはすごく味方になってくれて手助けしてくれるという、まさに「横にいて見ている」キャラクター。作中で明言はされていなかったですが、『ムービーマヨネーズ3』のなかでも、ボボはおそらくFtMのトランスジェンダーの設定ではないかと書かれている方もいらっしゃいました。ボボとメンバーたちとの連帯みたいなものが描かれていることも、それぞれの異なる経験を尊重しながらも、互いの痛みを思いやって手を取り合うコミュニケーションのあり方を少しずつ投げかけてくれているように思いました。全体を通して「これが正解だよ」ということでもなく、「じゃあどうする?」と問いかけているような映画であると感じました。
竹中:そうですね、問いを投げかけてもらえる作品でした。さっき由芽さんもあの3人がどうなっていくか問いかけたくなったように、「続きはどうなるの!?」というところで終わるじゃないですか。最後のシーンも、どういう道だってあるしどれだから正解というわけではない、という終わり方がすごくよかったなと思います。
強い女性がなにかを変えた、改革した、あるいはリベンジした。そういう物語ではない
野村:降矢さんはもともとどうしてこの映画を配給したいと思ったんですか?
降矢:実はすごく単純な動機が強くて、本作を観たとき、ポスターの一番手前にいる、ヘイリー・ルー・リチャードソン(メイシー役)という俳優さんのファンになって。かわいいし、元気だし、知的な部分もあるし。好きな俳優の映画を自分の手で配給するってすごい夢があると思いました。
降矢:一方で、今お話しいただいていたように、答えが出なくて、これが正しいと押し付けない部分もいいなと。今までこういう映画って、例えば強い女性が出てきて、なにかを変えた、改革した、あるいはリベンジした、というお話が多かったんじゃないかと思います。もちろんそういう映画も素晴らしいと思うんですが、一方で、本作はなんとも言えないところや曖昧なところを真摯に描いているのが、ユニークに感じたんです。こういう映画をみなさんに知ってもらうのは難しいと思いつつ、今大切なんじゃないかとも思って、上映しています。
僕から見るme and youさんの素晴らしさは、いろいろな人たちのお話を聞いて、悩みやもやもやを抱えてる人たちの場をつくっているところだと思います。「こういうことをしましょう」「こういうことがいいことですよ」と強く押し出すほうがもしかしたら浸透力や突破力があって、すぐに広がっていくかもしれないですが、さまざまな人の声を私とあなたの関係性で聞いていく。それはとても時間がかかることだし、答えが簡単に出ないことだけど、しっかりやられている。リサとも共通する態度がとてもいいなと思って、お二人にお声がけしました。話を聞くこと、あるいは答えが出なくても考え続けることについて、お二人がどう思われてるのかお聞きしたいです。
野村・竹中:ありがとうございます。
野村:ムービーマヨネーズにも寄稿されている、労働の問題をよく扱っている西口想さんと前に話を聞くことの難しさについて話しました。一人ひとりの話を聞いていると収拾がつかなくなってしまったりまとめるのが難しかったりするから、聞けないということもあるんじゃないかと(「武田砂鉄さんと長い話をする。男性なのに、ではなく男性だからマチズモを語る」)。時間の制約がそうさせるかもしれないし、スキル的なことがそうさせるのかもしれない。そもそも前提として速度が求められているようなところで一人ひとりの話を聞くことができないとしても、それは個人のせいではないと思います。
でもやっぱり話を聞くことを大事にしたいのは、シンプルに一人ひとりの話が大切だと思うからかもしれません。一つの大きいものに回収されていく世の中は怖いなとと思うので、そうならないように、小さくとも一人ひとりの個人的なストーリーをちゃんと残しておく、ということが大事だと思うんです。
竹中:今由芽さんが言ってくれたことは私も同じように大切にしてることです。いろいろなことを共有している由芽さんと話していても、意見や考え方がまったく違うときがかなりあるんですね。出会う前までに生きてきた環境が違うとか、もっと根本的になにかが違うとかもあるのかもしれないですけど、こんなに近くにいる私と由芽さんであってもやっぱりわからないこととか、わかりえないこととか、一つに括れないことがある。そうやって一人ひとりは異なっていて、けれど同時に、話を聞いていけば重なるところもあるかもしれない。そういったことをよく二人でも話しています。
さっき降矢さんもおっしゃっていたと思うんですけど、わかりやすいほうが売れたり、数が見えやすかったりしますよね。もちろん場面によってはそういったものも必要だと思うんですけれど、それだけになった世界に自分たちが生きていたいのか、と考えると、一つひとつをつぶさに見ていくほうを好んでいきたい気持ちがありますね。
野村:『サポート・ザ・ガールズ』はわかりやすい話とは言われないかもしれないけれど、私たちの話だ、という感じはすごくしますよね。大きいストーリーにまとめられない無数の私たちが描かれていると感じました。
プロフィール
『サポート・ザ・ガールズ』
(2018年/アメリカ/93分)
監督:アンドルー・ブジャルスキー
出演:レジーナ・ホール、ヘイリー・ル・リチャードソン、シャイナ・マクヘイルほか
配給:Gucchi’s Free School
配収の一部を<日本映画業界の「ジェンダーギャップ・労働環境・若手人材不足」を検証し、課題解決するために「調査および提言」を行う非営利型の一般社団法人・Japanese Film Project(通称JFP)>に寄付するそうです。
上映情報
書籍情報
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。