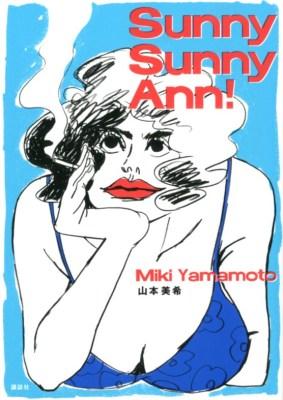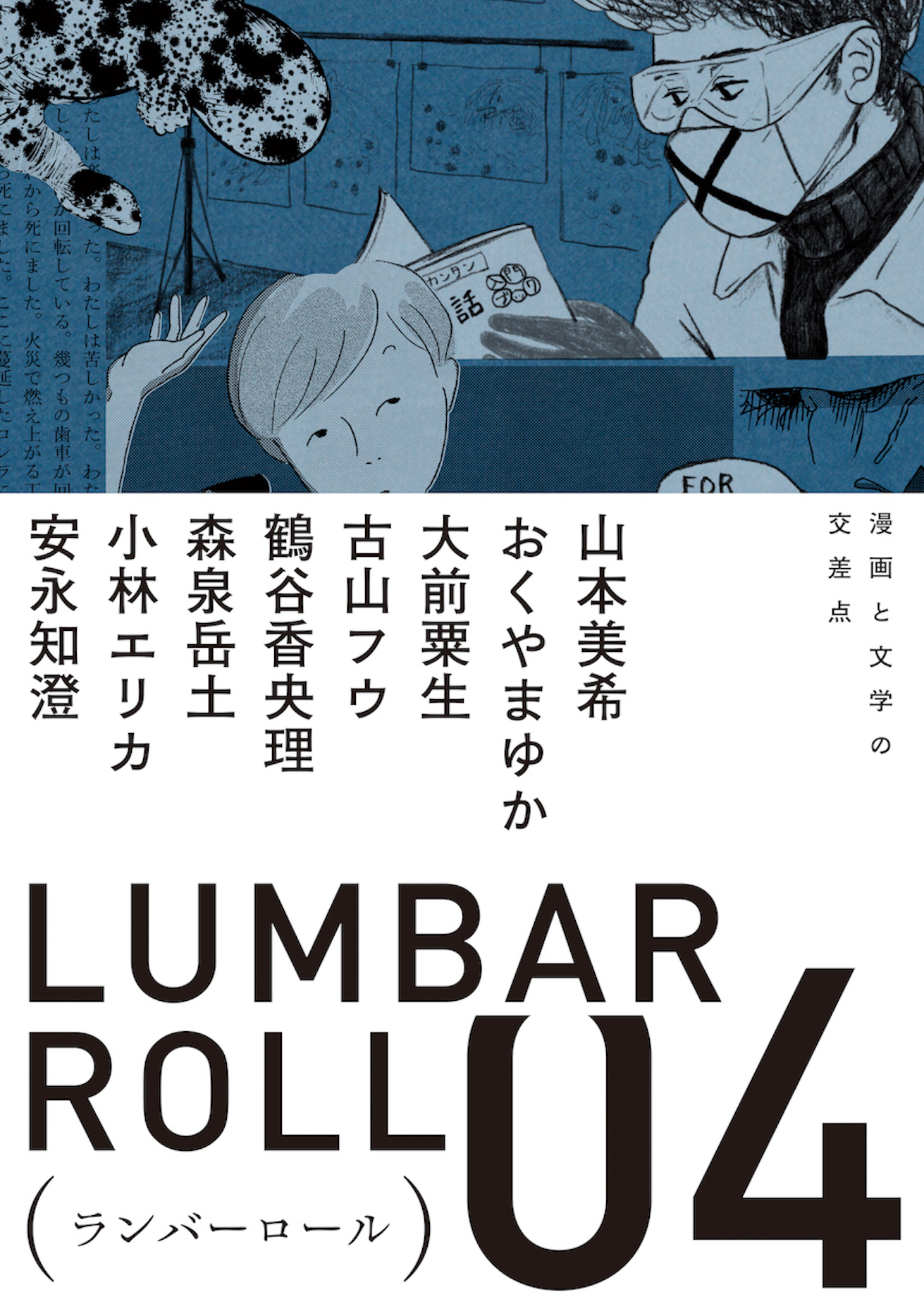漫画家 山本美希×映画監督 淺雄望 ジェンダーや表現の揺らぎに向き合い創作する
『ミューズは溺れない』や『ハウアーユー?』両者の作品を巡って
2023/3/23
妊娠、出産をとりまく不安や期待を描いた漫画『かしこくて勇気ある子ども』や、拠り所を失い壊れていく異国人妻の姿を描いた『ハウアーユー?』などで知られる漫画家の山本美希さん。愛情や友情、将来といった答えの出ない問い、そこに接続する社会への不安、漠然とした「なにか」の手がかりを探るように、丹念に心の機微が描かれます。
そんな山本さんが、偶然出会ったのが淺雄望監督の初長編作品『ミューズは溺れない』。美術部の高校生たちが創作を起点に進路やセクシュアリティ、恋愛といったさまざまな問いにぶつかり、迷う。そんな高校生たちが過去の自身と重なり、パンフレットを片手にサイン会に並び、興奮のまま熱い思いを監督に伝えたそう。そして淺雄監督も山本さんの作品に励まされた一人だと言います。
二人の邂逅を祝福して、映画と漫画における創作や「女性」の活躍、アイデンティティの揺らぎ、社会と創作の接点など話を交わしました。悩みが重なったり、「どうしてですか?」と深く質問をしたり。互いの言葉を大事に受け止めた、尽きることのない時間でした。
─山本さんが映画『ミューズは溺れない』を観られたのは、どういうきっかけだったのでしょうか?
山本:パートナーの実家がある広島に帰省した際、映画館に行きたいという話になったんですね。そのときちょうど広島出身の監督が凱旋上映されるという情報を見つけて、足を運んだのが『ミューズは溺れない』でした。
─映画を観られて、いかがでしたか?
山本:感想をまとめるのが難しいくらい、いろんな感情がこみ上げてきました。身体の芯からふつふつと熱い気持ちが湧き上がってくる感覚になって。その日、上映後に監督の舞台挨拶があったんです。そのときに話されていた内容も、まるで自分の気持ちを代弁してくれているかのようでした。普段考えていることや課題に思っていること、それらすべてがはっきりと言語化されていました。
淺雄:ありがとうございます。上映後にわざわざご感想を伝えに来てくださって、とてもうれしかったです。
山本:初対面なのに、恥ずかしいくらい熱弁してしまいました(笑)。
─山本さんの琴線に触れた点は、どのような部分だったのでしょうか?
山本:まず絵を描いたり創作をしたりする場面が出てくる映画が好きで、主人公が美術部所属というのが、私と個人的に重なったこともあります。
あと恋愛で悩む高校生たちの姿が描かれていましたが、主軸は「自分は何者なのか」ということだと感じたんです。何をやっていけばいいのか。自分の居場所はどこにあるのか、本当にあるのか──そういう生き方そのものに葛藤して、悩む時間が自分にもありました。その時間がすごくつらかったんですよね。作品を観てその時期を思い出しました。
淺雄:私も脚本を書きながら、これは「人間としての存在の話」だと思っていました。10代のころ、まさに「自分は何者なのか」「居場所はどこにあるのか」という不安と格闘していました。その悩みに対する自分なりの考えを映画に込めたつもりです。すべてを上手く言葉にできないからこそ映画にしたところがあり、決してわかりやすいメッセージを発信している作品ではないと思っています。それなのに、山本さんが深いところで映画を受け止めてくださったことが本当にうれしいです。
山本:淺雄監督に関するインタビューを読み漁ったので、理解度は高いと思います(笑)。その上でお伺いしたかったのがキスシーンのことです。撮影中にスタッフから「キスシーンを入れたらどうか」と何度か提案されても、頑なに突き返したというお話を拝見しました。その意見に賛成ですし、この世界観を守り切ったんだなと思いました。
作品をつくるとき、自分の信じる世界観を守り切ることは難しい。しかも監督は、意見を交わしながら映画を製作していると仰っていたので、相当な労力だったと想像します。
私の場合は基本的にひとりで描きますが、編集者など少数の人が関わっています。たとえば自分の作品に「ここでキスシーンを入れたらいいんじゃない?」と何度も言われたら、くじけてしまう気がする。相手の意見を受け入れるより、「わかってくれないならもういいや」と半ば自暴自棄になってしまいそうです。そこを相手も納得するように粘り強く説明するのは、どうやったらできるのだろうと思いました。
淺雄:説得は私も苦手で……(笑)。できることなら誰ともぶつかったりすることなく、自分が思っていることを表現したいという気持ちはあります。あれこれ言われながら何度も脚本を書き直していると、くじけそうになりますし……。ただ「どうして映画を選んだのか」に立ち返ると、私は映画の「集団で作る」部分に惹かれているんだと思います。
私はこれまでさまざまな創作活動に挫折してきた人間なんですけど、映画だったら私が至らない部分を周りの人がフォローしてくれることで乗り切れたり、新しい方向性が見えてきたりします。さまざまな視点からのアイデアに支えられることで、私だけでは到底生み出せなかった豊かな作品が生まれる可能性があるんだな、と一本映画を完成させて実感したところです。
─「キスシーンを入れたら?」と聞かれたときはどうでしたか?
淺雄:その提案をされたときは正直な話、とてもショックでした。この作品の根幹に関わる問題だったので……。「この先もわかってもらえないんじゃないか」と戸惑いました。ですが、信頼できるスタッフを集めた自負があったので、理解してもらえるまで説得しようと思いました。キスシーンを入れたバージョンのシナリオを書いたら想像しやすかったようで、「たしかにキスシーンを入れるとダメだね」と納得してもらえました。
山本:わざわざ脚本を書いてまで……!
─淺雄さんが考える「映画の集団性」とは反対に、映画とは監督が決定権を持っている印象がある人も少なくないと思います。そうした中で、ご自身にとって「ありたい監督像」は、どのように培ってきたのですか?
淺雄:私は助監督を10年ほどやっていたのですが、その経験が「集団でつくりたい」という考えにつながっているんだと思います。
最も影響を受けたのは、『勝手にふるえてろ』(2017年)などの大九明子監督です。初めてプロの撮影現場に助監督として就いたのが『ただいま、ジャクリーン』(2013年)で、それ以来何本か関わらせてもらっています。大九監督が、まさに集団で映画をつくる意識を持っておられる方で、スタッフの提案をかなり聞いてくださるんです。「脚本を読んで、こうしたらいいと思ったのですがどうでしょうか?」と話をすると、演出や小道具に関する細かい提案も聞いてくださって、かつ作品に取り入れてくださる。「結果的におもしろいものになったよ。ありがとう」とまで言ってくださって。演出意図に沿って各部署がさまざまに創意工夫できる信頼関係が大九さんの現場にはある。それを間近で見られたことは幸せな体験でした。大九監督のつくり出す現場の居心地の良さや、作品の広がりは、私の目指すところでもあります。
「自己の問題意識は、自然と社会につながりますよね」(山本)
─漫画家さんの場合は、個人の価値観や世界観を作品に落とし込むイメージがあります。
山本:私の場合は、自分の感じていること、経験してきたことを題材にしています。ごく個人的な話にならないように意識していますが、それでも大多数が共感するかどうかはわからない。そうした作品でも、「この本を出しましょう」と言ってくれる人が一人でもいれば作品をつくることができます。それは関わる人間の数が映画よりも漫画のほうが少ないからでしょう。
─関わる人数の規模感が違うと、それだけでかなり影響が出るのですね。
山本:漫画は属人的ですよね。作業も一人ですることがほとんどで、個人の考えがダイレクトに反映される。私自身影響を受けた大島弓子先生や岡崎京子先生といった女性漫画家はとくに、そういうところが魅力であり、強さだったと思います。
淺雄:作品のより深いところまで自ら潜って、なおかつ表現に昇華するというのは、ものすごく孤独な戦いですよね。自分と向き合い続けるのは、果てしなく苦しいことのようにも思います。怖くなってしまうことはないですか? 自分がわからなくなったり。
山本:恐怖と迷いの連続です。一つひとつのコマに対して、次はどうしようかと思い悩んでしまうのですが、それが性に合っている部分もあって。私の場合は週刊連載の漫画家さんと違って5年に1冊くらいの緩やかなペースなので、締め切りに追われることがないのも乗り越えられる理由です。「考えていれば、そのうち次のコマが浮かぶかな」という感じで、ゆっくりやっています。
─出発点は個人的なことだとしても、社会的なメッセージとつながるのが山本さんの作品の特徴だと感じています。たとえば『爆弾にリボン』(2011年)の描く思春期の葛藤も社会的な視点があるように思います。
山本:自己の問題意識は、自然と社会につながりますよね。『爆弾にリボン』を描いたのは、中学生のときに自分が制服でスカートを履くようになり、急に外見だけで「女」として扱われるようになったことへの違和感からです。突然の扱いの変化に気持ちが追いつけなかったモヤモヤをそのまま描きました。
作中、学校にあった裸の女性像に卵をぶつけたり、街中や電車で見る「美しい女」を決めつけるような広告に落書きをしたりする場面があります。それは社会への抗議でもあります。一方で、友人同士で制服に落書きをするのはお互いをエンパワメントする手段として描いたもの。
絵を描くことが日常だったので、「描く」行為にさまざまな感情を乗せてしまうんです。淺雄監督がものづくりをしている子を主人公にしたのはどういう狙いだったのですか?
淺雄:私自身がものづくりへの欲求が止められなくて、挫折しつつもしがみついてきた人間なので、同じような境遇の人たちを描きたい気持ちと、肖像画を描くという行為そのものに魅力を感じたからです。たった一本の線でその人を描くことは難しいし、一色だけでその人を表現することもまた難しい。一人の人間を描くために線や色を重ねていくアクションを通して、「人間は多面的である」ということを表現したいと思いました。
「『セクシュアリティは揺らぎ続けてもいい』と言ってもらい、自分を苦しめていた枠組みが取っ払われたような解放感があった」(淺雄)
─人間の多面性という意味で『ミューズは溺れない』はアイデンティティやセクシュアリティの揺らぎがテーマとなっています。山本さんも「自分とは何者か」「居場所はどこにあるのか」迷いながら葛藤した日々があったとお話されていましたが、淺雄さんがこのテーマで映画をつくられた理由を教えていただけますか?
淺雄:そもそもこのテーマを選んだのは、10代のころ、自分自身が女性であることにものすごく劣等感を感じていたからです。劣等感の原因は女性に対してポジティブなイメージを持てなかったからだと思います。幼少期から「女の子は結婚をして子どもを産むのが幸せだ」とたくさん言われてきたし、「女の子なんだから我慢しなさい」と諦めさせられる場面も多かった。女性らしさを期待されるたびに、期待に応えられない自分をどんどん嫌いになっていきました。
高校生のとき、自己嫌悪がマックスまで到達し、女に生まれてしまったことを息苦しく思うようになりました。キリスト教系の高校に通っていたのですが、あまりにつらくて牧師の先生に相談しに行ったんです。「女として生きるのがつらいです」と。そうしたら先生が「じゃあ女、辞めてみたら?」と。「男として生きてみてもいいんじゃない? 男として生きた先にやっぱり女に戻りたければ戻ってもいいし。どっちでなくてもいい。セクシュアリティは揺らぎ続けてもいいものなんだよ」と言ってくださったんです。
山本:素晴らしい先生ですね!
淺雄:周囲の求める「女らしさ」に適応できないままでも、生きていていいんだと肯定してもらえたような気持ちでした。同時に、誰よりも私自身が「男性らしさ」「女性らしさ」という枠組みに縛られていたことにも気がつきました。自分を苦しめていた枠組みが取っ払われたような解放感がありました。
山本:私も淺雄監督と同じように、中高生のときは「女性らしさ」の圧に息苦しさを感じていました。そんなときに私を支えてくれたのが女性作家さんの描いた漫画です。大島弓子先生の『赤すいか黄すいか』では、毎月の生理に苦しむ女の子がその辛さに思い詰めて医者に行き、生理を止めてもらおうとします。吉田秋生先生の『櫻の園』も、胸や身長など自分の身体と、それに折り合わない気持ちや社会との摩擦を描いています。
それらの作品が自分の悩みに答えをくれたり、答えはなくても同じ状況の人がいることを教えてくれたりして、どんどんのめり込んでいったんですね。そうして「私もここを耕す一人になりたい」と思いました。映画でそういう作品を思いつかないのですが当時、淺雄監督の支えになってくれたような映画はありましたか?
淺雄:そういう意味では、当時支えになるような映画を私は見つけられませんでした。むしろ社会における女性の弱さを痛感させられ、息苦しさを助長させられることのほうが多かったかもしれません。憧れたくなるような強い女性像を映画の中で見つけられていたら、考え方も変わっていたでしょうね。10代のときに山本さんの作品と出会えていたら、ここまでの劣等感は抱かなかっただろうなと思います。
「『男性〜』『女性〜』といった性別で映画を語ることがナンセンスになってほしいと思っています」(淺雄)
─映画業界は男性監督・スタッフの割合が高いですが、淺雄さんの中で耕す仲間が増えている実感はありますか?
淺雄:そうですね……ただ一方で、個人的には「女性監督らしさ」を求められることに違和感を抱くこともあります。それは、私自身が10代のころに「セクシュアリティは揺らぎ続けてもいい」と自分の心を既存の枠組みから解放できたにもかかわらず、いざ映画を撮るとなると、場面によって「男性監督」「女性監督」とまっさきにカテゴライズされてしまうことに戸惑いがあるからです。
映画業界に求めるものは、さまざまなセクシュアリティを持っている人が平等に作品に関われる環境づくりです。そのための第一段階として、まずは多様な女性の監督が存在しているという事実を知ってもらう必要があるのだと感じています。
私もその一人として認識してもらうことで、業界のジェンダーギャップ解消に貢献したいという気持ちはあります。ただ一方で、女性という冠に抵抗したい気持ちもあるんです。女性が撮った映画という以前に淺雄望という一個人が撮った映画として観てもらいたい。早く性別の冠が取れて、「男性〜」「女性〜」といった性別で映画を語ることがナンセンスになってほしいと思っています。
─社会の変化に個人が利用される。必要なこととはわかっていても葛藤がありますよね。
淺雄:疑ってかかるような見方かもしれませんが、特別枠を用意することで「ジェンダーギャップなどの解消に貢献していますよ」というアピールだけに終わって、内実が伴っていないのではないかという風に見えてしまうことも映画業界に限らずあります。誰かにとって都合のいいマイノリティ像がまつりあげられる一方で、誰かにとって都合の悪いマイノリティの意見は黙殺されてしまう場面もあるように思います。映画業界は過渡期だからこそ、なにを信じればいいのかわからなくなることがありますし、私だって無自覚に誰かを傷つけている可能性も大いにある。自戒をこめて、自分の立ち位置を見極めなければならないなと感じています。漫画家さんの場合はいかがですか?
山本:漫画では、ペンネームを使う方も多く、性別を公表しない場合も多いですね。私も「女性らしい」「繊細な」などと絶対に言われたくなくて、太いペンを選んだところがありました。
もちろん漫画雑誌には対象とする読者をあらかじめ年齢や性別でわける伝統があります。ただ発表の機会という意味で考えると、男性向け雑誌のほうが部数も読者も圧倒的に多いなか、少女や女性向けとうたう雑誌は小さな声や多様な声を拾う作品が発表できる場になってきたと思います。
いまの表現も先輩方が苦労の上に獲得されてきたもので、たとえば1950年代の少女マンガを描かれていた先生方のお話では、男女の恋愛を描くのは禁止だったとか、初潮の話はダメとか、スカートがひるがえった絵は描き直しさせられたとか……。
淺雄:女性の身体や生理現象は当たり前に存在しているのに、創作物の中でどのように見せるかは難しいですよね。『ミューズは溺れない』では主人公にミニスカートを履いてもらっているんですけど、それは、演じている俳優さん自身の身体から溢れ出る生命力、健康的なエネルギーを、私自身が素直に魅力的だと感じたからでした。ところが、男性の観客から「女性に対する配慮がない。性的な目で見てしまう」と言われてしまいました。
現場の半数が女性スタッフで、撮影時には誰一人として「いやらしいね」という声はあがりませんでした。だけど、そういう意見をもらい、表現の難しさを痛感しました。女性の身体を描くことが多い山本さんは、身体表現についてどう考えていらっしゃいますか?
山本:判断が難しいですよね。『ハウアーユー?』(2014年)に、修学旅行で女の子たちがお風呂に入っているシーンを描いたんですね。漫画でトイレシーンはあまり描かれないのですが、岡崎京子先生はサラッと描かれていました。たしかに生活の中にあるのに、見なかったことにされているのはおかしい。だから描いたのですが……今だったら描かなかったかもしれません。
淺雄:それは意外です。どうしてですか?
山本:言葉にするのが難しいのですが……。私自身いやらしいシーンのつもりでは描いていません。ですが、たとえば『ドラえもん』に出てくるしずかちゃんのお風呂シーンってクリシェのように使われていましたよね。女の子のお風呂を覗いてキャーと言わせたり、スカートをめくる場面などがマンガのなかで「このくらいのこと」と容認されてきました。そのなかに自分の作品が並ぶとき、果たしてどのように理解されるのかなと。私の描いた場面も作品として間違いではなくても、批判的に捉えられる可能性がある気がしています。未成年の女の子の描写ですし……今も迷いはあります。
淺雄:私個人の感想としては、あのシーンをいやらしいものとして見ることは一切なかったので残してほしい気持ちはあります。ただ、おっしゃる通り、いろんな意見が出る可能性はありますよね。配慮したい気持ちもよくわかります。
山本:『Sunny Sunny Ann!』(2012年)の主人公は開放的な人物で、手入れしてない太い眉や脇毛も描いたんです。最近、海外のイラストレーターさんで女性のすね毛を描いている方をけっこう見かけるようになりました。日本の電車では相変わらず脱毛やダイエットを勧める広告を見ますけど、大人の女性の身体のあり方は自由になってきているし、ボディポジティブな表現が増えてきているなと感じます。だからこれからも自分が描くことが何をもたらすのか、できるかぎり想像し、模索しながら創作するしかないですね。
「知らなかったことを知る、考えたこともなかった気づきを得るという経験は社会の価値観を変える可能性があります」(山本)
─最後に、創作と社会の接点について質問させてください。山本さんは『ランバーロール』で、コロナ禍における表現活動の「役立たなさ」を吐露されていました。実感として、社会において創作することの意味をどう考えていらっしゃいますか?
山本:作品で大きく社会が変わるとは思っていません。ただ読者にとって「自分とは異なる考えや悩みを知るきっかけ」になればいいなと思っています。たとえ小さなことでも、知らなかったことを知る、考えたこともなかった気づきを得るという経験は社会の価値観を変える可能性があります。そういう経験の一つに、私の漫画がなっていたらうれしいです。
─淺雄さんもメッセージ性の強い映画を作られていて、社会と創作の接点を強く意識されているのではないかと思いました。
淺雄:私は自分自身が抱えている悩みを題材に、登場人物たちにそれぞれの立場から討論させています。狭いコミュニティではあるけど、そこにも社会がある。セリフの応酬のなかで、新しい視座が見えてくることを目指しています。
『ミューズは溺れない』の中で、西原が主人公の朔子に「人と比べてどう思われるかよりも、自分がどう思うかの方が大事だと思う」と言うシーンがあります。そのセリフは、私が誰かにかけてもらいたい言葉であり、誰かにかけてあげたい言葉なんです。
私自身、まだまだ他人の視線が怖くて、誰かの「こうあるべき」という曖昧な基準に左右されてしまうこともあります。だけど、自分で自分のことを決めてもいい。もし基準からずれていると感じても、無理に合わせようとしなくてもいい。ずれている自分の「立ち位置」を見つけられれば、ずれているなりの戦い方を見つけられるかもしれないし。今回、映画をつくりながら、また上映をしながら、そういったことに気がつきました。
─社会とのずれを確認して、自分の立ち位置を見つめるというのは素敵ですね。
淺雄:企画段階では「わかってくれる人はいないかもしれない」と思っていた『ミューズは溺れない』を、山本さんはじめ、たくさんの方が受け止めて下さった。性別の問題にかかわらず、少数派だと思いこんでいたことが、案外そうではないこともある。『ミューズは溺れない』は社会が期待するものからずれていると思っていたけど「案外ずれてなかったのかな?」とすら思っています。
揺らぐことをよしとしない風潮もありますが、揺らぎ続ける自分を許しながら生き延びる方法を模索しています。そうして模索しながら生まれた映画が、誰かがせめて一呼吸おくための手がかりになるなら、それ以上に幸せなことはないです。
─ありがとうございます。あっという間にお時間がきてしまいました。
淺雄:本当は、山本さんの作品への感想をもっとお伝えしたかったです!
山本:私もいろいろと細かい質問や、前の作品『躍りだすからだ』も拝見したのでその感想も伝えたかったです。またぜひ、お話しましょう!
淺雄:ぜひ、お願いします。楽しみにしています!
淺雄望
1987年生まれ、広島県出身。関⻄大学・立教大学大学院で映画理論・映画制作を学ぶ。在学中に、映写技師のアルバイトをしながら映画づくりを開始。卒業後は助監督などとして映画や CM、テレビドラマの現場に携わる。初監督短編『怪獣失格』(2008)がCiNEDRIVE2009 で上映。その他監督作品に『分裂』(2012)、『アイム・ヒア』(2019)、『躍りだすからだ』(2020)等がある。コロナ禍での一時中断を経て、2年がかりで完成した初の長編映画『ミューズは溺れない』(2021)が公開中。
プロフィール
『ミューズは溺れない』
監督:淺雄望
出演:上原実矩、若杉凩、森田想、川瀬陽太、広澤草、新海ひろ子、渚まな美、桐島コルグ、佐久間祥朗、奥田智美
2023年3月18日(土)ポレポレ東中野にて公開 以降全国順次
作品情報
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。