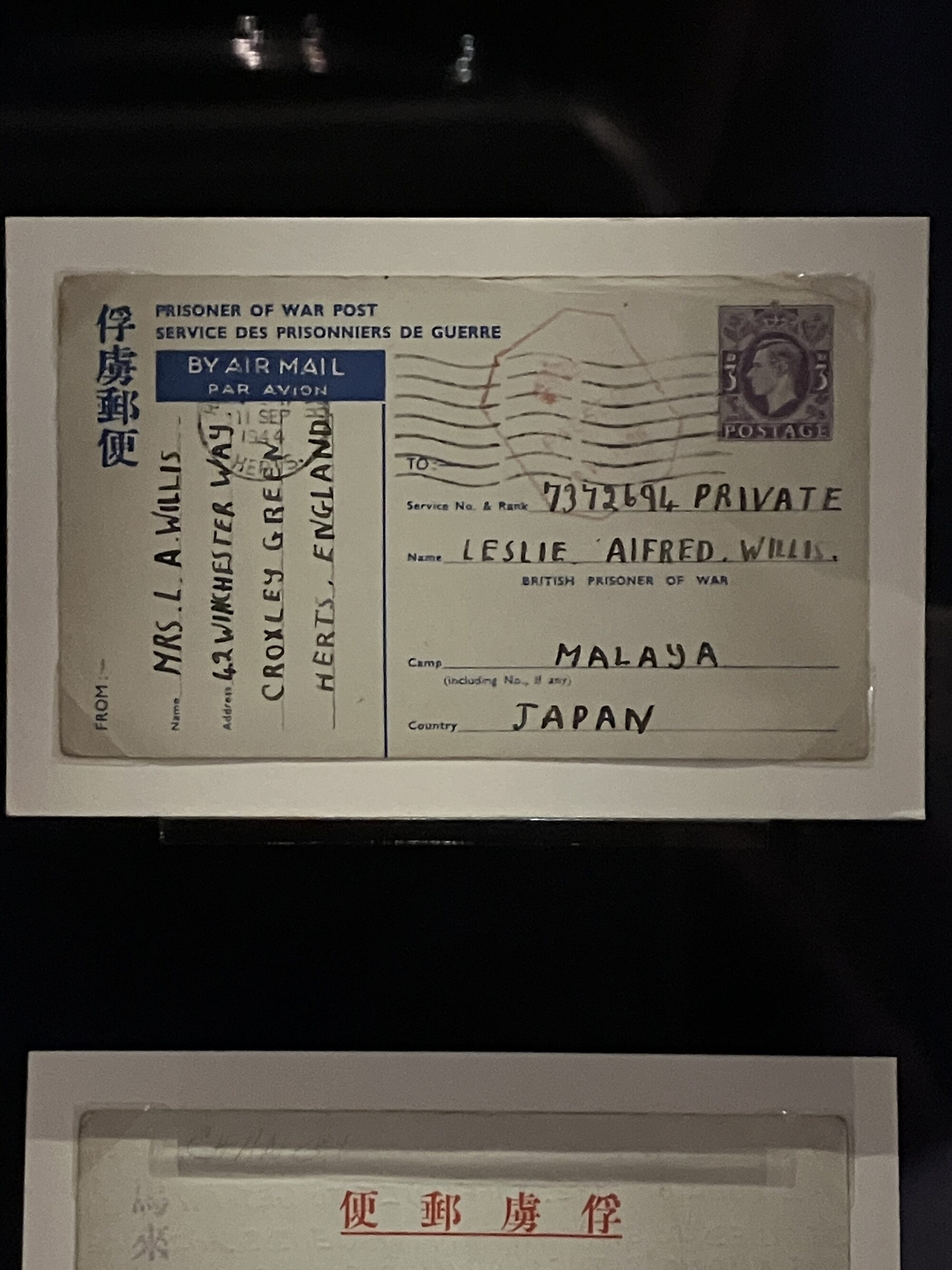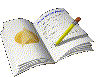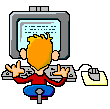シンガポール旅2日目、チャイナタウンのホステルで目覚める。移動の疲れで早くに就寝したけれど、冷房がめちゃくちゃに効いていて寒く、しかもタオルケットや布団の類が一切なくて、二度三度と起きる。最終的にまくらをお腹に乗せたらふとんの重みを再現できてうまく眠れた。
シンガポールと聞くと、でかい船がついたビルの上でインフィニティプールに入って、スパに行ったり、買い物したり、というイメージだったので、ラグジュアリーなものにまったく関心がない私が行ってもいいのだろうか? と思っていた。旅行を計画するときは、インディペンデントな本屋や、喫茶店、小さめのギャラリーなどがあるエリアについて調べることが多いのだが、シンガポールではなかなかそれがみつからない。どんなところにも有機的な文化シーンが必ずあるはずなのに、それがあまり表に出ていないところはたいへん不思議で、だからこそ深く知りたくて行くことにした。
朝はカヤトーストを食べるために近くのホーカーへ。ホーカーは、屋台が集まるショッピングモールみたいな場所のこと。行商人、を意味するHawkerから来ている名前らしい。ガイドに乗っているような場所だから観光客も多いけれど、ローカルの人も普通に来ている。今日は珈琲を出す店は一つしか開いていないようで、少し並ぶ。前に並んでいたひとは、これから会社に行くのか、珈琲を水筒に注いでもらっている。店員さんがテイクアウトを準備する手際の良さについ見とれる。
植物が見たくなって、Fort Canning Parkという公園に行く。公園といっても、街の中心にある小高い丘だ。むかし、灯台や砲台があったことからこの名がついている。東南アジアや東アジアに行くと、どこに行っても自国の植民地主義の跡と向き合わざるをえない。この灯台も、日本軍上陸後はもちろん接収されている。灯台にしては少し海からは遠いように思う。今はビル群が阻んで海はよく見えない。イギリスの植民地時代に作られたのだろう、いかにもコロニアルな庭園を歩いて、暑さで少しぼうっとしながら、なじみのない植物たちを見る。「What To Do When You Encounter Otters」(カワウソに遭遇したときの対処法)という張り紙が出ていて、カワウソ見たい……と思ったけれど会えなかった。