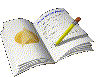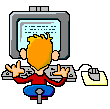山田由梨とパンセクシュアルの10代が語り合う。『虹クロ』収録レポ
違いがあるからこそ自分のことが分かる。性に揺らぐ10代の対話の場
2025/3/31
ようやく可視化されてきた、セクシュアルマイノリティの存在。ドラマや映画のなかに自分を投影できるキャラクターを見つけたり、自分はまた少し違うかもと思ったり。一つのジェンダー、セクシュアリティのなかでも、具体的な経験や悩みはさまざまです。
『虹クロ』は、そんな個別具体的な10代の経験にスポットライトを当てる番組だといいます。“性に揺らぐ10代、自分らしくありたい10代、LGBTQ+の人を応援したい10代たちが、さまざまな分野で活躍するLGBTQ+のメンターたちとセクシュアリティやジェンダー、多様性について本音で語り合う”そう。
新年度1本目となる4月1日放送予定の『虹クロ』のテーマは、「パンセクシュアルの私が人を好きになるということ」。性別に関係なく相手を好きになるパンセクシュアルの10代・ハルさんから寄せられた疑問をもとにスタジオで考えを深めた収録にお邪魔しました。メンターの一人でもある日本文学者のロバート キャンベルさん、そしてゲストとして出演した作家・演出家の山田由梨さんへのインタビューとともに、番組の様子をお届けします。
NHK Eテレが届ける『虹クロ』は、悩みや伝えたい思いを寄せる10代が中心となった番組。『虹クロ』の「クロ」は「クローゼット」から来ています。「カミングアウト」は、“coming out of the closet(クローゼットから出る)”という言葉が元になっており、「クローゼット」は、LGBTQ+当事者がカミングアウトをしていない状態を指す言葉です。
そのため、『虹クロ』では10代の方もスタジオで一緒に語り合いますが、放送では「クローゼット」のアバターとなって登場します。一人ひとりと打ち合わせを重ねながら、その人の好きな色、好きな形のアバターを作るそう。実際に「クローゼット」な当事者は、実生活では自分の思うような表現ができていない場合も多くあります。そのため、アバターとして自分自身の望む姿を表現し、その姿が放送を通して社会に存在することは、大きな意味を持つと想像します。
今回悩みを寄せたのは、性別に関係なく人を好きになるパンセクシュアルのハルさん。自分以外のパンセクシュアルの人と会ったことがないので話してみたい、そしてパンセクシュアルではないセクシュアリティの人が誰かを好きになるときに「性別」が条件になる感覚について話をしたいと連絡をしたといいます。
虹クロでは、“さまざまな分野で活躍するLGBTQ+のメンター”が10代の方と語り合います。今回スタジオに登場したメンターは、モデル・タレントの井手上漠さん、日本文学者のロバート キャンベルさん、臨床心理士・公認心理師のみたらし加奈さんの3人。みたらしさんはハルさんと同じパンセクシュアルです。
さらにゲストとして、レズビアンが主人公のドラマ『作りたい女と食べたい女』や、高校生の性を描いたドラマ『17.3 about a sex』の脚本を手がけた山田由梨さんが登場。『17.3 about a sex』には、パンセクシュアルを自認する登場人物も出てきます。シスジェンダー・ヘテロセクシュアルという立場から、脚本を書くにあたってさまざまなセクシュアリティの人への取材を重ねたといいます。
現在17歳のハルさんは、まず「バイセクシュアル」という言葉を知り、女性に惹かれていたときの気持ちが恋愛感情だったことに気付いたといいます。しかし、その後「パンセクシュアル」という言葉も知ったことで、パンセクシュアルの方がしっくりきたそう。同じくパンセクシュアルのみたらしさんも「最初はバイセクシュアルだと思っていたけど、少し違和感があった」と話します。
「性別を条件とする恋愛がどういうものなのか知りたい」というハルさん。どんな性格の人を好きになるか、どんな時に相手を意識して緊張してしまうかなど、スタジオ全体でそれぞれの経験を話します。男性に惹かれるキャンベルさんと山田さんは「男性だから好きになったわけではないと思うけど、結果的に惹かれるのはいつも男性だった」といいます。一人ひとりの異なる「好き」を共有することで、「ヘテロセクシュアル」「ゲイ」「パンセクシュアル」というカテゴリーでは表しきれないセクシュアリティのあり方や“惹かれ”の性質について、それぞれが思いを巡らせました。
異性愛者がセクシュアリティについて説明を求められないのは特権
「今は自分自身に満足をしているものの、大人になったら社会でどう扱われるか分からない不安がある」というハルさんの言葉を受けて、会う人会う人に説明しなくても済むように、エンタメの力でパンセクシュアルの存在を伝えていきたいと話す山田さん。マジョリティの立場からセクシュアリティに向き合うこと、創作を通して社会と対話することについて聞きました。
収録中「男性を好きになることに疑問を抱いたことはなかったけど、もしかしたら自分の中にもグラデーションがあるかも」と話していた山田さん。「“惹かれ”に関して少し揺れる部分があるかもしれないと思うことはありました。今回の対話を通して、それを曖昧なまま持っていていいんだと改めて思えた」といいます。一方で、セクシュアリティについて問われることがなかったのは特権だと振り返ります。
「セクシュアルマイノリティの方は『同性を好きになるってどういうことなの?』って好奇心で聞かれたり、性行為について聞かれたり、失礼な質問を受けることが多いですよね。対して私は、そういう説明をする必要がなかったし、求められてこなかった。だからこそ、今日みたいに『異性愛ってどんな感じ?』と問われることが新鮮でもあり、少し困ってしまって。セクシュアルマイノリティの人たちは、そういう居心地の悪さを、きっと何倍も強めた形で問われることがあるんだなという気づきがありました」
また、人を好きになる際に性別が条件に入らないパンセクシュアルについて話したことで、今まで無意識だった部分に目を向けられたといいます。
「自分が性別を意識して人を好きになっているとは思っていませんでしたが、パンセクシュアルの方の話を聞くと、たしかに自分は相手の性別を意識していたのかもしれないと思う場面がありました。違いがあるからこそ、『自分の場合はこうかも』って分かるんだと思いました」
脚本家だから知れたことを、媒介者として作品に落とし込む
マイノリティを描いた作品を書く際は事前にリサーチを重ねているという山田さん。日頃からセクシュアルマイノリティの友人と話す機会はあるものの、脚本家という立場だからこそ知れたことばかりだといいます。
「友達とは雑談をすることが多いので、親との関係とか、どういうふうにカミングアウトしたかとか、同性カップルだと家を借りるのに苦労するとか、そこまで踏み入った話はできないですよね。脚本家という立場だから聞けたことがたくさんあると思います。だからこそ私が媒介者となって、そのような話をなるべく丁寧に作品に落とし込んで、多くの人に知ってもらえたらいいなと思います」
一方で、パーソナルな話を聞き出すということは時に暴力的になる側面も。取材の際には、異性愛者としてセクシュアリティを聞き出されない立場にいるからこそ、話をすることがその人にとってどういうことなのか、想像します。
さらに、話を聞いた当事者数人や、自分が読んだ本がそのセクシュアリティのすべてではないと思いながら制作をしているそう。一人のキャラクターが、そのセクシュアリティの代弁者にならないように。同じセクシュアリティでも、環境によって、性格によって、辿る道はさまざまです。セクシュアリティと性格や考えを結びつけてしまうと、個人の差異はもちろん、インターセクショナリティー(セクシュアリティに限らず、人種や性別、階級などさまざまなカテゴリーが互いに作用し格差や抑圧を生むこと)が見えなくなってしまう可能性もあります。
「言葉によって可視化が進む側面もありますが、一つのセクシュアリティのなかにもグラデーションがあります。セクシュアリティを描こうとすると、必ずそこから溢れるものがあると思うので、その属性を背負った一人の個人として書くようにしています」
「完全に理解することはできないからこそ、理解しようとすることをやめたくない」
今回の収録では、マジョリティであるシスジェンダー・ヘテロセクシュアルというSOGI(性自認、性的指向の総称)を持つ人は山田さんのみ。虹クロは“10代の当事者を中心に、LGBTQ+のメンターが相談役となる”ため、山田さんのようなゲストは珍しいそう。しかし、このような番組の作りがあるからこそ、山田さんも一つのセクシュアリティを持つ人として、自分自身について考えられたと振り返ります。
ドラマ『作りたい女と食べたい女』では、主人公の野本さんの友達として、原作に登場しないシスジェンダー・ヘテロセクシュアルのキャラクターも登場しました。知識がないことで傷つけてしまうこと、それでも友達のために何ができるのか考えること。このキャラクターが、物語と視聴者の架け橋になるのではないかと考えたそう。虹クロには個人の悩みが寄せられますが、その先にある社会的な生きづらさに無関係な人はいないということに日々意識的になりたいと話します。
完全に理解することはできないからこそ、理解しようとすることをやめたくない。『17.3 about a sex』の脚本を書いた際に、セクシュアリティについて知らないことがたくさんあると気づいたそうです。
「自分が知らなかったことで、これまで傷つけてきた人がきっといるだろうなと実感したんです。今後出会う人に対しては、できるだけ無意識に傷つけるようなことはしたくないから、もっといろいろなことを知りたい。ただ、違いがある、分からないことがあるということは、相手を知りたいという興味やコミュニケーションが生まれるということだから、とてもいいことだと思うんです。収録でも、話していくことで一人ひとりの違いと共通点がどちらも見えてきた瞬間が面白かったです」
また、脚本で10代の登場人物を描く際や、10代の当事者に話を聞く際は、自分の知らないことを知っている人として関わるようにしているといいます。
「『17.3 about a sex』を書いた時は28歳でしたが、今の高校生は私が高校生だったときとは違う感覚を持っているところもあると思ったんです。だから、自分の経験や持っているイメージで決めつけて書かないようにしたいと、当時高校生だった方々に話を聞かせてもらいました。歳を重ねていって、自分の常識が固まってしまう年齢にもなってきていると思うので、常に柔軟に、変化し続けられるように心がけていたいです」
「この番組が電波に乗って広い場所に届けられていることに大きな意味がある」
2021年の番組開始時から、メンターとして10代の相談者と話をしてきたロバート キャンベルさん。自身にとって、虹クロのスタジオは特等席だといいます。
「セクシュアルマイノリティに対する接し方はここ6、7年でガラリと変わり、現在も変化し続けています。一方で、両親や祖父母にはカミングアウトができないなど、変わらない部分もある。10代の恋愛は、人とどのように渡り歩いていくかという人生のコアな悩みが反映されると思います。そのため、セクシュアリティについて話していたとしても、僕の耳にはセクシュアリティに限らない、これからの生き方など、さらに広い話にも聞こえてくるんです。普段なかなか出会えない10代との対話を通じて、学ぶことがたくさんあります」
また、さまざまな状況の10代と出会ってきたからこそ、番組として声を届けていくことが大事だと話します。
「この番組の面白いなと思う点は、番組が当事者を探すのではなく、当事者が手を挙げてやってくるところです。ネット上で当事者とつながって勇気をもらって、学校という世界のなかで生きようとしている子もいれば、それがうまくできない子もいる。本当に千差万別です。もっといろいろな場所でこのような場が作られるべきですが、この番組が電波に乗って広い場所に届けられていることに大きな意味があると思います」
セクシュアルマイノリティとして生きることは、自身の性自認や性的志向と向き合うだけではありません。他者との関係性や社会的な承認などのさまざまな要素に影響された、一人ひとり異なるリアリティーがあります。個別具体的な経験を通して対話をする虹クロは、悩みを寄せた10代にとっても、テレビの前にいる10代にとっても、自分自身を照らす時間になるのだろうと想像します。
筆者自身も同じパンセクシュアルとしてハルさんの話を聞き、10代の自分と出会いなおすような感覚になりながらも、高校生で「パンセクシュアル」という言葉に出会える時代の変化や、パンセクシュアルに辿り着くまでの道のりなど、同じセクシュアリティ内での違いも実感。「違いがあるから自分自身のことが分かる」という山田さんの言葉を心に留めた収録でした。
山田由梨
1992年東京生まれ。立教大学在学中に「贅沢貧乏」を旗揚げ。俳優として映画・ドラマ・CMへ出演するほか、小説執筆、ドラマ脚本・監督も手がける。贅沢貧乏『フィクション・シティー』(17年)、『ミクスチュア』(19年)で岸田國士戯曲賞最終候補にノミネート。セゾン文化財団セゾンフェローI。主な担当ドラマにNHK夜ドラ「作りたい女と食べたい女」脚本、ABEMA「17.3 about a sex」脚本、WOWOW「にんげんこわい」シリーズ脚本・監督など。
ロバート キャンベル
日本文学研究者。早稲田大学特命教授。早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)顧問。せんだいメディアテーク館長。
近世・近代日本文学が専門で、とくに19世紀(江戸後期~明治前半)の漢文学と、それに繋がる文芸ジャンル、芸術、メディア、思想などに関心を寄せている。テレビでMCやニュース・コメンテーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組企画・出演など、さまざまなメディアで活躍中。
ニューヨーク市生まれ。カリフォルニア大学バークレー校卒業(B.A. 1981年)。ハーバード大学大学院東アジア言語文化学科博士課程修了、文学博士(M.A. 1984, Ph.D. 1992年)。
1985年に九州大学文学部研究生として来日。同学部専任講師(1987年、国語国文学研究室)、国立・国文学研究資料館助教授(1995年)を経て、2000年に東京大学大学院総合文化研究科助教授に就任(比較文学比較文化コース〔大学院〕、学際日本文化論〔教養学部後期課程〕、国文・漢文学部会(同学部前期課程)担当)。2007から同研究科教授。2017年4月に国文学研究資料館館長就任。2021年4月から現職。
プロフィール
贅沢貧乏『わかろうとはおもっているけど』
山田由梨主宰の贅沢貧乏が、『わかろうとはおもっているけど』を2025年11〜12月に東京・久留米・札幌で上演。
『わかろうとはおもっているけど』は現代の日本社会が抱える問題を奔放な想像力と多彩な手法でポップに浮かび上がらせる作風で話題の贅沢貧乏による、男女の性差について問う演劇作品で、2022年にパリで上演し好評を博した。
ツアー日程・会場はこちら
イベント情報
newsletter
me and youの竹中万季と野村由芽が、日々の対話や記録と記憶、課題に思っていること、新しい場所の構想などをみなさまと共有していくお便り「me and youからのmessage in a bottle」を隔週金曜日に配信しています。
me and you shop
me and youが発行している小さな本や、トートバッグやステッカーなどの小物を販売しています。
売上の一部は、パレスチナと能登半島地震の被災地に寄付します。
※寄付先は予告なく変更になる可能性がございますので、ご了承ください。